2017年1月17日,C型肝炎治療薬ハーボニー配合錠の偽物が奈良県のチェーン薬局で調剤され,患者さんに渡ってしまっていたことが大々的に報道されたのは記憶に新しいやんね?
僕もハーボニー偽造品が出た件で奈良のチェーン薬局会社が判明いう記事をアップして皆さんに情報提供をしました。
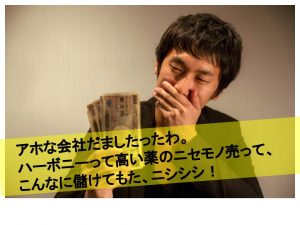
その後,調剤したチェーン薬局の会社名および薬局名と,流通ルートが明かされます。そのことを書いた記事がハーボニー偽造品を売った卸が判明!サン薬局の店名も,偽造品の中身も判明したで!
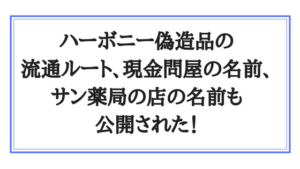
そして,2017年3月7日,関西メディコに対し奈良県と奈良市より行政処分として改善措置と報告を命じるという処分が下りました。
さてさて,具体的にはどんな改善措置と報告を命じられたのやろか?調べてみたで☆
また,この行政処分が下るまでの間に起こった事もおまけで書いていこうと思う。
奈良県と奈良市からの行政処分の対象施設と命令の内容とは?
やっぱりこれが気になりますよね?業務停止とか重い処分でも出たのかな??と。
行政処分の対象となったのは3店舗
今回の行政処分の対象となったのは
- 患者さんに偽造品を交付しちゃったサン薬局平松店
- 偽造品を在庫し保有していたサン薬局平郡店
- 同じく,偽造品を在庫し保有していたサン薬局三室店
の3店舗。
3店舗とも奈良県にある薬局や。
行政処分の内容は?3つの命令と平松店へのさらなる2つの要求
患者さんに偽造品を調剤してしもてるからね,平松点にはちょっと多めに要求があったみたいや。
2つの要求とは
- 事故報告の体制整備
- 医薬品譲渡の帳簿への記載
この2つ。
これを見て,
え?事故報告を会社本部に上げてなかったの?患者さんから問い合わせがあって発覚したのに?
え?他店からの譲渡伝票とか,残してないの?
という2つの驚きを感じずにはいられなかったわ。
どんだけずさんな管理体制になってたんやろか・・・。
そして3店舗共通の改善命令の内容は3つあって
- 医薬品管理の徹底
- 薬品の品質検査の実施
- 構造設備変更時の届け出など
となっていたようや。
②について特に思うんやけど,
現金問屋から外箱無しの薬品を買っておいて品質検査,というかその医薬品の外観などのチェックをしてなかったという点において,サン薬局ってホンマにずさんだったとしか言いようがない。
これはDisってるわけでも何でもなく,
会社として,仕事として,
論外や
としか言いようがなかったと思うねん。
③の命令については,今回どう関係しているのか不明瞭やね。何なんやろ?どういう意味?コレ。
改善命令の報告書の提出は3月14日までらしい
1週間の猶予しかないんやね。
もはや通常営業して業務を行うどころやない状態になっているんやなかろうか?
今もサン薬局の3つの店舗では必死の作業が続いていることでしょう。
行政処分ってこれだけなの?ことの重さの割には重みが足りない??
こういった意見がネット上では散見されるね。
今現在,奈良県と奈良市は,改善措置命令以外の行政処分については
「現在検討中であり,未確定のため発表は差し控える」としてるねん。
個人的には,
悪いけど,保険指定取り消しが妥当やと思う。
理由は明らか
- 命に係わる医薬品の粗悪品を利益目的で安く仕入れ,偽物と気が付かず,チェックもせず患者に渡したこと
- 医薬品を取り扱う保険薬局への信頼の失墜
この2点が重い気がするねん。
過去にあった「食の安全」に対する問題はもっとデカく報道されたやんね?
- 2011年のユッケで食中毒が起こった事件➡その後,刑事罰が設けられ,当該業者は裁判にかけられた(不起訴処分)
- 2016年のCoCo壱番屋の期限切れ冷凍カツ横流し事件➡横流しをした業者は逮捕された
どれも非常に重大な事件として取り扱われたし,報道もされた。
そして,それ相応の処分が下っている。
今回の医薬品の問題は「医療の安全」の問題や
僕は今回の問題は非常に重大な問題なのではないかと思う。
医薬品の流通の仕組みや規制についてもっと考えなければならないんじゃないかな?
現金問屋の存在は確かにありがたい。しかし,法規制はガッチリと固める必要が絶対にある。
そう思うね。
まとめ と おまけ
まずはまとめていこうか。
ハーボニー偽造品事件は会社名も薬局も,現金問屋の医薬品の流れも明らかにされた。
そして現在,業務改善命令が出ている最中や。
さらなる行政処分については何かしらの動きがあるやろうから,もし発表されたときには記事を書こうと思う。
おまけ:ハーボニー配合錠もソバルディ錠もボトル入り包装が廃止されてます!
現在のお姿は,皆様がお馴染みの銀のシートに入った状態になってます。
ハーボニー配合錠&ソバルディ錠400mgヒート製品へ 3月1日から流通開始これは2017年3月1日から流通が開始されている。
なので,ボトルが流用された偽造品はもう登場しようがない。
でも,最初っからこの状態で売ればいいのに。
これを売っているギリアド社って外資やなぁ。新薬のベムリディ錠も,ボトル包装(中に錠剤がバラで入っている)やねん。何故だ,なぜ過去の失敗に学ばないんだ。。。
 けいしゅけ
けいしゅけ 今回の記事はいかがでいたか?
アナタのお役に立てていれば幸いです!
もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆待ってます!!











記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (2件)
初めてコメントさせていただきます。新米薬局薬剤師のタケと申します。
いつも大変興味深く拝読させていただいております。
勤務薬局自体は小児科の門前ではあるのですが、在宅に力を入れている薬局で半年ほど前から、自分も在宅チームに参加を許されました。利尿剤、抗血小板剤と抗凝固剤、ARB、下剤等々、小児科の外来ではなかなか経験できない薬に関する記事は、何回も何回の読み返しながら勉強させていただいております。自分に知識が蓄積されていき、現場で活かせている感覚は、とても嬉しくやる気につながっております。
さて、前置きが長くなって申し訳ありません。
質問と、記事依頼をお願いします。
この度、在宅チームとして、余命6ヶ月~1年、膵臓がん末期の患者様の在宅依頼を受けました。
ベテラン薬剤師(ターミナルケア経験者)が担当することにはなっておりますが、自分も同行させてもらえそうです。
そこで、麻薬を扱う上での、事務上、薬事法上、現場等々での注意事項。
そして、ターミナルケアとはなんぞや?といった、アドバイスをいただければと思います。
お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます!
凄くやりがいのあるお仕事に関わることができていますね、僕はターミナル患者さんの個人在宅には関わったことがまだ無いのです。
外来患者さんでターミナルの方への支援は経験したので、そのうえで言えることは、
ターミナル患者さんを支援するうえでできることは精神的な支えと疼痛コントロールだと思ってます。
疼痛コントロールの上で、医療用麻薬の使用に対する不安は説明で除去できますし、適切な使用方法の説明で確実に痛みをゼロにできます。
吐き気のコントロールは必ずできるし、それを超えれば確実に疼痛コントロールは可能なので、患者さんの最期を痛みのない状態で迎える支援ができると思います。
麻薬を扱う上での、事務上、薬事法上、現場等々での注意事項は、
https://www.jspm.ne.jp/guidelines/pain/2010/chapter02/02_05_01.php
こういったオフィシャルサイトを参考にするといいと思います。僕はガイドラインや文献を参考にしています。
また、疼痛コントロールについては、淀川キリスト教病院が出している、緩和ケアマニュアル http://amzn.to/2lIRh96 が非常に参考になります。
この病院はホスピスがあり、臨床経験上、有効であった疼痛補助剤など適応外使用についてもガッツリと載せてくれています。
僕はこの本を中心に勉強を進めています。