Zettelkastenは、20世紀ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが研究と論文執筆のために考案したと言われている知的生産システムです。彼は70冊の本を出版し、500の研究論文を発表するなど多くの面で成功を収めましたが、その多くはZettelkastenのおかげであると考えています。 「Zettel」がメモを「kasten」が箱という意味を表しており、一つのアイデアを一つのメモに短く記し、それを順番ごとに分けた箱で管理するというのが大きな特徴です。1
Web search resultsから得られる情報によると、Zettelkastenは知識を保存・整理し、記憶を拡張し、アイデアの間に新たなつながりを生み出し、文章の出力を高めることができるツールです。2
本記事が最も参考にしたWebページがコチラ
 けいしゅけ
けいしゅけ”Zettelkastenとは,文章出力という結果を生み出すプロジェクトを進めるためのシステムである。また,最終的に知識の外部保存となる資料自体を『Zettelkasten本体』と呼ぶ。
このシステムは以下の流れで進行する。
気づき・ひらめきを記述すること → 参考文献を記録し,内容を自分の言葉で記す短文集 → 公開文書(公開後は知識の外部保存ノート=Zettelkastenアーカイブとなる)”
まずは,ざっくりと捉えておきましょう⭐
Zettelkastenとは何かを知るためのKey Words
- 一時メモ(Fleeting Note)
- 文献ノート(Literature Note)
- Zettelkastenアーカイブ(Permanent Notes / Structure Notes / Index Notes)
- プロジェクト管理(Project Notes)
Zettelkastenを作り上げる4つの保存先と6つのノート
ノートはそれぞれ4つの保存先に別れており、ノートの種類としては合計6つが存在する。3がZettelkastenと呼ばれているものの本体であり、他の3つはこのZettelkastenを作る補助的な役割である。
| 保存先 | ノート |
|---|---|
| 一時メモ | Fleeting Notes |
| 文献ノート | Literature Notes |
| Zettelkasten本体 | Permanent Notes |
| Structure Notes | |
| Index Notes | |
| プロジェクト管理 | Project Notes |
一時メモ(Fleeting Notes)
思いつき,ひらめき,気になったこと,調べたくなったことetc… あらことをひとまず保存しておくため保存先を用意します。役割としてはインボックスです。Fleeting Notesと呼ばれるノートが定義されていますが,要するにメモの切れ端レベルのものです。単語カード1枚に収まる程度のものをイメージすると良いかも。
Fleeting Notesは定期的に処理されるべきもので、発展させてノート化する価値があるものにならば清書しZettelkasten本体に保存します。反対に,清書されなかった一時メモ(Fleeting Notes)はどんどん破棄しちゃって良い。
- タスク管理におけるInbox(インボックス)って何ですか?
-
タスク管理におけるInbox(インボックス)とは、あらゆるタスクや情報、アイデアを最初に収集する場所のことを指します。これはメールの受信箱のようなもので、未分類のタスクや情報が一時的に保管されます。
日々私たちの周りで様々な事象が起こり、タスクや情報はどんどんと発生します。これらをすぐに処理しきることは難しいので、それら全てを一箇所、つまりインボックスに集めておきます。
そして、ある時点でインボックスを見て、その中にある各タスクや情報を評価し、それぞれ適切な場所に分類したり、適切な手段で処理したりします。これにより、大量の情報やタスクを効率的に管理することが可能となります。
たとえば、メールが届いたら、それはインボックスに入れ、後で一括して処理します。あるいは、新しいアイデアが思いついたら、それをインボックスにメモしておき、後で詳細を考えるという具体的な行動を決めます。
つまり、インボックスは「とりあえずここに置いておく場所」であり、後で整理し、適切なアクションを決めるための一時的な保存場所と言えます。これにより、情報の見逃しや忘れることを防ぎ、効率的なタスク管理を支える重要なツールとなります。
文献ノート(Literature Notes)
インプットした書籍や論文などに関するショート記事(出典として引用した文献をデータベース化したものに,自分なりに一言まとめを加えてカード化したもののイメージ)
最終的に公開する文献は出典を明記する。そのためにも,Literature Notesは出典や引用文だけではなく,これに自分なりの考察を加えておく。文献ノートは,最終的に出力される文章のパーツとなるものと考えれば良いかも。



ちょっと例を書いてみますね。
『もしも大きな仕事を任されるようになった時,僕たちが意識すべきことは諸先輩方のやり方を踏襲することや周囲の評価なんかじゃなく,自分が主体となって結果を出すことのみに集中することなのかもしれない。
”「憧れるの、やめましょう。ファーストにゴールドシュミットがいたりとか、センター見たらマイク・トラウトがいるし、外野にムーキー・ベッツがいたり…と、アメリカチームのスター選手をあげていく。野球やってれば誰しもが聞いたことあるような人がいると思うんですけど、今日1日だけは、憧れてしまっては越えられないので。僕らは今日、超えるために、やっぱトップになるためにきたんで、今日1日だけは、彼らへの憧れは捨てて、勝つことだけ考えていきましょう」2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ 決勝・アメリカ戦の円陣声出しにて 侍JAPANの公式Twitterアカウントより引用”』



『』内の文書がLiterature Notesになるイメージです。ひとまず,このノートに記された文はどこかで使えるかもしれない。文章のパーツになり得るので。実際に書く際には改変することがあるかもしれないけれど。
Zettelkasten本体(Permanent Notes / Structure Notes / Index Notes)
Zettelkasten本体:上述した2つのノート「Fleeting Notes」と「Literature Notes」をもとに自分の考えを清書したものがZettelkasten本体となり,保存版とする感じです。ブログで言うところの記事ですね。
Zettelkasten本体は3種類のノートで構成されます(Permanent Notes / Structure Notes / Index Notes )
- Permanent Notes:自分の考えをまとめたノート(ブログ)
- Structure Notes:複数のPermanent Notesへのリンクを含むまとめノート(書籍で言うところの目次➡カテゴリーページ)
- Index Notes:索引キーワードをまとめたもの(Index Notesは基本的にStructure Notesへのリンク集➡タグ・キーワード集をひとつのページにまとめる)
プロジェクト管理(Project Notes)
一番大枠になるもの。Zettelkastenというシステムを完成させるためのマネジメント・メモって感じです。
具体的には,・着想したことの言語化 ・文章を練り上げる上でどんな参考資料やマニュアルを用いるか ・スケジューリング ・タスクリスト などを記述する感じ。なんだろう,ノートというよりもNotionやGoogleカレンダーを使って全体の進行を自分でコントロールできるツール自体がこれに当たる気がする。
このProject Notesに関しては,僕はNotionが適していると感じていて日々使っています。ただし,使いこなせておらず,思い通りにならなくてモヤモヤしています。
まとめ
📌 ツエッテルカステンとは,アウトプットすることを前提としたPermanent Notes(ブログ記事)へのリンク集を作ることと言える。 まず,Inboxとして,一時メモに思いついたことを書き出す(ノートを携行するか,Notionにページを設けると良さそうだ。口語で書く) 次に,記事作成に当たって参照した参考書などを「Literature Notes」にデータベース化する。これを行うことで今後も改めて使うかもしれない情報を書き溜めておくことが可能になる。論文と書籍で分ける方が望ましそうだ。 最後に,ツエッテンルカステン本体に取り掛かる。思いついたことをプロジェクトノートにタスク化してリストアップする。そして,ブログコンテンツを仕上げていくのだ。プロジェクトノートはブログ記事が完成してしまえば消してしまえばよい。









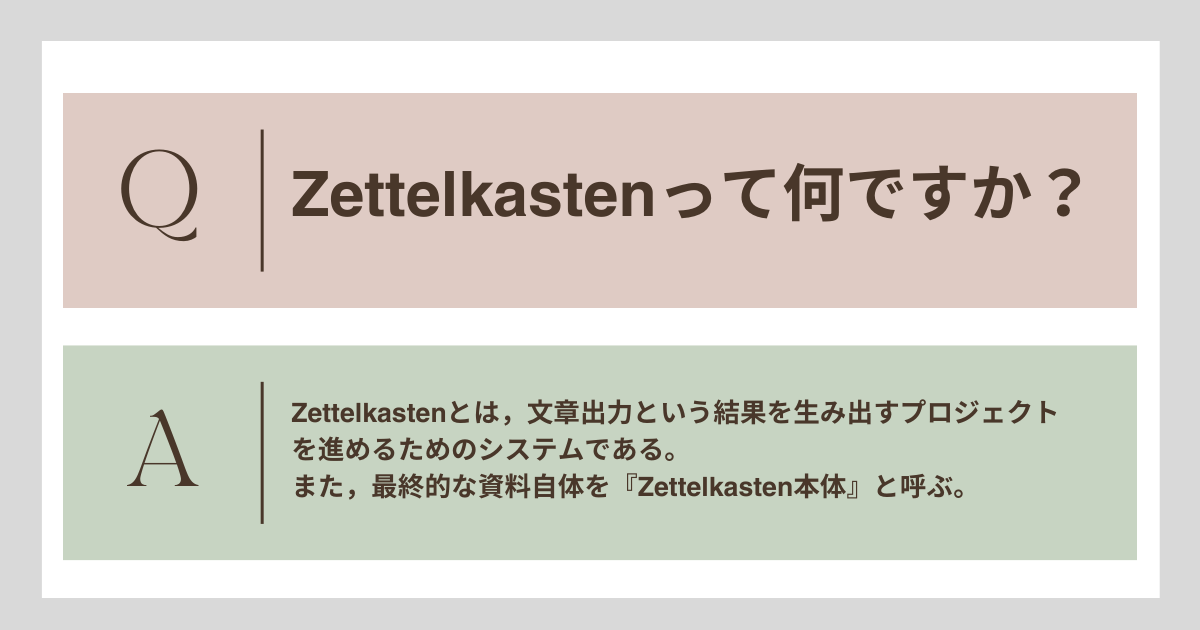
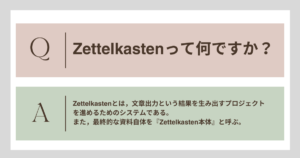
記事の感想など,ひとこと頂けますか?