- 演繹は三段論法と言い換えることができる
三段論法は推論の方式の1つで,大前提と小前提から結論を導く法則のことで,アリストテレスが確立したものや
➡三段論法の例文:鳥は空を飛ぶ➤ヤンバルクイナは鳥である➤よって,ヤンバルクイナは空を飛ぶ
➡三段論法(演繹)の問題点:大前提が間違っていると,結論が正しいと言えなくなるねん。言うまでもなく,例文の大前提が間違ってるやん?だって,ペンギンやダチョウは空を飛ばれへんから。すると,ヤンバルクイナが空を飛ぶってホンマって言い切られへんよね?となってしまうんや。*事実,ヤンバルクイナは空を飛ぶことは出来ない鳥や - 帰納法とは,すなわち調査であると考えれば良い
帰納法は,たくさんの現象を観察した結果「どうも〇〇っぽい!」と推論する方法や
➡帰納法の例:①私が飼っている犬は”お手”をする ②お隣さんが飼っている犬も”お手”をする ③テレビで見た犬だって”お手”をしていた。①~③の結果から,「犬はお手をするものである」っぽい!!と推論すること
➡帰納法の問題点:調査結果を出すための参照データ量が少ない場合,説得力も信ぴょう性もないこと。例文は非常に分かり易いわな?お向かいさんが飼っている犬に何度「お手っ!!」と言っても”お手”をしなかった場合,「犬はお手をするものである」っぽい!!という推論は誤りだという事になるのは明白や。
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
最近読書にハマってんねんけど,『演繹』と『帰納』って何回見てもどういう意味やったっけ??となるねん。皆さんはどうやって覚えた?この記事は,演繹と帰納という言葉の意味がわからなくなったときに何度でも見返せるものを目指して書いています。
コトバは人間とは別に存在する何かを言い当てるモノではない。
ソシュールの思想の概要
何らかの実体の存在がコトバの違いを根拠付けしているのではない。
コトバによって世界は分節され(別けられ)認知される。
コトバが指し示す実体は個物も含めて存在する必要はない。
イデアが実在する必要もない。
- 『演繹』と『帰納』の意味
- 演繹の具体例
- 帰納の具体例










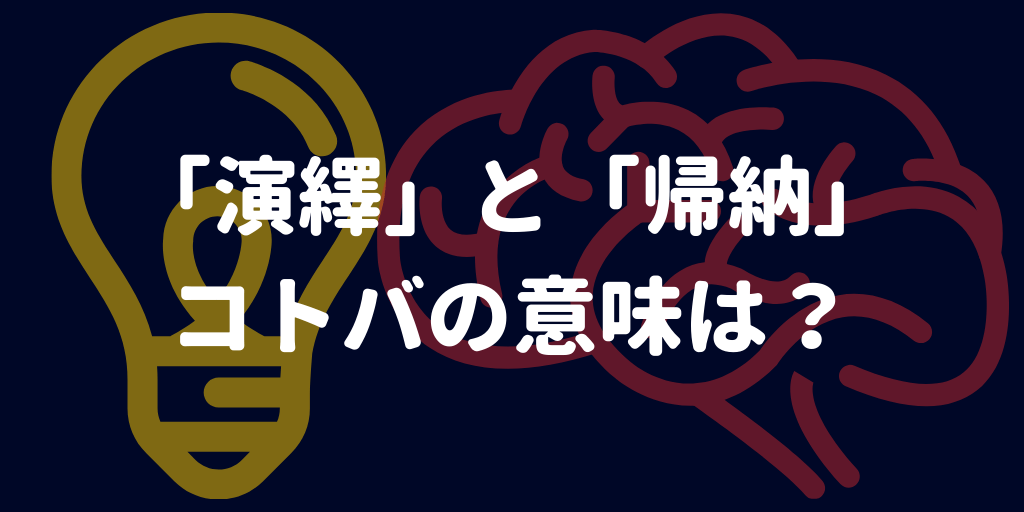







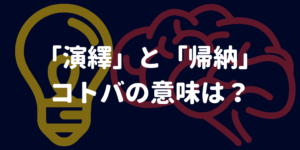
記事の感想など,ひとこと頂けますか?