2020 年 1 月 30 日に発売開始となった 『医療情報を見る,医療情報から見る エビデンスと向き合うための10のスキル 』
この本に関してレビューするとともに,どんな人にオススメかを考えてみました。
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』ってどんな本ですか?
医療情報を読み解く事実判断能力と,それを受け取る人がどう感じるかという価値判断は異なるよね?ということを伝えてくれる本と僕は思います!
『医療情報を見る,医療情報から見る エビデンスと向き合うための10のスキル 』という本は,週刊誌を読んで薬に対して不安を覚えたことがある人や,そうした情報が正しいのか確かめる方法を知りたいと思ったことがある人にオススメの書籍やとぼくは考えています。本書を読むことを通じて,医療情報をどんな視点から理解すると「トンデモ医療」と「正しい医療情報」を見分けられるかを10のスキルを通じて知ることができるでしょう。
しかし,本書の魅力はそれだけにとどまりません。
読み解いた医療情報の正しさ(事実判断)ができるようになることの”向こう側”である,その医療情報にどんな価値観を見出すかは人によって異なること(価値判断)に言及している点に,僕は興味を惹かれました。
降水確率という情報によってもたらされる人の意思決定は,一律には規定できないことが分かると思います。つまり同じ情報を前にしても,人の感じ方,実際の振る舞いは,情報を受け取る人の関心や価値観によって,個別性を帯びているということです。そして,薬やサプリメントを飲むかどうかという判断もまた,医療や健康に関する情報に強く影響を受けているように思います。
医療情報を見る,医療情報から見る エビデンスと向き合うための10のスキル 序文より

ぼくたち医療者が寄せる関心としての良い医療と,患者さんが寄せる関心としての良い医療がイコールではない(価値判断は人によって異なる)という前提条件を知ったうえで,事実判断である医療情報をどう扱うか,どう伝えるかを改めて考えてみようよッ!そんな風に語りかけられたように感じました!!

医療者にとってもオススメできる内容でちゅか?

モチのロンやっ!!

も,モチのロン…。
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』 を読むことで得られることって??
- 事実と意見を読み分ける方法を知ることができる( 情報の正しさ(事実判断)がすべての人にとって等しく当てはまるわけじゃないという価値判断の多様性を知ることができる(天気予報の傘が代表的な例) )
- 治療効果の背後にある様々な要因を知ることで,本質的な効果について思考する方法を身につけるキッカケを得られる
- どんな文章で書かれているものが信頼性が高い医療情報かを知ることができる(情報の根拠を示している文章かどうかを見る視点を学べる)
- 論文の研究デザインと妥当性の高さを知ることができる
- 研究デザインの長所と短所を知ることができる
- 研究結果に影響を及ぼす要因があるということ,それらを加味して読み解くことが大事だと知ることができる
- 研究結果の統計解析について,いろんな視点から見ると印象が変わることを知ることができる
- 自分が抱いた疑問を定式化し,実際に論文検索するにはどうしたらいいかにも言及されている

盛りだくさんでちゅね☆

うんっ!!実際に青島先生の講演を聴いているかのようやったよ。ただ How to を伝える本じゃなくって,それをどう解釈するか?そこをどう考えるかを哲学する感じやわ。
哲学するっちゅうても,小難しいことは書いてへんで~
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』 は医療者でなくても読めますか?
医療従事者だけでなく,医療情報に関心がある方ならどなたでも読めると思います!!

先生,この本って医療従事者ではない方でも読めますか?

読めると思うで~っ!!(価値判断として,読めるとは言い切れないから表現は抑えめや)
医療従事者も新人からベテランまで誰もが読める内容になってると思うし,医療情報に関心がある方なら誰にとっても何かしら”ココ,おもしろいなぁ!! ”って感じる部分があるやろうね☆
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』 は医療者にもオススメできますか?
医療従事者にとっては,相手に事実判断として知り得た知識をどのように伝えるかを考えるキッカケとして大きな意味を持つ書籍になろうかと思います!!

エビデンスでぶん殴るような使い方じゃダメなのよ。そもそもエビデンスってフニャフニャ,フワフワしてるものなんかから…。

ん?どういうことでちゅか??

うん。論文を読む → エビデンスを知る。
結果として,エビデンスがあるんやぞぉ!って鬼の首を取ったように
「我が手にある者こそ唯一無二にして最強の医療情報であーる!!対してYouの持ってる意見にはエビデンスあらへんがな(持ってるエビデンスはクソ弱いがな),よってYouはワイの意見に従いたまへ」みたいな勢いで意見を言うのをエビデンスでぶん殴るなんて言う風に表現するんや。
そやけどな,その手にあるエビデンスは ” 誰にとって ” 有益に働くものなんやろか? 論文で研究対象になっている人たちは目の前にいる患者さんと寸分たがわないような特性を持つ人なんやろか?
そういうのんを考えるとね,バッキバキの最強な武器みたいなものじゃないって気が付くのよね,エビデンスって。

- どんな人を対象にして行われた研究か
- 研究自体に妥当性はあるのか
- 目の前にいる患者さんとエビデンスとなる臨床研究の対象患者さんの特性は合致するのか?
そうしたものを考慮していくと,バッチリ合うものはあんまりないってことでちゅよね…。

そうそう。近しいものはあっても,人種が違ったり研究デザインがそもそも内的妥当性が低かったりすれば,手にしているエビデンスは目の前の患者さんにピタリと当てはまるものとは言い難いやん。
だからといってエビデンスが無力とは言えへんで?科学的に治療に関して検証した結果なんやから,参考にするものとしては根拠がしっかりしたものやもの。
ただし,それを使うとしてもフワッとした・ふにゃっとしたものやんね?ってことを言いたいの。

エビデンス(事実判断)を,目の前の人にどれくらい合うのかを考える(価値判断)材料に使おうよってイメージでちゅか?

うん,そんな感じかなぁ。
事実判断をベースに置きながらも,医療従事者がどんな価値判断をして,患者さんがどんな価値判断をして,○○さんが価値判断をして…。その時その時,暫定的決定として総合価値判断をする,みたいなイメージ。
だから,変わりゆくものとしてふにゃっとフワッとしてる。そんなイメージかなぁ。
まさしく,「医療情報を見る」ことと「医療情報から見る」という,どちらからの目線も本書を読むことで見えてくるという点において,医療従事者の皆様にもオススメできるように個人的には思っています!
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』ってどんな人にオススメですか?
医療情報を見る目を養いたい方,医療情報から(医療を)見る方どちらにもオススメと考えます!
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』 はこんな経験がある方に是非とも読んでほしい1冊です!
- 週刊誌を見て自分の飲んでいる薬に不安を感じたことがある人・そうした人に対峙したことがある医療従事者
- ピグマリオン効果・ホーソン効果・プラセボ効果(ノセボ効果)といったことを考慮しながら治療効果について思考できるようになりたい方
- ネット情報を見ていて,どれを信用したらいいのかわからないと感じたことがある方
- 論文を読むことに興味がある方
- 研究結果の統計解析について,複数の角度から内容を見ることができるようになりたい方
- 論文の結果をどのように現場に活かしたらいいのかを知りたい方

ざっくりやけど,以上のようなことに一つでも当てはまる方ならば,読んでよかった!と思える可能性が高いと思われますッ!!
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』のAmazonレビューはどんな感じですか?
2020/02/04 現在,Amazonレビューはありません。
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』を読んでみた けいしゅけの感想(読む前の印象と読後の変化もレビューします)
ここから少しだけ,完全に個人的な読書感想文を記したいと思います。
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』を 読む前に感じていた事とは?
- 論文を読めるようになってきた気がするけれど,正直言ってまだまだどのように手にしたエビデンスを考察していいのかわからない
- ブログなどの文章を書くなかで,参考文献としてどういった論文を引用したらええんやろか?どのくらいの数やったらええのんか?ってか,自分が引用した文献は妥当だっただろうか?・・・という疑問や不安があった
- 改めて,医療情報の見方を学びたい
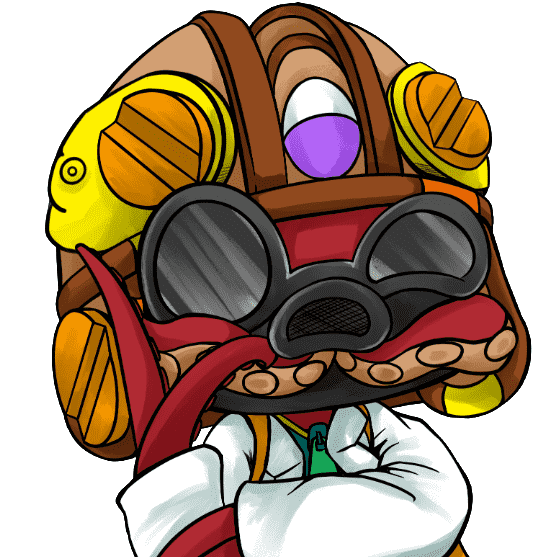
なんやかんや勉強していく中で,自分の無知を知ってしまったから,改めて学びたいって思いがあったんよ。
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』を 読んだ後に感じた事
- 議論の前提と主題を明確にすることの重要性を再認識できた。
→ ブログを書く上で,このあたりはより一層意識しなきゃなぁと背筋が伸びました - 自分自身がバイアスがかっているということを意識しようと感じた(完全に逃れることはかなり難しいけれど)
- 論文の対象グループがどんな人なのか?をこれまで以上に意識的に見ようと思った(そうじゃないと,目の前の患者さんに適応できない)
- 相対危険とともに,相対利益という視点で論文の結果を見ていこうと感じた(見方を変えると印象がホンマに変わることを改めて実感した)

書き出すとキリがないくらいでした~!!
マーカー引きまくり。赤線引きまくりでした。まだまだ勉強不足やわ💦💦
『医療情報を見る,医療情報からみるエビデンスと向き合うための10のスキル』を読んだ人にオススメの本はありますか?
本書p.126で登場した『相対利益』という言葉の出典であり,僕自身がEBMを学び始めた当初に夢中になって読んだ本がこの《薬剤師のための医学論文の読み方・使い方 》です。本書を通読し,EBMに興味を持った方にオススメ!!
《薬剤師のための医学論文の読み方・使い方 》と同様,EBMを学び始めたころに購入した書籍が《 薬剤師のための医学論文活用ガイド〜エビデンスを探して読んで行動するために必要なこと〜 》です。

どっちがオススメなんでちゅか?

好みは人それぞれやからね。書店で見比べてほしいかな。
ぼくは,書籍中に 1 か所でも勉強になる部分があれば『買い』だ,という価値観を持っているから両方買ったんやけども。
《 医療情報を見る,医療情報から見る エビデンスと向き合うための10のスキル 》で第10のスキルとして紹介されていた「エビデンスを効率よく検索するスキル」について,実践方法を対話形式で書かれている書籍です。
実際に医療情報を検索してみようとしたものの,やってみたら上手くいかへん…。どないしたら,どないしたらええんやっ!!
そんな風に感じた方に,オススメの書籍です。ちなみに,論文検索本というだけではなく,医療用医薬品のインタビューフォーム中で自分が欲しい情報を効率よく探すテクニックが紹介されていたり(PCだけでなくスマホでの操作についても書かれています!!),妊娠・授乳中に服用できる薬かどうか調べる方法も記されています。

白状します。初めて知った検索テクニックがいくつもありました。こうしたテクニックが広く伝わってほしいなって思います。すんごいオススメ!!
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!

この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!
ちょっとした質問も大歓迎

もしよければ,下のボタンを押してけいしゅけをフォローして欲しいでちゅ🍀
よろしくお願い致しましゅ~☆
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!
書いて欲しい記事の要望も募集中









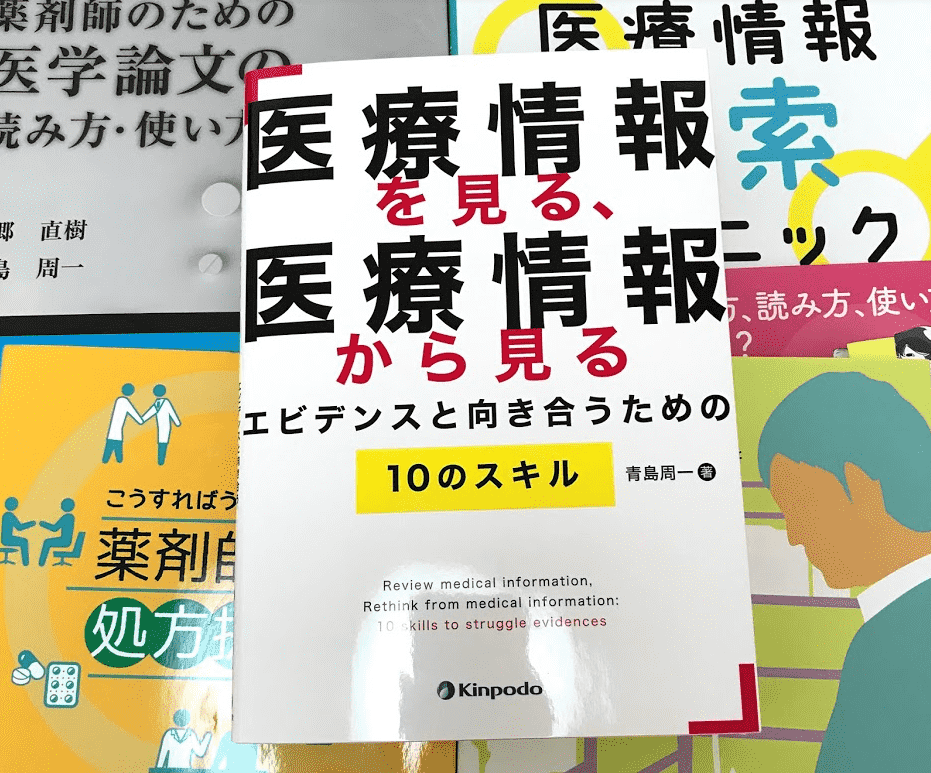
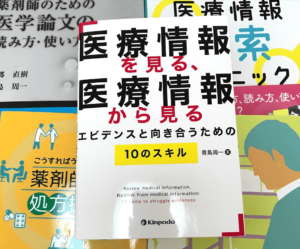
記事の感想など,ひとこと頂けますか?