【実践薬歴】は薬歴の書き方本ではなく薬歴を通した薬学管理の教本だ
当ページのリンクには広告が含まれています。
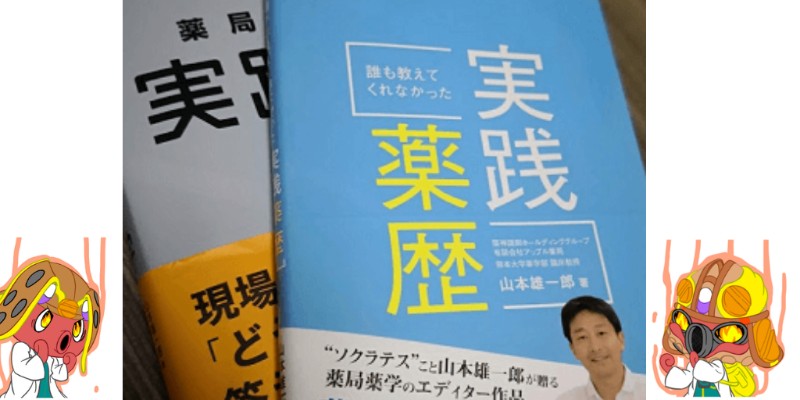
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
調剤薬局に勤める薬剤師として避けられない業務,それは『薬歴を通して薬学管理をすること』や。僕は社内で教育担当の仕事をすることがあるんやけど,新人薬剤師からベテラン薬剤師まで口をそろえて言うセリフが『薬歴の書き方がイマイチわからない』なんよね。
ちょっとカタい表現を使えば,「薬歴」というコトバの概念の規定と記述方法,そして利用目的。こうした思考を言語化したのが『実践薬歴』やと思うわ。
「薬歴の書き方」って一言で言い表せないという事でちゅか?
そもそも薬歴ってどんなもので・どう考えて・どう記録していくの?そして,何のために使うの?
こうした事が書かれているという理解でしゅか??
やるな,タコちゅけ。そやね。そういう感じやわ。
それと同時に,こうした薬歴を書くためには,プロとして膨大な予備知識が必要やとも記述されているわ。そりゃそうや,プロスポーツ選手を例にしたらスグわかる。
出場した試合について記録を残しましょう,ってなったとするわな。試合に出たときにどうやったら,きちんと自分の動きと相手の動きを把握できるんやろか?次の試合を有利に進める為に活かせる記録の残し方ってどんなのかなぁ?って議論になる訳や。けどな,「っていうか(前提として)プロレベルのスポーツスキルを持ってるん?」ってとこは見落としちゃダメやわなぁ。その前提なしに記録の残し方だけ知ってても,意味ないんよ。
薬剤師も一緒や。プロレベルの薬学知識を持っていて,薬をお渡しする患者さんと話しながら色々な情報を得たり提供したあとで,ようやく記録はつけることができるんやもの。そやから,この本はうわべだけの「薬歴(記録)のつけ方」の[How To 本]ではないよ。
ほんじゃ未熟者には無理ゲーじゃないでちゅかぁぁぁっ!!!
[/ふきだし]
アホたれぇ~っ!!
スグに無理ゲーやぁ!とか諦めるんじゃないっ!!
たしかに,プロレベルの知識を持つという前提に立つのは容易くないわ。けど,薬剤師国家試験通ってるんやろ?きっちり基礎知識は備わってるはずやで?そこまで自分を否定したり悲観的になったりせんでええやんか。仮に忘れてしまっているならば思い出す・改めて覚えるということに力を注いだらええねん。それが僕たちの,薬剤師の選んだ道なんやから。
たしかに,あの国家試験前の地獄のような勉強漬けの日々を乗り越えたから今がありましゅ・・・。
やるしかないんでちゅよね!! うんっ,そうでちゅ☆
うおぉぉぉぉっ!!!!!! やってやるぅぅぅぅっ🔥🔥🔥
[/ふきだし]
前置きがメッチャ長くなりました。
2017年3月6日に初めて山本雄一郎先生が世に放った書籍,それが『実践薬学』でした。そして,その次回作が期待される中,氏が世に放つ書籍第2弾のタイトルは,『実践薬歴』や。(正式名称は[誰も教えてくれなかった 実践薬歴])
この記事では,『実践薬歴』のレビューを書いていくでっ!!
冒頭にもあったように,表面上に見える程カンタンに実践できるか?と言えばそうでもなかったりする部分が多いのですが,裏を返せばそれこそがプロの仕事なのだと僕は思います。故に,この本が伝えたいメッセージのアツさってハンパじゃないなと感じたので,それをレビュー内容に盛り込みたいと考えてます!
まず,ネタバレなしの1分間で読めるサクッとレビューで実践薬歴を紹介していきます。
次に,本書の目次を紹介します。それから,ぼくの感じたことを記述していきます☆
最後に,まとめを書いて〆ますわ~。
目次
実践薬歴をネタバレなしで1分間レビューします!(未読者向け)
それでは,まだ中身を読んでいない方のために,本書籍の内容をネタバレしないように1分間レビューしたいとおもいますっ!!
実践薬歴の内容紹介
2018年9月1日に発売された本書,タイトルは『実践薬歴』。書籍販売ページに書かれている本書の3つのキャッチコピーを見てみましょう。
- 薬歴を見れば,その薬剤師の「仕事の質」がわかる!
- 薬歴を通して薬学管理の実践的な考え方を身につけよう!
- “ ソクラテス “こと山本雄一郎が贈る薬局薬学のエディター作品!
なるほど。確かにこの通りやと思います。
『実践薬歴』は,タイトルどおり薬歴の基本的な書き方・考え方を著した書籍やねん。しかし,ただのHow To 本ではないでっ!!
「薬歴というツールを使った薬学管理の実践的な考え方」を例示ベースで詳しく解説してくれてはるんや。薬剤師であれば日常的に出会う症例やDo処方であっても,患者情報や薬剤師の考え方によって服薬指導がどれほど変化するかを比較例も示しているねん。まさに実践的なんよ。
ちなみに,本書籍の中では多くの添付文書や文献,診療ガイドラインの内容が紹介されてるわ。これらを薬剤師として,どのように実践で活用しているのか書かれているのが有難いっ!!読んでいて参考になることマチガイなしやわ☆
そして,最終的にどのように薬歴へ知識が落とし込まれるのか,薬学管理につながっていくのか?そこまで見せていいの?と思うくらいに全部公開されています!
こんなもん,読まな損やんけ~!!!ってくらいに実践的な考え方と薬歴の書き方が記されてるで!!
このノウハウ,全部いただきやぁっ!!!!!
はい~っ!! 僕も思いっきりマネできる部分をマネしたいと思いましゅ~!!!!!
[/ふきだし]
若手からベテランまで,すべての薬剤師にお勧めの1冊です。
実践薬歴の評価
薬局に1冊置いておきたい書籍やね。僕は職場に置くことを決めたで~🎵
B5判で170ページちょっとなので,持ち運びやすい!どこでも読めるで☆学会で買う予定の方,余裕で持ち運びできまっせ💛
ちなみに,薬学的な知識に自信が持てない!そんなアナタには次のような書籍をオススメします☆
頑張るしかないでちゅーーーー!!!!!!
国家試験に通ったんでしゅもの,根性見せたりまちゅっ🔥🔥🔥
[/ふきだし]
実践薬学の目次が知りたい?はい,書きます!
Amazonを見てみると,目次が書いていません。じほう社の書籍紹介ページに行けば読めるのですが,せっかくこの記事にアクセス頂いたのですから,こちらで確認できるようにしておきましょう☆
第1章 薬歴とは
- 薬歴の歴史
- POSとは
- SOAPとは
- 薬歴をつける際のいくつかの注意点
[/list]
第2章 SOAP 形式の薬歴がうまく書けない理由
- 薬歴がうまく書けない理由は誤訳にある
- ごちゃごちゃした薬歴になってしまいます
- SOAP 形式の薬歴が書けない本当の理由
- いつも同じ処方なので薬歴に書くことがありません
[/list]
第3章 薬歴は薬学を通して患者を理解するためのツールである
- 医師と違う視点を常にもつ
- 併用注意は薬剤師の考えを伴って投薬される
- 患者の個人データを落とし込む
- すぐに答える,そこにアセスメントはあるのか
[/list]
第4章 高齢者の薬学的管理
- 高齢者の高血圧治療
- 高齢者の糖尿病治療
- 『高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015』
- 高齢者の漢方治療
[/list]
第5章 薬歴から学ぶ
- 薬歴を研修資材にする
- 症例ベースの問題に取り組む
- 学んだことを薬歴に還元する─ハイリスク薬SSRI/SNRIのリスク
- ディテールを保存する
[/list]
コラム
- 薬歴は「つける」もの? それとも「書く」もの?
- 薬歴は自由に書いていい?
- ストックフレーズはなぜいけないのか?
- SOAPで一番難しいのは?
- 薬局薬剤師が抱える構造的な問題とは?
実践薬学の序文が読みたい?はい,書きます!
ちょっと欲が出てきて,序文も読みたいなぁ~と思った方向けに引用文を載せておきます。
序文って著者の想いがガッツーン!と書かれているから,僕は読むのんが楽しみだったりするねん☆なのでネタバレしたくない人のためにコチラもクリックしたら読めるようにしておきますね🎵
こんにちは,“薬局薬学のエディター”こと山本雄一郎です。
この本は,薬剤師が毎日格闘しているであろう薬歴について,僕の論考をまとめたものです。薬局薬学において,薬歴は欠かせないツールです。薬局薬学のエディターを名乗っている以上,それに触れないわけにはいきません。しかしながら,僕が考案した理論などはただの一つもこの本には登場しません。僕はエディターなのです。尊敬する先生方が生み出した理論を,僕の意図を伴ってそこに配置する。その配置の仕方をもって,僕の作品としています。
さて,薬歴は調剤報酬が関与するデリケートな問題でもあります。僕が薬歴をテーマに講演する際,必ずといってもいいほど事前にそういった内容について触れるかどうかの確認が入ることからも,それは伺えます。ゆえに,講演で調剤報酬の問題に触れることは一切ありませんし,この本もそういったことを目的にはしていません。
では,何を目指しているのか? それは,薬理学や薬物動態学といった僕らの武器である薬学を存分に振るうためです。そして,薬物療法を個別最適化すると同時に,薬というリスクのある物質から患者を守るためでもあります。そもそも薬歴という医療記録が何のためにあるのかというと,まずは患者の安全のために存在しているのです。
薬歴とは,薬剤師が行った医療を記録したものです。換言すれば,薬歴を記載するところまでが医療行為であって,その重要性は調剤や服薬指導と何ら変わりはありません。薬歴なしで投薬するなんて怖くて僕には到底できませんし,患者の立場になって考えても,そんな薬局は信用できません。だから,薬歴は大事なのです。決して,点数の算定がためではありません。薬歴は患者の安全のための大事なツールである,そんなことは皆,肌で感じている。しかしそうはいっても,僕らは大学で医療記録について学んでこなかったし,隣の薬局の薬歴を目にすることもありません。ましてや,一人薬剤師ともなれば…。
そこで,よくある症例の薬歴を通して,どのように薬歴を記載すればいいのか。そして,薬歴をどのように目の前の患者のために活用すればよいのかを一緒に考えていきたいと思います。この本を通して薬歴への悩みが少しでも減ってくれれば,そして薬物療法の専門家としての自信へとつながっていく,その一助になればと期待しています。(後略)
2018年6月 山本 雄一郎
じほう社 HPより転載 http://www.jiho.co.jp/shop/list/detail/tabid/272/pdid/51155/Default.aspx
実践薬歴をレビューします!!
では,本格的にレビューしていこか☆
『実践薬歴』を手にしたいと思ったアナタは,いったい何を期待していますか?
僕の場合は,薬歴のつけ方をアップグレードしたいという欲求があり,その回答が得られることを期待して買いました。この記事をお読みのアナタも同じ期待を寄せていたりしませんか?
ハッキリ言いましょう。その期待,満たされます!!
もし購入を迷っているのであれば,僕は自身をもって背中を押したい。「ポチったらええねん☆メッチャええでこの本🎵」と
僕が『実践薬歴』を手にした理由
薬局薬剤師として知識や経験を総動員し,患者さんの情報を言葉を通じてやり取りをする場は,大きく分けて3つあるかと思う。
- 外来患者さんに薬を渡す投薬窓口
- 患者さん(その家族)からかかってくる電話
- 在宅業務(個人宅や施設)
[/list]
この全ての対応の記録は,薬歴をつけることによって残されていく。
しかし,これほどまでに日常的に記しているにもかかわらず,自分がつけている薬歴に対して正直言って自信が持てない。もっとぶっちゃけた表現をすれば,僕は自分の薬歴に対してコンプレックスがあるねん。
なんやろなぁ,自分の考えや知識・経験を盛り込んでいるはずなのに,なんかこう,しっくりこない。SOAP形式で記入しているのに,なぜこんなにもしっくりこないのか。なぜに…?
[/ふきだし]
先生,ボク書いている薬歴を指さして「ここに患者さんの薬学的管理の歴史が刻まれていましゅ!」と言い切れないんでちゅ…。
それどころか,この薬歴の書き方で他の薬剤師に患者さん情報って伝わるのかな?いや,これじゃダメでちゅよね!?みたいな。
[/ふきだし]
 けいしゅけ
けいしゅけ
お,まさに僕が思っている事じゃないか,それは!!
[/ふきだし]
それだけじゃないんでちゅ。この薬歴じゃ患者さんの副作用モニタリングができないんちゃうか??って。
そもそも,副作用モニタリングを言語化して継続的に記録していく意識が薄いんちゃうか??とも感じてましゅ。
[/ふきだし]
 けいしゅけ
けいしゅけ
ドキーッ!!僕もや…。
[/ふきだし]
ウホンウホン,タコちゅけよ。ハッキリ言うわ。僕も全く同じ悩みを持っている。
だから,一緒に学ぼうか。
こうした背景があって,僕は本書を手にしてん。
結論から言うわ,買ってよかった。
ほんじゃ,ちょっくら印象深い内容を振り返りながら買ってよかったと思った理由を書いていくわな☆
【実践薬歴】第1章 薬歴とは で薬歴に関する考え方を学ぶ
まず,はじめの1章。ここで書かれているのはザックリ以下のようなことやで
- そもそも,薬歴って何ですか?
- 薬歴のスキルアップで求められ2つの軸
- POSとは
- SOAPとは
- 薬歴をつける際のいくつかの注意点
- コラム:薬歴は「つける」もの?それとも「書く」もの?
基本的であり,とっても大事な考え方が書かれています。
POSやSOAPってそう言う事だったんでちゅね!!と頷くことが多かったでしゅ☆
[/ふきだし]
薬歴をつける際のいくつかの注意点と,コラム:薬歴は「つける」もの?それとも「書く」もの?が僕は印象的やったなぁ。
#プロブレム を書くのってブログ記事を書くところの主題を書くようなものやもの。それが僕は出来てなかったよ。反省やわぁ~。
【実践薬歴】第2章 SOAP 形式の薬歴がうまく書けない理由 で薬歴の書き方を知る!
薬歴の書き方のノウハウはこの章にまとまっていると思います。
- 薬歴がうまく書けない理由は誤訳にある
- ごちゃごちゃした薬歴になってしまいます
- SOAP形式の薬歴が書けない本当の理由
- いつも同じ処方なので薬歴に書くことがありません
もはや,この章の小見出しを列記するだけで伝わると思います。
この章を100回読みましゅ!
[/ふきだし]
【実践薬歴】第3章 薬歴は薬学を通して患者を理解するためのツールである から薬剤師の担う役割を再認識
第3章の扉ページにはこんな風に書かれています。
薬剤師によるSOAPのA,アセスメントには,当然ながら薬学的なアセスメントがされていなければなりません(意思は医学的な,看護師は看護学的な・・・)。
つまり,僕らは薬学を通して患者を理解する必要があるというわけです。その視点の多くは医師とは異なります。いや,異なるべきであって,そうであるからこそ薬剤師不要論が払拭できるのです。
実践薬歴 p.67より(強調はけいしゅけによる)
この他にも,第3章からは刺激をビッシビシ受けました。
- 副作用モニタリングピリオドを意識
- 併用禁忌はダメだけど併用注意は大丈夫?~禁忌と注意は,簡単には割り切れない~
- 患者の個人データを薬歴に落とし込む~個人データの蓄積が現場の強さ~
- すぐに答える,そこにアセスメントはあるのか
この章は正しく「The 薬剤師」の世界がビシバシ広がってきます。僕自身,勉強不足は自覚していましたが,改めてもっと勉強したいっ!!と痛感したのでした。書籍に目を通すことはもちろん,PISCSの視点をもっと持たなきゃなぁと。
実践薬歴レビューまとめ
ざっくりとしたレビューとなりましたが,いかがでしたでしょうか?魅力が少しでも伝われば幸いです。
僕は薬剤師として未熟もので,薬歴の記入に関してもまだまだ満足していません。その中でこうした書籍に触れ,薬歴と言うツールを最大限利用して薬剤師として職能を存分に発揮できるようになりたい!と強く願っています。
知識や経験の蓄積には時間がかかります。そやけど,やり続けることしかないと僕は考えます。学び続けよう,そうしよう☆って。
そして,本書にも記述がありましたが,薬学の知識を継続的に蓄え続けると共にブログ記事などを通して後世の薬剤師に伝承していくことの重要さも強く感じたのでした。
少し脱線しました。僕たち薬剤師は継続的に知識や経験を蓄えている間も,常に薬歴をつけ続けなければいけません。その薬歴のつけ方・考え方を実践的に詳細に言語化した書籍,『誰も教えてくれなかった 実践薬歴』は”薬局薬学のエディター”山本雄一郎先生から贈られた学習激励本なのではないでしょうか?
もっと薬剤師にはできることがあるよ!薬歴というツールを使って,患者さんを副作用から守ろうよ!薬剤師にはそれができるさ!!と。
本書の「おわりに」はこう記されています。
薬物療法の専門家として,その患者の薬歴を携え,処方医のもとへ,他職種連携の場へ,自身をもって向かう薬剤師たち。
そんな未来に宛て,僕はこの本を差し出すことにする。
実践薬歴 p.170より
やりまちゅーーーー!!!!!
[/ふきだし]
アナタもこのアツいメッセージがこめられた本書を手に取ってみてはいかがでしょうか?
[kjk_temp id=”5491″]
他にも過去に,書籍のレビュー記事を書いています。よかったらお読みください。
[[kjk_temp id=”6015″]]

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
 けいしゅけ
けいしゅけ

















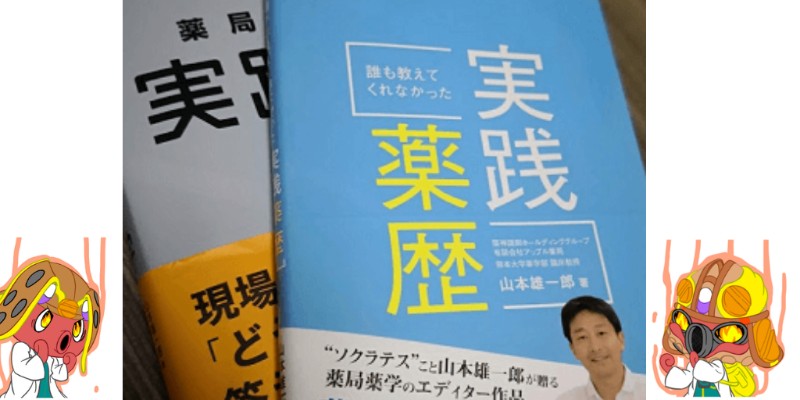

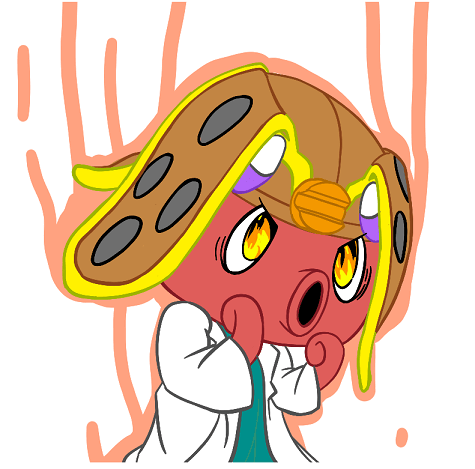











記事の感想など,ひとこと頂けますか?