【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】はEBMを学ぶ薬剤師必携の書や!
7月16日の事である。僕の手元に届いた【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】
著者は 名郷直樹 先生と 青島周一 先生。
6月に入会したAHEADMAPの共同代表者である青島周一先生が「現在のところ主著となる本です。」とおっしゃる本や。
僕はTwitterアカウント @keisyukeblog (👈良かったらフォローしてなっ☆喜びます!)で名乗っている通り,まだまだEBMを学び始めた言わばEBMレベル1薬剤師やねん。
そんな僕と同じ境遇の人も多いんちやうかな?それやったら読んでみた感想やどんなふうに活かせるで!ってことをレビューすることが最も参考になると考えてん。結果的に「EBM,勉強してみよっかなぁ~」そう思える人が増えたら嬉しいから書いていこうと思うわ。全力で!
ブログやから,完全に砕けた表現で書いていくし,ちょいちょいおふざけが入ることを容赦いただきたい。
ほんじゃ,いっくでぇぇぇーーーーーー!!!!!! オシッコしてから書き始めます!
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】はEBM勉強の必携書籍や!1冊の構成が完璧や
さて,スッキリしたところで書き始めていこう。まずはタイトル通りやねんけど,本書は構成が完璧や。
どう完璧か早よ言いなさいや!
まぁ落ち着きなさい。すぐに書くから。ほんじゃチャッチャとザックリした構成を書き出すで!
- 論文を読む為に知ってなアカンい基礎知識として,統計用語についての解説(ムッチャわかりやすい!)
- 薬の効果について,哲学する。構造主義科学論的検討についての解説(哲学的で難解やけど非常に大事!)
- 論文を具体的にどのように読むのか?研究デザインごとに読むべきチェックポイント付きで解説(論文を読むにあたり,名郷先生と青島先生が横にいてくれるようで非常に心強い!)
[/list]
このような構成になってるねん。
論文を読む為に知ってなアカン基礎知識として,統計用語についての解説がムッチャわかりやすい!
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】の Ⅱ章 知っておきたいキーワード は,統計用語について解説している章やねんけど,この章を読むだけでも【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】を買う価値があるんとちゃうかな?って感じる。
統計用語を学ぶにあたってコンパクト かつ わかりやすく解説されていて,EBMを学ぶ基礎知識がガッチリ理解できるわ。
Ⅱ章 知っておきたいキーワード の目次 は以下の通り☆
- 薬剤効果の観念的側面と事実的側面
- 代用のアウトカムと真のアウトカム
- 背景疑問と前景疑問
- EBM の 5 つのステップ
- 内的妥当性と外的妥当性
- ランダム化比較試験
- コホート研究
- 症例対象研究
- メタ分析
- 横断研究
- その他の研究デザイン
- 情報収集戦略
- 6S アプローチ
- PubMed 検索のコツ
- ハザード比, オッズ比
- 平均差, 標準化平均差, 治療必要数
- 統計的仮説検定, P 値, 有意水準
- 統計的検定, 95%信頼区間
- プラセボ効果, ホーソン効果, ノセボ効果, 二重盲検法, PROBE法
- クロスオーバー, ITT解析, 非劣勢試験, マージン
- αエラー, βエラー, 一次アウトカム, 二次アウトカム, 複合アウトカム
- サブグループ解析, ボンフェローニ法
- 交絡因子, 傾向スコアマッチング
- 情報が示すものと臨床研究が示す関連
[/list]
これだけの情報がまとめられているねんで☆ 目次にある項目のどれもが論文を読むうえで非常に大事なキーワードやから,僕自身なんども繰り返し読んでるわ。
 けいしゅけ
けいしゅけ【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】を読むまでに,薬剤師の国家試験対策本などで勉強していたんやけど,書かれた知識を咀嚼して飲み込み,自分のものにするには時間がかかっていた。
ところが,【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】では難解に感じる統計用語が消化・吸収しやすいレベルまで噛み砕かれて解説されているわ。
Ⅱ章 知っておきたいキーワードの目次を見りゃご理解いただけると思うねんけど,通読することで統計用語の理解はバッチリや!すんごい情報量やろ?これ1個ずつがメッチャわかりやすく書かれてるねんで?スゴ過ぎるっちゅうねん!
薬の効果について,哲学する。構造主義科学論的検討についての解説は,哲学的で難解やけど非常に大事!
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】の Ⅲ章 「効果のある薬」の実体:統計学的検討と構造主義科学論的検討 についてレビューを書いていく。
薬の効果があるかないかを考える際に,2つの考え方をまず紹介しよう。1つは存在論的に考えるという視点,もう1つが認識論的に考えるという視点である。
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】p.80より引用
- 存在論的に考える:薬の効果について「効く・効かない」の間に明確な境界がある。という仮定が想定されていて,その境界の間には客観的な断層があるという考え方
- 認識論的に考える:薬の効果について「効く・効かない」の区別は,薬の側ではなくそれを判断する側の認識の問題であるという考え方。



正直に言おう,本気でこの章は難しい。
薬の効果と言うのはハッキリと客観的に「効く・効かない」の境界線を引くことなんかできへんのに,一応,近似的にどのくらい効果があるのか?それを論文などでは表現する。その表現方法はどうしても存在論的にならざるを得ない。
しかし現実はどうや?薬の効果って客観的に数値として目に見えるの?見えへんよね? つまり,薬の効果は存在論的に考えることはできず,認識論的に考える方が現実に沿ったものになる。ではどうやって表現するのか?
「実体」を明らかに表現することはできないが,観察された「現象」,その現象を記述した「コトバ」,さらにその「現象」をとらえ「コトバ」として記述した主体である「私」について記述する。これが構造主義科学論的検討の基盤である。
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】p.86より引用
構造主義科学論的検討については何度も読んで,雰囲気はつかんだつもりになるんやけど,読めば読むほどにややこしくなっていくねん。
薬の効果と言う「実体」は,効果を言い表したい「私」が観察された「現象」を「コトバ」として記述するもので,
「実体」という客観的な現実に対して,
「実体」と「現象」のあいだと,「現象」と「コトバ」のあいだに,「私」が作る主観的なギャップが生じてしまう。そやから,どんなに客観的に書かれているように感じる論文であれ,主観を逃れてはいないから,「実体」を絶対的に表現したものではないゆえに妄信はできへんよね?
そんな風に理解したつもりなんやけど,どうかな。うーん,完全に言い表せないや。
非常に難解なものやけど,非常に深い。エビデンスを絶対視して,それを根拠に医師の処方をぶった斬るような真似をするのは違うで!って思えるわ。だって,そのエビデンス自体,薬の効果という「実体」を100%「コトバ」にできている絶対的なものじゃないんやもん。
エビデンスはそれを医師や薬剤師の「私」がどう「現象」を「コトバ」として出し合い,臨床に応用するかを検討する材料にするものでしかない気がしたわ。
※この項に関する僕の考えを書いていますが,哲学的な部分ですので,この記事を読む「アナタ」はどう感じるでしょうか?良かったら感じたことを「コトバ」としてコメントとしていただけるとありがたいです!
ちなみに,ちょっと読んでみたいと思った方のために,「構造主義科学論の冒険」のリンクを貼ります。僕も読んでいこうとしています。
論文を具体的にどのように読むのか?研究デザインごとに読むべきチェックポイント付きで解説されている!
この本が非常に素晴らしいのは,Ⅳ章 クリニカルクエスチョン で実際の論文を題材に名郷先生と青島先生がどのように読み進めたらいいのか?を実況中継のように文章化してくださっていることや。
名郷先生と青島先生が横にいてくれるようで非常に心強い!
あなたは論文を読むにあたって二人の知の巨人が横にいて指南してくれるとしたらどうや?僕はこのⅣ章を読んだときに鳥肌が止まらんかったよ。
ちなみに,Ⅳ章では,
- RCTについて4例
- メタ解析について2例
- 観察研究について2例
- 症例対象研究について1例
それぞれ論文を Ⅱ章 で学んだキーワードをどこでどのように使って,構造主義科学論的検討をしながら,結果を考察する記述が読むことができる。



ハッキリ言おう。
この本を持たないのは薬剤師として勿体ない!!!
ここまで丁寧に,120%の読者満足度を提供するEBM関連の本はそう多くないやろうさ。ホンマ,これはあり得へんくらいに勉強できる本やと思う。僕はこの本をTwitterでもつぶやいたけれど,手放すことができへん。
仕事の行き帰りの電車の中で読み,論文を読むときは当たり前のように机に置き,ブログ記事を書くときも書きながら考察をするのでPCの横には必ずおかれている。
本の内容にはマーカーが引かれまくり,メモが多く書かれるようになっている。まだまだこれからもメモ書きが増えていくのは間違いないわ。
EBMを学ぶ上で,【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】は必携や。これは,買おうよ!
そんなわけで結論としては,【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】は薬剤師なら必携の書物であると言い切るわ。
買っておきましょう。さぁ,ポチってしまいなさい☆
これに尽きる。学ぶ気持ちがある人にとって損をすることはあり得ないと断言できる。もちろん僕の主観でしかないけれど,断言できるわ。
別に僕がAHEADMAPの会員やから宣伝をしているわけでも何でもない。僕は薬剤師としてEBMを学ぶためにAHEADMAPに参画している。そこで得た知識や知恵を,このブログの主旨でもある「誰かの役に立つ情報をわかりやすい表現で発信する」ことに活かしたいねん。
【薬剤師のための医学論文の読み方・使い方】持ってるで!って人,Twitterで@keisyukeblogに絡んできておくれ!
さぁ,自分を追い込んでいきます。
この本を持っている人,一緒にEBM勉強しようぜ! @keisyukeblog と一緒にEBM勉強しよっかなーって人,フォロー待ってるで!
@keisyukeblog に教えてやるぜ,EBMというものをな!っていうハイレベル薬剤師の先生は特に大歓迎です!勉強させてもらいます!
論文への考察について意見を交えましょう!
[kjk_temp id=”5491″]









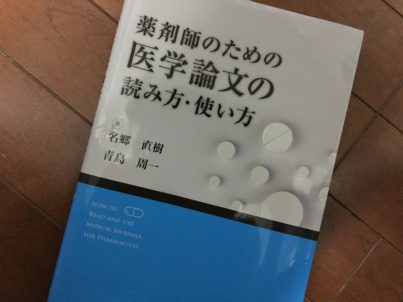


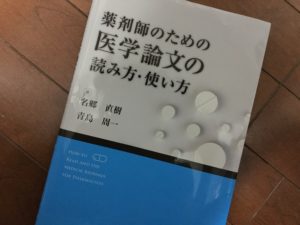
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (2件)
こんにちわ。ときどきTwitterでも絡ませてもらっているちはるです。40代管理職です。若かりし頃は薬局薬剤師もこれからは学術的に物を考えるようになるべきだと思っていたし、実際医師にも会いに行き質問したり意見を伺ったりしましたし、処方変更提言も些細なことでもしてきました。でも、今は管理職的な事務業務や人事的なことに忙殺され薬の勉強をする時間がなくなりました。そんなときけいしゅけさんのブログを見つけ、薬剤師のアカデミックさの必要性を改めて思い出し、私たちの仕事の根幹であるところを再認識しました。すっかり忘れるではなく、刺激を受けるレベルですけど『いつも見てます』‼︎
オススメの本、ポチります。
自分が読む時間なければ、後輩たち若手に紹介して刺激を与えます。
これからもよろしくね。
ちはる 様
コメントありがとうございます!
もうなんやろ、この上なく嬉しいコメントを頂戴し、光栄です。僕も管理業務などに忙殺されておる薬剤師の一人なのですが、そうした現実問題に対峙しながらも、なお、青臭く薬剤師として勉強をし続けて誰かの役にたちたい!という(自己満足と言えばそれまでなのですが)理想を追いたくてブログを書き続けています。こうしたコメントを頂ける事で、まだまだ書き続けたるっ!という力が漲ってきました。ありがとうございます!時に誤った表現があることもあると思います。そんなときはどうぞ指摘してやって下さい☆
同じ薬剤師として、青臭く理想を追っていきましょう!