JJCLIP #59 認知症患者さんは積極的な運動療法を受けた方が良い?
2018
12/29
当ページのリンクには広告が含まれています。
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog )です☆
久しぶりにJJCLIPツイキャス配信のログ記事を作成します。(配信後は下にYouTube投稿版を貼ります)
薬剤師のジャーナルクラブ,JJCLIPのツイキャス論文抄読会の内容をまとめると共に,自分なりにも考えたことを記録していく記事です🎵もし,聞き逃したぁ!という方にとってアーカイブ情報となれば幸いです☆
YouTubeのチャンネル登録,是非ともお願い致します!!!
目次
仮想症例および論文タイトルと使用するワークシート
それでは,今回のJJCLIP配信の内容を引用します。
仮想症例シナリオ,抄読会に使う論文,論文を読み解くためのワークシートのリンクが得られます。
[症例51:認知症患者さんは積極的な運動療法を受けた方がよいのでしょうか?] 【仮想症例シナリオ】
「ちょっと聞きたいことがあって来たんです.実は担当している患者さんの家族から,
[患者情報]
これはここで何かしらの方向性を示した方がいいと思ったあなた.
【論文タイトルと出典】 29769247 こちら よりダウンロード可能です.
【使用するワークシート】 http://j.mp/jjclipsheet1 @syuichiao89 先生作成)
よろず屋「雅(Miyabi)」のみたて より引用
STEP.1
仮想症例の問題の定式化
仮想症例のPECOを立てる
STEP.2
問題についての情報収集
エビデンスの収集
STEP.3
論文情報の批判的吟味
ワークシートに従って論文を10分で読み解く
STEP.4
論文の結果を仮想症例の患者さんにどう当てはめる?
結果の
STEP.5
まとめ
感想・自分なりの考えをまとめる
この流れで書いていきますわ☆
頑張りまちゅ!!
[/ふきだし]
仮想症例のPECOを立てる
それでは,仮想症例のPECOを立てていくで。
P: 軽度認知症と診断された75歳男性.抗認知症薬の治療はすでに導入・継続済み。ケアを受け始めて半年ほど経過,ご家族の目からは徐々に増悪しているように見える。ただし,医療・介護者からの視点では特変なしと判断されている E: 運動(+) → ケアプランにリハビリを入れる C: 運動(-) → 現状のまま O: 認知症の進行は抑制されるか? BPSDは改善するか? などなど
今回のPECO(PICO)は,こんな感じでどうやろか?他にもいろいろなPECOが立つと思うで☆
[/ふきだし]
BPSD(行動・心理症状)ってなんや?
認知症の症状には「中核症状」と呼ばれるものと,「BPSD(行動・心理症状)」と呼ばれるものがある。
BPSDは「認知症の行動と心理症状」を表わす英語の「Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia」の頭文字を取ったものやで。
どういったものがBPSDか?
→暴言・暴力,興奮,抑うつ,不眠,昼夜逆転,幻覚,妄想,せん妄,徘徊,もの取られ妄想,弄便,失禁などがBPSDや。
BPSDの表現型は人それぞれで,その人の周囲環境や,人間関係,性格などが絡み合うんや。介護者が対応に苦慮する多くは,中核症状よりもBPSDだったりする。
エビデンスの収集
EBMのStep2にあたるセクション。JJCLIP配信の場合はお題論文と共に論文もひとまず出ているので,割愛。
Dementia And Physical Activity (DAPA) trial of moderate to high intensity exercise training for people with dementia: randomised controlled trial.
Lamb SE, Sheehan B, Atherton N, et al.
BMJ. 2018;361:k1675.
PMID:29769247 PDFはこちら よりダウンロード可能です.
論文情報の批判的吟味
ワークシートに沿って書いていくで☆
論文のPECO
P: 認知症患者494名 (軽度~中等度) E: 運動プログラム(有酸素&強化運動)ジムで4ヶ月間,週2回60-90分の運動(5分間のウォーミングアップ+中程度からキツイエアロバイク,筋トレとしてダンベルを使った腕のトレーニングを色々と)+週当たり1時間の自宅運動。4ヶ月間のプログラム終了後は自宅で150分/週の運動 C: 通常ケア O: 12ヶ月後のADAS-cogのスコアはどうか?(スコアが高いほど悪化していると判定,0-70点で採点)
論文情報の批判的吟味チェックポイント6項目
ランダム化されているか?➡ されている(I群:C群=2:1の割り付け,I群329例,C群165例) 1次アウトカムは明確か?(1つに限定されているか?)➡ 明確と判断: The primary outcome was score on the Alzheimer’s disease assessment scale-cognitive subscale (ADAS-cog) at 12 months. 真のアウトカムか?➡ YES(代用のアウトカムっぽいけど,真のアウトカムではないと言い切れない) 盲検化されているか?➡ 治験責任医師のみマスキング=PROBE法: investigator masked 解析方法は?➡ ITT解析:We conducted analyses using intention to treat principles and analysed all people according to their random allocation. 追跡期間・状況は?➡ 6か月間の追跡・追跡率90%(445人/494人),最終的にはI群85%,C群83%
[/list]
ADAS-cog(Alzheimer’s Disease Assessment Scale-cognitive subscale)って何ですか?
認知機能を評価するための方法であり,単語再生,口頭言語能力,言語の聴覚的理解,自発話における喚語困難,口頭命令に従う,手指及び物品呼称,構成行為,観念運動,見当識,単語再認,テスト教示の再生能力の項目より評価する。得点の範囲は0~70点(正常→重度)である。
【PROBE法(Prospective, Randomized, Open, Blinded-Endpoint method)】って何ですか?
前向き,無作為,オープン,エンドポイントブラインドで行われる臨床試験のこと。
エンドポイントブラインドとは,各症例がどの群に割付けられたかを知らない第三者がエンドポイントの評価を行うことにより盲検化すること。
論文の結果
介入群の方がADAS-cog scoreが有意差を持って 1.4点 悪化した。(臨床的な 有意差があるのは,2.45ポイントの差がついたとき)
→つまり,臨床的には差がない。という結果と言える。
By 12 months the mean ADAS-cog score had increased to 25.2 (SD 12.3) in the exercise arm and 23.8 (SD 10.4) in the usual care arm (adjusted between group difference −1.4, 95% confidence interval −2.6 to −0.2, P=0.03).
論文の結果を仮想症例の患者さんにどう当てはめる?
「運動させたい」が家族さんの想い。介護者さんはその相談を聞いて悩んでいる。
ただし,この論文のようにガッツリ運動したからと言って,認知機能に対してポジティブな結果は出ない事を踏まえると,「無理に運動させる」意味はあんまりなさそう。けがをしてしまうリスクもある。
かと言って,どう伝えるのか?を考えると悩ましい。
無理に運動させる必要はないけれど,運動したい人を止める必要もなさそう。なので,「人によって,どちらでも好きな方を選べば良いのかもね」と言えたら良いのかもしれない。
感想と自分なりの考えをまとめる
JJCLIP視聴前
介入群で悪化するという結果。
過去の骨折歴も両群で変わりないし,う~ん。わかんない。
運動介入がハード過ぎてストレス溜まったんちゃう?とか思ってしまった。
ジムで色々やって,家に帰ってからも運動せぇ。その毎日が終わったと思ったら,その後も週に150分は運動せぇと言われる。
これ,ストレス溜まるんちゃうん?という感じてしまう。ストレスと認知症のリスクに関する論文読もうかなぁと思いました。
JJCLIP視聴後
「運動って認知症に良さそうやんね?」が「げ。あんまり意味ないっぽいねんや?」と知ることによって『人によりけり』感が高まった。
エビデンスを知ることによって,患者さんやその家族さんの想いを汲み取ることで,それぞれの患者さんにとってのベターな答えが浮かび上がってくる気がしました。
[kjk_temp id=”5491″]
[[kjk_temp id=”6015″]]
 けいしゅけ
けいしゅけ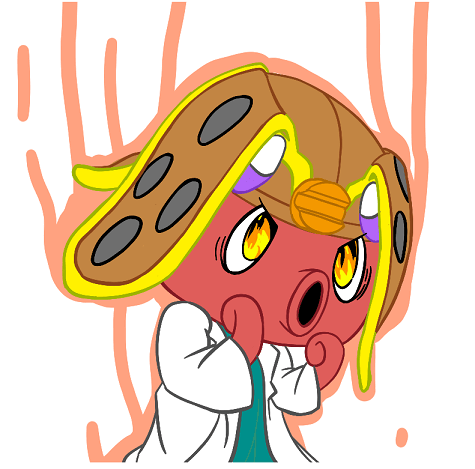
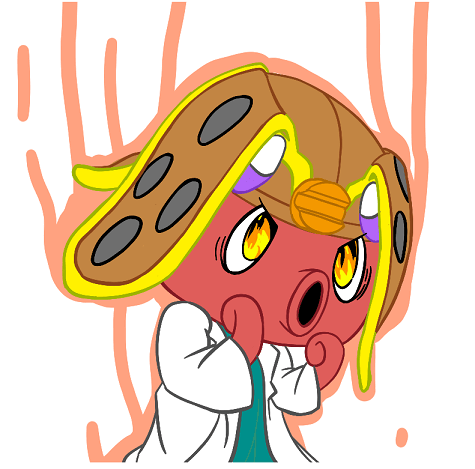
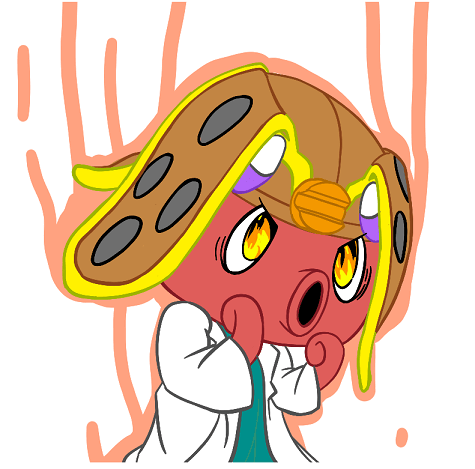












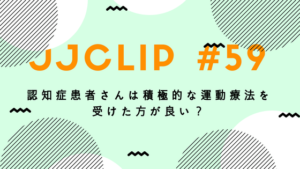
記事の感想など,ひとこと頂けますか?