【JJCLIP_#53】 褥瘡患者の栄養はどういったものを投与するのが良い??
2018年2月25日(日)のJJCLIP配信の内容をまとめました。
今回のツイキャスでは,メタ分析についての論文を題材としています。
僕なりに今回のツイキャスからも学ぶことが非常に多かったのでここに記録しようと思います。
 けいしゅけ
けいしゅけYouTubeのチャンネル登録,是非ともお願い致します!!!
仮想シナリオ
あなたは,とある街の薬局の薬剤師さんです.
今日は一日外来調剤…と思っていた矢先に,提携している在宅医より相談の電話がかかってきました.
「施設入居患者の〇〇さん,仙骨部の褥瘡,やっと改善してきたかなって思ったら,最近食事がさらに摂れてないって介護士さんから言われてね.それで,エンシュア・H®︎に切り替えてもいいのかなって考えてるんだ.
ただ,正直自分は栄養のことはあまり詳しくなくて,もし代替案があれば,それが処方できるかどうかも含めて教えて欲しいんですよね.先生,どう思います?」
【患者背景】
- 70歳女性.仙骨部の褥瘡が入所時より持続.そのほかの既往歴はなし
- これまでに医師・看護師・介護士と協働で,適切な外用薬や創傷被覆材は使用している
- 軽度摂食障害がありエンシュア・リキッド®︎のみが不定期で処方されていた
今日中に折り返し連絡しますと伝えたのち,いつも通り,文献を探してみると,褥瘡と栄養に関する論文を見つけることができたので,その場で早速読んでみることにしました.
【論文タイトルと出典】
Efficacy of a Disease-Specific Nutritional Support for Pressure Ulcer Healing: A Systematic Review and Meta-Analysis.
Cereda E, Neyens JCL, Caccialanza R, Rondanelli M, Schols JMGA.
J Nutr Health Aging. 2017;21(6):655-661.
PMID: 28537329【使用するワークシート】
メタ分析を10分で吟味するポイント
http://j.mp/jjclipsheet2(@syuichiao先生のブログより)
引用元:クスリのよろず屋「雅 (Miyabi)」の見立て
褥瘡は栄養状態を良くすることが改善のポイントになる。
シナリオのPECOはどうなりますか?
- P: 70歳女性。仙骨部の褥瘡が入所時より持続。その他の既往歴なし。
適切な外用薬や創傷被覆材が使用され,軽度摂食障害(摂食量の減少)。
エンシュア・リキッド®︎の不定期処方。褥瘡が回復傾向にあったが,摂食障害悪化(介護士の報告より) - E: 栄養剤の変更(例えばエンシュア・H®︎)・・・より栄養価の高いものに切り替える
- C: エンシュア継続
- O: 褥瘡の悪化は防げるか?褥瘡の回復が早まるか?
JJCLIP#50と同じ内容を記載します。
1つのケースに対してPECOはいくつも立てることができる。
いま目の前にいる患者さんに興味を持ち,頭を柔軟にして,色々な介入方法を考える・いろいろなPECOを立てる訓練をすることが薬剤師には大切かもしれない。
論文のチェックシートを使い,10分で読む!
いつもどおり,チェックシートを用いて10分間で論文を読んでいく作業に入ります。



AHEADMAPのWebページ➡資料ダウンロードページからダウンロードしておいたワークシートを利用します。普段から使えますのでダウンロードしておくといいかも!!
ポイント:厳密に見過ぎない。ほぼアブストラクトからPECOはさがせるので,Key Wordを探して立ててみよう。数値を追うのも良い。
論文中の英単語についてのメモ
PUって何ですか?
➡ Pressure Ulcer=褥瘡
Malnutrition って何ですか?
➡ malnutrition =栄養失調
ONSって何ですか?
➡ ONS=Oral Nutrition Supplementation=経口的栄養補助
論文のPECOは?
Pはどこをみる?
Table.1に記載あり。N数を足せばOK.
EとCはどこを見る?
Abstractの最初に記載あり。
Oはどこを探す?
P.3のOutcomesに記載あり。
- P: 273名の患者,高齢者(70歳以上)で褥瘡は中等度から重度である患者が集められている。
- E: 高カロリー負荷(高カロリー,高タンパク,)
- C: 疾患特異的ではなく,標準的な経口栄養(に加えてプラセボか何もしない)
- O: 8週間時点での褥瘡面積の回復率(1次アウトカム)
4週間時点での褥瘡面積の回復率や8週間での褥瘡面積の40%以上ないし完全治癒(副次アウトカム)
1次アウトカムは明確か?
明確である(1つに決まっている)
論文のアウトカムは真のアウトカムか?
真のアウトカムである。
1.DESIGN®褥瘡重症度分類用(表1)
1)Depth(深さ)創内の一番深いところで判定し,真皮全層の損傷(真皮層と同等の肉芽組織が形成された場合も含める)までをd,皮下組織をこえた損傷をDとし,壊死組織のために深さが判定できない場合もこのDの範疇に含める。2)Exudate(滲出液)
ドレッシング交換の回数で判定する。ドレッシング材料の種類は詳しく限定せず,1日1回以下の交換の場合をe,1日2回以上の交換の場合をEとする。3)Size(大きさ)
褥瘡の皮膚損傷部の,長径(cm)と短径(長径と直交する最大径(cm))を測定し,それぞれをかけたものを数値として表現するもので,100未満をs,100以上をSとする。持続する発赤の場合も皮膚損傷に準じて評価する。4)Inflammation/Infection(炎症/感染)
局所の感染徴候のないものをi,感染徴候のあるものをIとする。5)Granulation tissue(肉芽組織)
良性肉芽の割合を測定し,50%以上をg,50%未満をGとする。良性肉芽組織の量が多いほど創傷治癒が進んでいることになり,本来なら数値が逆であるが,大文字が病態の悪化を表現しているためこのような記述方法となった。なお,良性肉芽とは必ずしも病理組織学的所見とは限らず,鮮紅色を呈する肉芽を表現するものとする。6)Necrotic tissue(壊死組織)
壊死組織の種類にかかわらず,壊死組織なしをn,ありをNとする。7)Pocket(ポケット)
ポケットが存在しない場合は何も書かず,存在する場合のみDESIGNの後に-Pと記述する。たとえば,深さ,大きさ,壊死組織が重度であり,他が軽度でポケットの存在する場合は,DeSigN-Pと表記する。日本褥瘡会より引用
評価者バイアス
2ページ目の最初に書いている。
2名のauthorが評価していると記載あり。
この論文の場合は,RCTとSRの著者が同じ・・・。
これは何とも・・・!?
2015年のRCTを読む方がいいかもしれない。
Ann Intern Med. 2015 Feb 3;162(3):167-74. doi: 10.7326/M14-0696.
A nutritional formula enriched with arginine, zinc, and antioxidants for the healing of pressure ulcers: a randomized trial.
Cereda E, Klersy C, Serioli M, Crespi A, D’Andrea F; OligoElement Sore Trial Study Group.
PMID: 25643304 DOI: 10.7326/M14-0696
出版バイアス
4ページめの左カラムに記載あり。
Visual inspection of funnel plots showed that publication bias was unlikely.
と本文中に記載あり。
ファンネルプロットはないのだが,出版バイアスはなさそうだ。と書かれている。(publication bias was unlikely)
元論文バイアス&異質性バイアス
2ページ目に記載あり。
RCTのメタ分析であると記載あり。
組み入れられている
3本の論文だけですが大丈夫ですか?
異質性が高くなければ問題ないが,異質性が高いと適切かどうかが疑わしくなるかもしれない
I2=58.6%で高くなければ低くもない。異質性はありそう。
3本中,2本は同じ著者の論文で,それだけだと異質性は低い。
結果は何か?
対照介入と比較して,アルギニン,亜鉛および抗酸化剤で強化された処方は,潰瘍面積が15.7%小さくなった。
(-15.7%, 95%CI [ -29.9~-1.5 ], P=0.030 ; I2=58.6% )
論文の結論
このシステマティックレビューは,アルギニン,亜鉛,酸化防止剤を強化した配合物を経口補充剤およびチューブ供給剤として少なくとも8週間使用することにより,標準的な配合物に比べてPUの治癒が改善されることを示している。
シナリオの患者さんに論文の結果をどう当てはめられますか??
今回のシナリオの患者さんに結果をもとにどう向き合えるか?
出てきた意見等は以下の通りでした。
- エンシュア以外に何かたべられるのか?介護士さんから食事量が落ちているとの話が出ているのでそれを突っ込んで聞き取るのも大事で,患者さんの状態を知りたいところ
- 食事の形態を徹底的に栄養士さんと考える!言語聴覚士の意見ももらう
- STさん,管理栄養士さん,歯科衛生士さん,摂食嚥下のキーパーソンがたくさんいるので意見を集めるのもいいかも
- 栄養状態を評価したい➡評価ツールを使う?
- 食事をとれていないのはエンシュア®に飽きているからかも??
- 患者さんはエンシュア®やエンシュアH®を飲みたいのか?食事を楽しみたいのではないのか?
- 患者さん自体の関心はどこにあるのだろうか?に注目しても良いかもしれない
- 患者さんや家族さんが望むのならば,メイバランス®などを使っても良いかもしれない➡褥瘡が治ってないまま亡くなってしまうと,家族さんが「もっとしてあげられることあったんじゃないか?」って思ってしまうかも
- 本人と家族の意向次第かもしれない
- 胃の容量が下がって入らない時はエンシュアHは重宝する
*エンシュアやラコール,エネーボといった医療用の栄養製剤以外にも市販では上に挙げたようなものがあるので,参考としてリンクを貼っています
感想
ざっくりとまとめました。いつもながら,まだまだ勉強不足であることを痛感しています。
論文の結果から沢山の意見が出ました。答えは出ません。
というよりも目の前にいる患者さんにとっての答えはなんだろう?と議論するキッカケ,スタートラインが見えたのではなかろうかと僕は感じました。
「臨床における結論は論文の結果とは一致しないことが当たり前」ことを再認識しました。
AIが進化し,多くの役割を担う時代は来るとは思います。きっと妥当性の高い論文とその結果をはじき出すことは想像ができます。
しかし,現状は論文の結果=臨床に摘要する最適な答えにならない訳で,AIに臨床判断の全てを決められるわけではないでしょう。
最後に今回の抄読会を〆る名言を。
やっぱりエビデンスと実臨床をつなぐ架け橋は人間が行わなければならないっ!!



今回の記事はいかがでしたか?アナタのお役に立てていれば幸いです!
もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆
待ってます!!













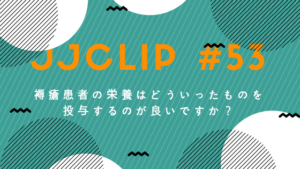
記事の感想など,ひとこと頂けますか?