| 提唱した人 | ベンサム(Jeremy Bentham)[1748~1832]イギリスの法学者・哲学者 |
| どんな内容? | 個人の行為の判断基準が幸福の追求にあるのと同様に,社会の目的は「最大多数の最大幸福」の実現にあると説いた。 |
| 利点 | 個人の利己主義を抑制する |
| 問題点 | 集団の利己主義を肯定してしまう。相対価値によって幸福の増大を捉えるため,個人の自由が無視されてしまうことが生じ得る |
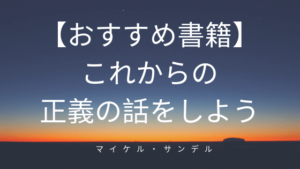
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
前回の記事から,『これからの正義の話をしよう』を読んで学んだことを外部記憶として記事にしてます。
功利主義ってどんな考え方?
道徳の思考の原理は幸福,すなわち苦痛に対する快楽の全体的な割合を最大化すること。ベンサムは,正しい行いとは「効用」を最大にするあらゆるものと主張している。
- 誰もが心地いいことを好み苦痛を避ける。そしてこの感覚は我々の行為を支配し,意思決定をする
- 心地よいことが,苦痛にたいしてより多い割合を占めることが,幸福を最大化することである
- よって幸福を最大にするために,あらゆる手段を取るべきである
 けいしゅけ
けいしゅけここだけを見ると,功利主義って分かり易いわな。
誰にとっても心地良いことを増やし,苦痛を減らせば社会全体がハッピーやんね?って言いたいわけやもん。
でもでも,思考実験をしてみると意外にも功利主義には弱点があることが見えてくるんや。
功利主義で考える事例
ベンサムが提案した事例として「貧民管理」が本文で挙げられている。



路上の物乞いを減らすことを目的とした計画で,功利主義を知る上で非常に分かり易い事例や。
路上で暮らす物乞いによって,通行人は2通りの意味で幸福を減らされている。
① 情け深い人は,憐れみで心が痛む
② 非情な心の持ち主は嫌悪で不快になる
これらによって,社会全体の効用は減少する。だから救貧院なるものを建設して路上の物乞いを収容すべきだ。
これによって,路上で暮らす物乞いは家を得ることができる。路上で人知れず餓死したり,襲われるリスクから救われる(幸福の増大)。中には路上で暮らしている方が幸福だという者がいることは認めるものの,物乞い全員がえる幸福の総和は,一部の路上暮らしを良しとする人が被る苦痛よりも大きいと考える。
通行人は,路上の物乞いに出会うことが無くなるため,幸福は増大する。
ちなみに,救貧院の運営資金は入居した物乞いが自分で働いて稼いだお金で賄われる。さらに,物乞いを救貧院へ引き渡した市民には報奨金が支払われる(この報奨金は物乞いが負担する)
物乞いにとって,ひどい仕打ちのように見えるかもしれない。
しかし,社会全体の幸福度は増大しているのではないか?
これがベンサムの主張や。
功利主義への反論①:個人の権利が棄損される
ベンサムの主張を見る限り,反論は間違いなく存在する。
1つが,個人の権利が棄損されることや。
社会全体の幸福度が増大するんやから,1人ひとりの権利を尊重してなんかいられません!
こうなってしまう。
著書本文では,これを『キリスト教徒をライオンに投げ与える』『拷問は正当化されるか?』といった事例を挙げて反論を述べている。
ザックリ言えば,1人の人間が犠牲になることでみんながハッピーになる…。そんなもん,ハッピーちゃうやろ??という感じ。
人間の権利や尊厳は効用を超えた道徳的基盤を持っている
これからの正義の話をしよう p.68
功利主義への反論②:価値を共通通貨へ変換する事は不可能
著書本文p.79で『苦痛の代償』として挙げている内容が非常にわかりやすい。
いくらもらったら,不快な体験を甘受できますか?というものが記載されているんやけど,これらに付いた値段が誰もがそれでOK!となるわけちゃうやん!というもの。
例えば,上の前歯を引き抜かせるのにいくらもらいたいか?という質問が書かれているけれど,いくらもらっても嫌です!と答える人がいるのは容易に想像がつく。



幸福の増大や苦痛の減少を,あらゆる事例に対してい数値化して比較できるのか?という問いへの回答が不可能であることがこれでわかるわな。
功利主義とトロッコ問題~フィリッパ・フットが提起した思考実験~
功利主義と道徳問題を考える思考実験として有名なのがトロッコ問題。
次の問題に対して,道徳的に見て「許される」か「許されない」どちらかで答えなければならないとする。
1台のトロッコが走ってきた。しかし様子がおかしい。なんとブレーキが壊れ制御不能になっているのだ。その先には5人の作業員が線路上にいる。このまま暴走したトロッコが進めば彼らは確実に轢かれて命を落とすことになる。
この時,A氏は線路の分岐器の前に立っていた。
分岐点を操作し,トロッコの進路を切り替え進路を変えることができる。しかし,その先にも作業員が1人いるではないか(B氏とする)。
A氏が分岐器を操作すればB氏が命を落とすことになる。ただ…5人の命が助かることになる。
さて問題。
A氏が分岐器を操作して,B氏のいる線路へ進路を変えることは道徳的に許されますか?
(言い換えると,B氏ただ1人の犠牲をもって,5人の命が助かる…。A氏が分岐器を操作する事は道徳的に許されますか?)



功利主義は,この問題に対して「許される」と答える。なぜなら,相対的に見て助かる人数が多く,犠牲になる人数が最小になるからや。


選ぶことなんて…できないでしゅよ!!!!
[/ふきだし]









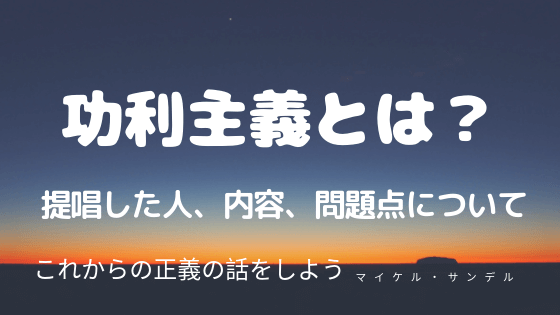


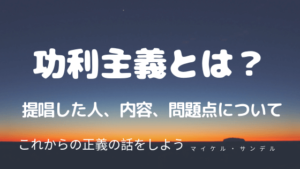
記事の感想など,ひとこと頂けますか?