僕,痛風なんですがビールじゃなくて焼酎とかワインならいいですか?
AHEADMAP関東支部ツイキャス#5 に参加したで!
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
ツイキャスのテーマで扱った論文の結果はもちろん,参加した感想をレビューします!
ある町の薬局にて,初めて来局された患者さんからこんなことを聞かれました。
「僕,痛風の治療しているんだ。以前痛みも出たことがあってね。食事には気を付けたいんだけどお寿司とかお酒好きなんだよね。
でもプリン体の多い食品とかビールはなるべく避けた方がいいって言うじゃない。
ビールじゃなければいいかな? 焼酎とかワインならいいかな?」
<患者背景>
高血圧と痛風の診断を受けており,以下の薬を服用している。
・フロセミド20mg 1錠 分1 朝食後
・アロプリノール100mg 1錠 分1 朝食後
早速食品のプリン体含有量,アルコール飲料と痛風疼痛発作の関連を検討した文献を検索したところ次の論文がヒットし,読んでみることにしました。
今回勉強した論文タイトルとURLの紹介
Am J Med. 2014 Apr;127(4):311-8. doi: 10.1016/j.amjmed.2013.12.019. Epub 2014 Jan 17.
Alcohol quantity and type on risk of recurrent gout attacks: an internet-based case-crossover study.
PMID: 24440541
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24440541
[/box]
問題の定式化
それでは,問題の定式化をば。
問題の定式化:仮想症例シナリオのPECOを書いていくでッ!!
- P: 痛風患者 *お寿司やお酒が好き,フロセミドおよびアロプリノール服用中
- E: 焼酎やワインした場合(プリン体含有のアルコールを避けた場合)
- C: ビールを飲むのと比べて
- O: 痛風発作の再発リスクは上がるのか?
問題の定式化:論文のPECO(PICO)を書いていくでッ!!
- P:痛風と診断された12カ月以内に痛風発作を起こしている18歳以上のアメリカ在住の患人 *N=724,平均54歳(21-88歳),男性(78%),肥満指数(平均BMI 32.1kg / m 2),白色人種(88.7%)
- E: 24時間以内に中等度以上の飲酒をした場合
- C: 24時間以内に飲酒をない場合と比べて
- O: アルコール消費量と再発性痛風発作のリスクとの間に用量反応関係はあるか?
- T: 追跡期間1年間
 けいしゅけ
けいしゅけ今回の論文のPECO。
けいしゅけはこんな感じで考えてみました。
どうやろか?
論文のチェックポイント4項目を書き出すでッ!!!
- 真のアウトカムか? ➡ 真のアウトカム
- 研究対象集団(PECOの”P”)の代表性:外的妥当性が高いか?つまり一般人口に研究対象集団が近いか? ➡ 今回の論文では白人男性の率が高いので,日本人に対してそのまま当てはまるかはわからないと思われる
- 交絡への配慮は? ➡ 潜在的な時間変化型交絡因子を調整している,とある。(観察研究 [症例-対象研究] の為,交絡の可能性は排除しきれないかもしれない)
[/list]
論文の結果のを書き出すど~ッ!!!
アルコール消費量と再発性痛風発作のリスクとの間に有意な用量反応関係あり(傾向についてはP <.001)
24時間以内に飲酒しなかった場合に比べて,
> 1-2杯の飲酒があった場合に再発性痛風発作のリスクは1.36(95%信頼区間[CI],1.00-1.88)
> 2-4杯の飲酒があった場合に再発性痛風発作のリスクは1.51(95%信頼区間[CI],1.09-2.09)
と高かった。(1杯の飲酒量はアルコール量で約15gとしている)飲酒量をアルコール量に換算するサイト ➡ KIRINのWebサイト
消費するワイン,ビール,または酒はいずれも痛風発作の危険性の増加と関連していた。
すなわち,アルコール飲料の種類にかかわらず,偶発的なアルコール消費は,潜在的に中等度の量を含む再発性の痛風発作の危険性の増加と関連するかもしれない。
痛風患者の再発性痛風発作のリスクを減らすためには,あらゆる種類のアルコール摂取を制限する必要があるだろう。
痛風発作の再発リスクは増すか?結果の定式化:仮想症例シナリオPECO
- P: 痛風患者 *お寿司やお酒が好き,フロセミドおよびアロプリノール服用中
- E: 焼酎やワインした場合(プリン体含有のアルコールを避けた場合)
- C: ビールを飲むのと比べて
- O: 痛風発作の再発リスクは同様に上昇する
論文の結果を仮想症例に当てはめると・・・
なかなか興味深い結果ですねぇ。
僕自身が勉強不足だったのですが,尿酸値の上昇ってプリン体の摂取と必ずしも関係がないんです。
補足として下にメモを貼っておきます。
アルコールの消費は,尿酸排泄を減少させ,その産生を増加させることによって高尿酸血症を引き起こす。
PMID: 6470146 PMCID: PMC425250 DOI: 10.1172 / JCI11151
アルコール飲料の消費は,高尿酸血症および痛風と関連している
PMID: 7144847 DOI: 10.1056 / NEJM198212233072602
つまり,摂取するアルコール量が多くなれば血中の尿酸濃度は上がってしまう。
そやから,痛風発作のリスクはビールであろがワインや日本酒であろうが同じように上がってしまうって訳です。
なので,仮想症例に対して薬剤師として言うならば
「実は尿酸値が上がってしまう原因ってプリン体だけが問題とちゃうんです。根本的にアルコール自体が尿酸を体の外に出しにくくしてしまうんです。さらに,お酒を飲んだ時の利尿作用で体の中の尿酸が濃くなるんです。厄介ですよね。そやから,ビールじゃなきゃ良いって事とちゃうみたいですよ~。発作出てほしくないので,ワインや日本酒を飲むにしても量は少なめでお願いしますっっっ!!!」
っと愛嬌を振りまきつつ言ってみようかなぁと考えました。
感想
今回のAHEADMAP関東のツイキャス配信で尿酸値の上昇メカニズムについて盲点が自分にあることが発覚!
メッチャ勉強になりました。
配信中に貼られるリンクや,それを起点に自分で論文検索をしてみたりと,思わぬ発見と言いますか勉強のチャンスが降ってきたのが嬉しかったです。
最後に言いたいのは,
「プリン体ゼロのビールは存在意義もゼロかも知れない」



今回の記事はいかがでしたか? アナタのお役に立てていれば幸いです!
もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆
待ってます!!









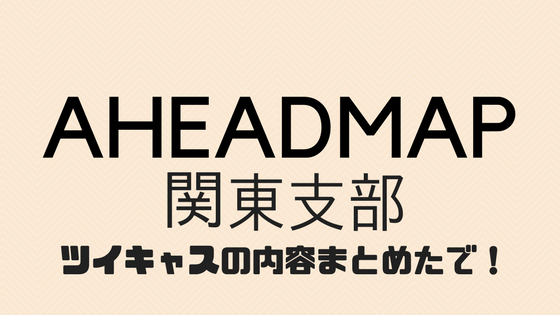
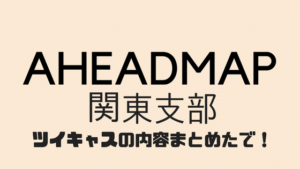
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (1件)
一言で言うと素晴らしい。
説明が、論理的で、根拠も明確で、分かり易い。
図や写真の例示も的確で、面白いだけでなく、記憶に残る。
薬剤師にしておくのは勿体ない才能です。
いや、それこそが患者と接する薬剤師の本来の在り方かも知しれないですね。
これからも、迷える患者の助けになられるよう、頑張って下さい。