根拠となる資料を示します
(11) 自家製剤加算
ア 「注6」の自家製剤加算は,イの(1)に掲げる場合以外の場合においては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,イの(1)に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
イ 本加算に係る自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。
ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは,薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に,次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ) 液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合
オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
カ 自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。
キ 「予製剤」とは,あらかじめ想定される調剤のために,複数回分を製剤し,処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
ク 通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,「注6」の「イ」を算定できる。
ケ 自家製剤を行った場合には,賦形剤の名称,分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
コ 自家製剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より 引用
注6ってなんですか?
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より引用
(一部筆者により中略,強調を加えています。)
 けいしゅけ
けいしゅけ










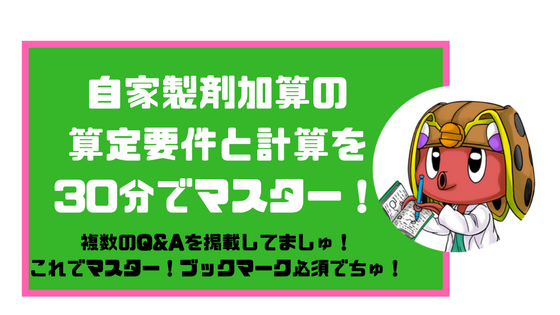







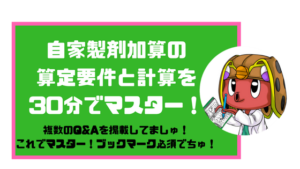
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (2件)
新人医療事務員です。
自家製剤加算算定で調べてるうちに
こちらに、たどりつきました。
アマリール錠3mg®の半割指示処方が来ました。アマリール®には1mgと0.5mgが存在するので,自家製剤加算は取れないですよね??
チッチッチ。理解が浅いです。分割した医薬品と同一規格のアマリール®,例えばアマリール錠1.5mgが存在しない限りは自家製剤加算は算定できます!
とありますが、
疑義解釈資料の送付について(その1)
平成28年3月31日事務連絡
問22
RP A錠200mg 1回1.5錠疼痛時服用
(注A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。)
(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。
とあります。
この二つの違いは???
どーしてもわかりません。
申し訳ないのですが、解説頂きたいのです。
長くなって申し訳ありません
まる子 様
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。しばらくブログが放置状態となっておりました。
ご質問の件について
ポイントは【服用する錠剤の個数と,半割の手間がかかることが両立するか?】といったところでしょうか。
「低用量組み合わせ 0.5錠+1錠 (服用する錠剤2つ,半割あり) ➤ 高用量 1錠 (服用する錠剤1つ,半割なし)」
「低用量組み合わせ 1錠+1錠 (服用する錠剤2つ,半割なし) ➤ 高用量 0.5錠 (服用する錠剤1つ,半割あり)」
この2つの例に関して,前者が疑義解釈例であり,後者がブログ記事本文で取り上げたグリメピリドの例です。違いを考えてみましょう。
まず,前者は高用量の調剤をすれば服用錠数は1つです。低用量の組み合わせにすると半割する必要が出るし,服用する錠剤の個数は1.5錠で高用量のそれより多くなります。すると低用量の組み合わせで調剤する妥当性があるか?と言えばなんとも言い難いですね。
次に後者について。低用量の組み合わせでは2錠飲む必要がありますが,高用量半割ならば0.5錠1つだけ飲めば済みます。飲み間違いリスクを考慮すると服用種類は少ない方が良さそうに感じます。
このように,自家製剤調剤算定の算定に妥当性があるか?を考慮すると算定の可否が分かれることを飲み込めたりするのかなぁと思ったりして…。
如何でしょうか?