まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
さてさて,調剤料に関する記事を連載として書いていきます。
今回は2つ目,「計量混合調剤加算(以下:計量混合加算と表記)の算定要件について」です。
 けいしゅけ
けいしゅけ1つめは,内服薬調剤料の計算方法をたった30分で理解する!でした。良かったらこちらの記事も読んでみてください☆


今どき手計算なんかせぇへんねんから調剤料の計算なんか不要ちゃうの?という思われるかもしれません。たしかにそうです。
しかし,停電になってしまったり災害に見舞われた時,手計算ができるのがプロではないでしょうか。そもそも,内服薬の調剤料の算定の基礎知識が備わっていないと,レセコンが自動計算してくれたものが合っているのかチェックができません。
なので少なくとも最低限の知識を頭に入れておく重要性はあるのではないでしょうか。
計量混合加算って何ですか?



タコちゅけ,計量混合加算って何ですか?



う・・・これまた改めて聞かれると,「粉や水,軟膏を混ぜる事」ってことが思い浮かぶ感じでちゅね。
詳しい点数については覚えていないでちゅ。



お~,今回もエエ感じやね。最低限の知っている・・・かも。ってくらいにはなってるやん。
タコちゅけ,今回はこれをキッチリ説明できるように勉強してみよっか🎵
まとめるの,手伝ってくれるかい?



ハイでちゅ!!
計量混合加算とは
ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。
処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。
(12) 計量混合調剤加算
ア 「注7」の計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,液剤,散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外
用薬を調剤した場合に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。
なお,同注のただし書に規定する場合とは,次の場合をいう。
(イ) 液剤,散剤,顆粒剤,軟・硬膏剤について注6の自家製剤加算を算定した場合
(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合
イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。
ウ 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。
ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は,この限りでない。エ 計量混合調剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]



この注7って何でちゅか!?ややこしいでしゅ!!



これや☆
注7とは?
01 調剤料
中略
注7 2種以上の薬剤(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,内服薬若しくは屯服薬又は外用薬を調剤した場合は,計量混合調剤加算として,1調剤につきそれぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
ただし,注6に規定する加算のある場合又は当該薬剤が注6のただし書に規定する別に厚生労働大臣が定める薬剤である場合は,この限りでない。
イ 液剤の場合 35点
ロ 散剤又は顆粒剤の場合 45点
ハ 軟・硬膏剤の場合 80点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB]
(一部筆者により中略,強調を加えています。)
注6って何?
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より
(一部筆者により中略,強調を加えています。)



厚労省資料の計量混合加算に関する記述がややこしくて良くわからないでちゅ💦



まとめよか~
計量混合加算とは? カンタンな言葉でまとめまっせ!
簡単な言葉で表すと…
計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して
- 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
- 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
- ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
- 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合
に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。
| 剤形 | 点数 | 予製の場合
(20/100の点数) |
| 液剤 | 35点 | 7点 |
| 散剤/顆粒剤 | 45点 | 9点 |
| 軟膏剤/硬膏剤 | 80点 | 16点 |



どや!
スッキリまとまったやろ?(注7とか,注6とかいらんねん☆ややこしい。)
ちなみに内服薬と外用薬で点数に変わりないで☆



先生,すっごく分かり易くまとまってるでちゅ!
流石でちゅ!



やたーっ!!タコちゅけに褒められた!
フフンフ~ン🎵
計量混合加算の算定パターンを見てマスターしよう!
ここからは実際の処方例を元に,計量混合加算の算定方法をマスターしていこうと思います!
軟膏に関する計量混合加算(80点)の算定パターン



これ,僕の実体験です(笑)
混合する必要性が不明であっても,医師からの指示がある=医療上の必要性がある,となった場合には算定ができるねん🎵



この処方…ビミョーでちゅ💦💦



ホンマでしゅか!?
これ,ビックリでちゅ!!



ホンマや。根拠となる参考文献を示すわな。
計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし,分包品は,あらかじめ所定の分量が計量され,既製品として流通しているものです。
したがって,そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には,計量混合調剤加算を算定することは認められていません(分包品の販売の有無ではなく,その調剤において分包品を使用したか否かで判断します)。
保険調剤Q&A じほう社より 引用(強調は筆者による)



な?ホンマやろ??
実際問題,知らずにチューブから中身を絞り出して混合調剤したもので計量混合加算を取ってしまう事って多いと思うねん。
しかしやな,厳密には「アウト」や。
堅苦しいなぁ!って思うかも知れへんけど,仮に保険監査で「チューブから出すなら計量の必要はないですよね。つまり,「計量」してませんやん?なのに加算を取ってたんなら返還してくださいな。」って言われちゃったら,「ええ,たしかに・・・。わかりました(涙)」ってなってまうもんね。



バラ包装を発注しまちゅ!!



うむっ!!それが正解や!
計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,混合して
- 液剤や散剤,顆粒剤として内服薬/屯服薬を調剤した場合
- 軟・硬膏剤等として外用薬を調剤した場合
- ドライシロップ剤を液剤と混合した場合
- 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合
に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。
これが計量混合加算の定義でしたものね。
ところが本件は自家製剤加算で算定しましょうという回答でした。根拠となる厚労省資料を示します。
(11) 自家製剤加算
ア 「注6」の自家製剤加算は,イの(1)に掲げる場合以外の場合においては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,イの(1)に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
イ 本加算に係る自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
(イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
(ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
(ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。ウ 「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは,薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。
エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に,次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。
(イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
(ロ) 液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合オ 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
カ 自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。
キ 「予製剤」とは,あらかじめ想定される調剤のために,複数回分を製剤し,処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。
ク 通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,「注6」の「イ」を算定できる。
ケ 自家製剤を行った場合には,賦形剤の名称,分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。
コ 自家製剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より
注6って何?
6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は,自家製剤加算として,1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては,投与日数が7又はその端数を増すごとに),それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。ただし,別に厚生労働大臣が定める薬剤については,この限りでない。
イ 内服薬及び屯服薬
( 1 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点
( 2 ) 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の屯服薬 90点
( 3 ) 液剤 45点
ロ 外用薬
( 1 ) 錠剤,トローチ剤,軟・硬膏剤,パップ剤,リニメント剤,坐剤 90点
( 2 ) 点眼剤,点鼻・点耳剤,浣腸剤 75点
( 3 ) 液剤 45点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 平成30年 厚生労働省告示第43号(調剤点数表)PDF [132KB] より
(一部筆者により中略,強調を加えています。)



厚労省資料の記述がややこしくて良くわからないでちゅ💦



まとめよか~
自家製剤加算とは? カンタンな言葉でまとめまっせ!
自家製剤とは,個々の患者に対し市販されている医薬品の剤形では対応できない場合に,医師の指示に基づき,容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤,溶解補助剤,懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用,ろ過,加温,滅菌等)を行った次のような場合であり,既製剤を単に小分けする場合は該当しない。
- 割線のある錠剤を医師の指示に基づき分割した場合は,錠剤として算定する。ただし,分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。
- 錠剤を粉砕して散剤とすること
- 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること
- 主薬に基剤を加えて坐剤とすること
- 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒,基剤等の賦形剤を加え,当該医薬品と異なる剤形(軟膏など)の医薬品を自家製剤の上調剤した場合。ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合/液剤を調剤する場合であって,医薬品医療機器等法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合については算定することができない。
自家製剤加算は,上記の①に掲げる錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては,自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
⓶~⑤に掲げる場合おいては,投薬量,投薬日数等に関係なく,自家製剤による1調剤行為に対し算定し,投薬量,投薬日数に関係なく,1調剤行為に対し所定の点数を算定できる。
その場合の点数は以下の通り
| 剤形 | 点数 | 予製の場合
(20/100の点数) |
| 内服薬及び屯服薬 | ||
| 錠剤の半割
(割線のあるものに限る!デザイン割線はダメ) | 20点 / 7日ごとに | 4点 / 7日ごとに |
| 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤
又は エキス剤の内服薬 | 20点 / 7日ごとに | 4点 / 7日ごとに |
| 内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)
又は エキス剤の頓服薬 | 90点 | 18点 |
| 液剤 | 45点 | 9点 |
| 外用薬 | ||
| 錠剤,トローチ剤,
軟・硬膏剤,パップ剤, リニメント剤,坐剤 | 90点 | 18点 |
| 点眼・点鼻・点耳剤,
浣腸剤 | 75点 | 15点 |
| 液剤 | 45点 | 9点 |
自家製剤加算を算定した場合には,計量混合調剤加算は算定できない。
この一文の理解が実はメッチャ大事やで☆
自家製剤加算も計量混合加算もとれるようにみえる処方ってあるんです。
例)次のような処方の場合です。(RP.01とRP.02の服用時点が問題や!)
RP.01
A錠 0.5錠(割線あり,低用量規格製剤なし)
1日1回 14日分 (錠剤を半割する)
RP.02
B散 0.5g
C散 0.5g
1日1回 14日分 (混合指示が有り,軽量混合する)
- RP.01とRP.02の服用時点が同一の場合 ➡ 同一「剤」のため,自家製剤加算と計量混合調剤加算を同時算定ができません。
- RP.01とRP.02の服用時点が異なるの場合 ➡ 異なる「剤」のため,RP.01で自家製剤加算,RP.02で計量混合調剤加算をそれぞれ算定することができます。
通常,成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を,6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において,薬剤師が必要性を認めて,処方医の了解を得た後で,単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても,自家製剤加算として,次の点数を算定できます。
- 錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤又はエキス剤の内服薬 20点(処方日数7日ごとに20点)
- 内服用固形剤(錠剤,丸剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤)又はエキス剤の屯服薬 90点 / 1調剤
- 液剤 45点 / 1調剤



濃いでちゅね!!



うん,濃いんや。できればここでは語りたくなかった。
記事が長くなるからね。
しかし!これを語らずして説明しても「なんかよくわかんない!」というギモンを残してしまうじゃないか!
そんな無責任なことができるかーーーーーーーーーーっ!!!!!!
・・・ということで書きました。



(暑苦しいでちゅ・・・。)
散剤の計量混合加算(45点)の算定パターン



同じ「剤」の計量混合加算の場合,日数が同じなら「1調剤」とみなされてしまうんでちゅね。



せやねん。
もしも日数が一緒で「剤」が同じやったら,全部まとめて混合できるやろ?っていう考えがあるんやね。



ちなみに,上記の例でいうところのRP.01とRP.02で同じ服用時点かつ,同じ日数で,医師から「RP.01とRP.02は別々に分包してください」と指示があった場合は2調剤になるんでしゅか??



ナイス質問や!
タコちゅけ,すまん。
この場合は,2調剤にカウントはされへんねん。医師の指示には関係なく「服用時点が同じで処方期間が同じものは1調剤とみなす」とされてるねん。



そうなんでちゅね。
決まり事やし,仕方ないでちゅね。残念でちゅけど,算定することばかりを目的にしないようにしなくっちゃ!と前向きに考えましゅ。



偉いよ君は。素晴らしいよ,ううう。



軟膏と同じパターンや。もう一回,資料を示すで。
計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品を「計量かつ混合」した場合に算定することが認められています。しかし,分包品は,あらかじめ所定の分量が計量され,既製品として流通しているものです。
したがって,そのような包装単位の医薬品を使用して調剤した場合には,計量混合調剤加算を算定することは認められていません(分包品の販売の有無ではなく,その調剤において分包品を使用したか否かで判断します)。
保険調剤Q&A じほう社より 引用(強調は筆者による)



散剤まで…。驚きでちゅ!!



知らなかったなら驚くのは当然やわ。
軟膏もそうやけどさぁ,ちょっとこの規定って変やなぁと思うもん。
分包品から中身を取り出して「計量」した場合に,分包品に表記されている量よりもほんのちょっと多く入っている場合ってあるねん。そやから,結局分包品も中身を出して重量を「計量」する必要があることがしばしばある。
(軟膏とかの場合も一緒やで?絞り出してピッタリ5gチューブから5gの内容が出てくるとは限らへんもの。経験的に言えば,軟膏の場合,絞り出したらちょっと量が減るわ。)
ほな,そうした事実があるのに「計量してないから加算は取れない」って言えるの?って思ってまう。理論値≠実測値なんやもん。
とは言え,こりゃ決まり事やから,無視して算定するのはご法度なわけで。
モヤモヤするわ~。



分包品を使ったら絶対に計量混合加算を取れないものなんでちゅか??



良いところ付いてくるやん!
実は分包品を使っていても計量混合加算がとれる場合があるねん。
それは…



なるほど!!
分包品と言っても,必要な量が分包品の内容量の倍数と同じにならない場合は,「計量」が必要になるので,計量混合加算を取れるってわけでちゅね!!



そう言う事やっ!!!!
液剤の計量混合加算(35点)の算定パターン
カンタンなので一番最後に持ってきました。
厚労省資料を再度確認しましょう。
(12) 計量混合調剤加算
ア 「注7」の計量混合調剤加算は,薬価基準に収載されている2種類以上の医薬品(液剤,散剤若しくは顆粒剤又は軟・硬膏剤に限る。)を計量し,かつ,混合して,液剤,散剤若しくは顆粒剤として内服薬又は屯服薬を調剤した場合及び軟・硬膏剤等として外
用薬を調剤した場合に,投薬量,投薬日数に関係なく,計量して混合するという1調剤行為に対し算定できる。なお,同注のただし書に規定する場合とは,次の場合をいう。
(イ) 液剤,散剤,顆粒剤,軟・硬膏剤について注6の自家製剤加算を算定した場合
(ロ) 薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤を調剤した場合
イ ドライシロップ剤を液剤と混合した場合は,計量混合調剤加算を算定するものとする。
ウ 処方された医薬品が微量のため,乳幼児に対してそのままでは調剤又は服用が困難である場合において,医師の了解を得た上で賦形剤,矯味矯臭剤等を混合し,乳幼児が正確に,又は容易に服用できるようにした場合は,「注7」を算定できる。
ただし,調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は,この限りでない。
エ 計量混合調剤は,医薬品の特性を十分理解し,薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より



一応言っておくと,計量混合加算も自家製剤加算も液剤は45点やからどっちをとっても実際問題あんまり関係なかったりもする…。



ただ,どちらを算定できるか「わかる」事は大事でちゅよね☆



そのとーり!エエこというやん。さすがタコちゅけ!
愛してるぜ!!



(フツーに愛してるとか言うなぁこの人。そんなところが好きでちゅけど。)
最後に:計量混合加算か,自家製剤加算や1包化加算か何を取るべきか迷うパターン
クソ長い記事もようやく終盤に差し掛かってきました。(30分で理解するなんて嘘やんけ!というクレームが来そうですが)
最後は応用編です。そして,こういったケースがなんやかんやで現場で出てくる疑問だと思いますので示していきますね☆



もしも同一の服用時点,「1剤」となっていた場合で,RP.01が15日分以上になれば,自家製剤加算として60点以上になるので,その場合は自家製剤加算を選択するのが良いね☆
【一包化加算】
(問2) 一包化加算を算定した場合においては,自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが,一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば,以下の処方において,処方1又は処方2で一包化加算,処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠,B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠,D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散,F散 1日1回就寝前 × 14日分(答) 算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は,原則として1調剤行為に対して算定することとしている。
質問の例においては,処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており,処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが,処方3は,一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく,一包化加算の算定対象とならないことから,処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。
平成22年 厚生労働省 疑義解釈資料の送付について(その3)より引用



「剤が異なっていれば1包化加算,自家製剤加算,軽量混合加算」は算定可能。これは大事やから覚えとこうね。
質問の処方で仮にRP.01とRP.02,RP01.とRP03.,RP02.とRP03.,RP.01とRP.02とRP03.がそれぞれ同じ「剤」だった場合には,重複して加算を取ることができへんねん。この場合は点数が高くなる方を算定すれば良いねんで🎵



めっちゃまとまってまちゅね。
よくわかりました。ありがとうございましゅ!!
Q.一包化加算を算定した場合,自家製剤加算および計量混合加算は「算定できない」とされているが,この要件は内服用固形剤のみ(一包化加算の算定対象とならない部分を除く)に適用されるものであると理解してよいか。
A.そのとおり。
平成22年3月19日日本薬剤師会 平成 22 年度調剤報酬改定に関するQ&A より引用



知らなきゃ算定漏れする代表例やね。
算定を目的化してはいけない。それは論外や。
けれど,現場の仕事として点数が付くものは算定すべきだと思うねん。
すごく記事として長くなってしまったけれど,今回はここまでにしよう☆



すごく量が多かったでしゅけど,知っておかないと算定はできないなぁって痛感したでちゅ。
先生,ありがとうございました。またよろしくおねがいしましゅ!!
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!








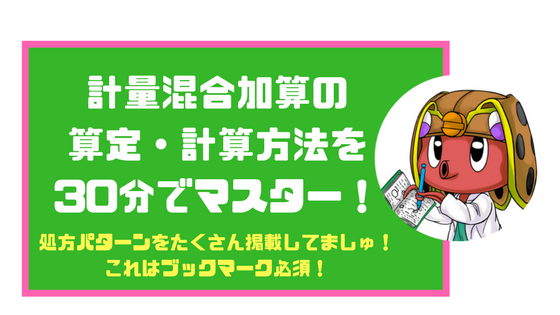
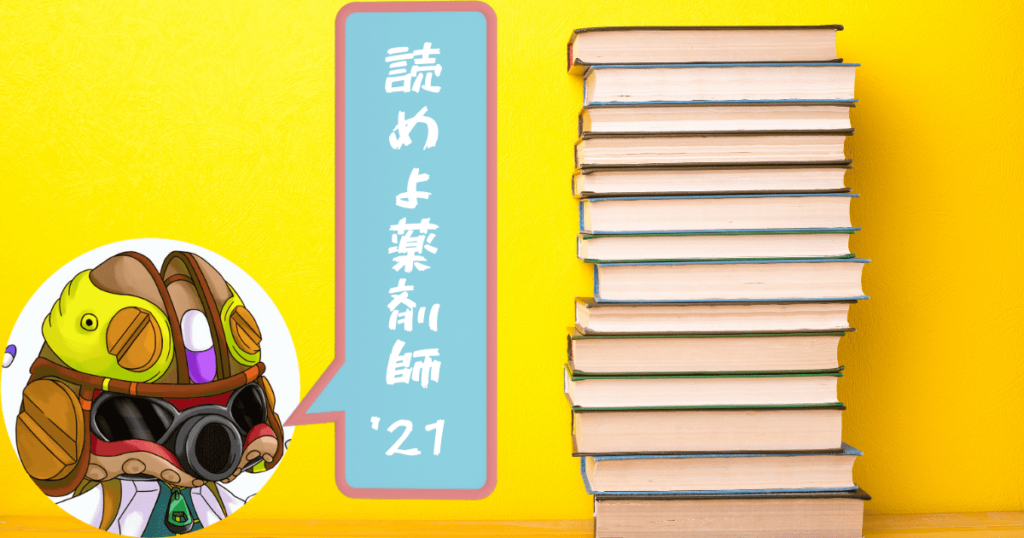
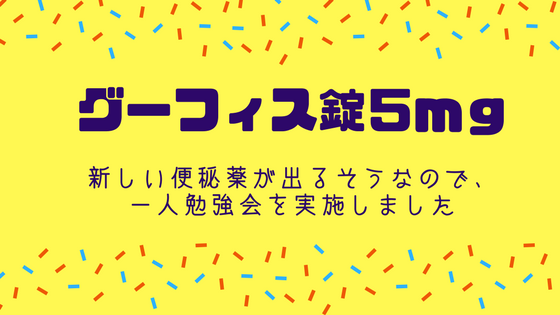
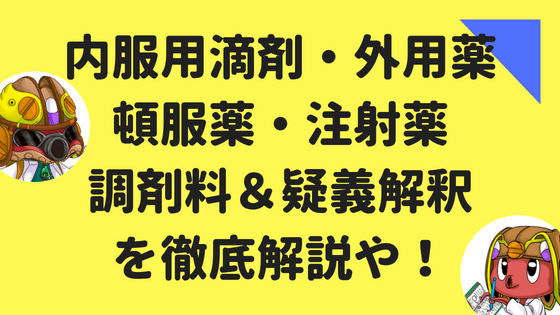


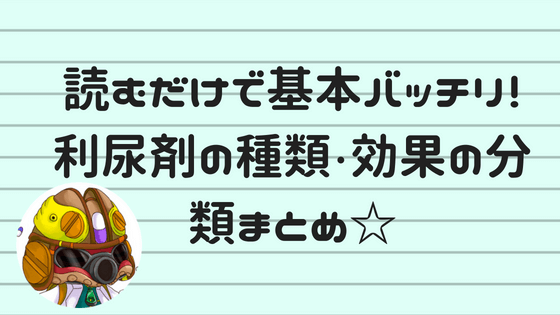
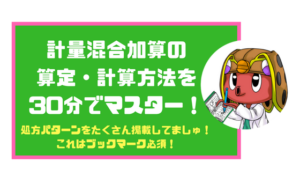
記事の感想など,ひとこと頂けますか?