一包化加算の算定要件や点数計算方法,6つの算定例,Q&Aで説明します
当ページのリンクには広告が含まれています。
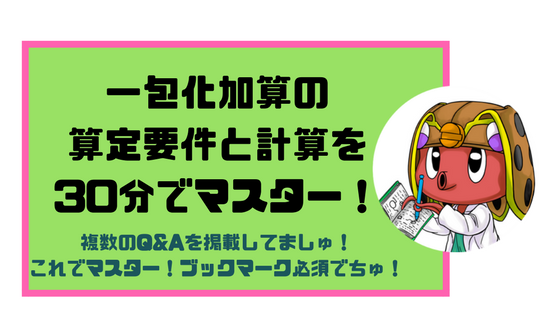
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
さてさて,調剤料に関する記事を連載として書いています。今回は4つ目,「一包化加算の算定要件について」です。
一包化加算って何ですか?
- 一包化加算って何ですか?という方のために説明しましょう。一包化加算とは,用法の異なる2剤以上(もしくは,1剤で3種類以上)を,服用時点(薬を飲むタイミング)ごとに一包として患者さんへお渡しした場合に算定する加算の事です
この記事は平成30年度版の保険調剤Q&Aを参考にして書いている記事やで。ハッキリ言うてしまえば,保険調剤Q&Aを読めば理解できるやんって内容やねん。
そやけど,独りで勉強するってしんどいやんね?しかも,できれば分かり易く説明されている方が嬉しい。
そんなアナタのために,内容をできる限りわかりやすく噛み砕いて記事にしました。良かったら最後までお付き合いください。
STEP.1
一包化加算の算定要件とは?
まずは,基本となる算定要件を説明します
STEP.2
一包化加算の算定点数の計算方法
次に,算定点数が計算できるよう説明します
STEP.3
一包化加算を算定した6つの具体例(処方例)と素朴なQ&A
実践的な内容で理解を深めましょう
STEP.4
一包化加算に関する過去に出た疑義解釈
あるあるな質問集です
この記事にこれだけの情報を盛り込みました。読み終わるころには,「一包化加算の算定要件はバッチリや!点数計算かてできてまうで!!どれどれ?一包化指示が入っている処方箋を持ってきてみなはれ☆」と言ってしまう自分と出会えるはずです🎵
目次
一包化加算の算定要件をわかりやすく説明します!
 けいしゅけ
けいしゅけ
タコちゅけ,一包化加算って何ですか?どんな時に算定できますか??
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
一包化はでちゅね,一包あたりに3種類以上の薬をまとめて1パックにまとめる(分包する)ことで算定しましゅ!たしか,点数は今回は変わらなかったはずでちゅが・・・。
[/ふきだし]
 けいしゅけ
けいしゅけ
はい,ブッブ~(●´ω`●)ハマッタナ
タコちゅけ,一包化加算の算定要件でよくある勘違いをしてござるよ🎵実はもう1つ,一包化加算を取れる要件があるんですじゃ!
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
なんでちゅとぉぉぉっ!!!「一包あたり3種類の薬品を分包する」以外の算定要件があるなんて・・・
教えて欲しいでちゅ!!
[/ふきだし]
 けいしゅけ
けいしゅけ
「教えて欲しいでござる」て言うてくれたら教えるわ。(だってタコちゅけかわいいねんもん🎵)
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
ぜ,是非とも教えてほしいでござる…でちゅ(く,屈辱でちゅ~!!!)
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
このぉ~・・・
[/ふきだし]
一包化加算の算定要件ってなんですか?
一包化とは,服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤 又は 1剤であっても3種類以上の内服用固形剤 が処方されているとき,その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいいます。なお,一包化に当たっては,錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものです。
ちなみに,一包化加算を取るにあたり,医師の了解(一包化指示)と,その旨を調剤録に記録する必要があります。
一包化加算について,図表を使って算定条件をまとめましたっ!
一包化加算は,服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤(散剤も含むよ!) 又は 1剤であっても3種類以上の内服用固形剤 を服用時点ごとに一包として患者さんに渡したときに算定できます。
 タコちゅけ
タコちゅけ
なるほど!
服用時点が異なっている2種類の薬,つまり「2剤」として内服薬調剤料を算定できる内服用固形剤であれば「2種類」でも服用時点ごとに一包にまとめれば一包化加算が取れる
わけでちゅね!!!
1剤で3種類以上を服用時点で一包にまとめれば一包化加算が取れるだけじゃないんやぁっ
[/ふきだし]
それでは,タコちゅけが理解した内容を表にしてみますね。
この場合やと,朝食後・昼食後・夕食後どの服用時点を一包化したとしても,1剤で3種類以上もしくは2剤2種類以上の薬をまとめていますので,算定要件を満たしています。よって,一包化加算を算定できます。
|
朝食後 |
昼食後 |
夕食後 |
寝る前 |
|
処方1
(朝・昼食後)
|
1カプセル |
1カプセル |
|
|
|
処方2
(朝食後)
|
2錠 |
|
|
|
|
1カプセル |
|
|
|
|
1.5g
(粉) |
|
|
|
|
処方3
(夕食後)
|
|
|
0.5錠 |
|
|
処方4
(昼・夕食後・寝る前)
|
|
1錠 |
1錠 |
1錠 |
一包化加算は
算定可能か? |
算定
可能 |
算定
可能
|
算定
可能 |
|
一包化加算の算定要件まとめ
- 処方2の朝食後「1剤」で3種類以上の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- 処方1と処方4において,異なる用法=「2剤」で内服薬調剤料を算定できる処方の,昼食後2種類の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- 処方3と処方4において,異なる用法=「2剤」で内服薬調剤料を算定できる処方の,夕食後2種類の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- ①~③のどの条件でも算定要件を満たすので,処方1~4が処方されている処方箋の場合は,どれかの要件を理由に一包化を算定することができる。
- 内服薬固形剤であればいいので,散剤が混じっても,散剤だけ*であったとしても一包化加算は算定が可能である。
*散剤だけの場合は計量混合加算との点数で高い方を算定する。同時算定は不可能。
- ちなみに,上記の処方1~4の場合,一包化加算を算定可能であり,寝る前は1種類だけである。この場合は薬をシートから取り出さず(分包せず)に患者さんにお渡しした場合でも服用に差支えがない旨,患者さんに確認ができていれば一包化加算の算定に問題は生じない。
[/list]
これで,算定要件に関しての理解はバッチリやで!!
根拠となる資料を示します
一包化加算の取扱いは,以下のとおりとすること。
① 一包化加算は,処方箋の受付1回につき1回算定できるものであり,投与日数が 42 日分以下の場合には,一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに 32点を加算した点数を,投与日数が 43 日分以上の場合には,投与日数にかかわらず 220 点を所定点数に加算する。
② 一包化とは,服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき,その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお,一包化に当たっては,錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
③ 一包化は,多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ,飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし,治療上の必要性が認められる場合に,医師の了解を得た上で行うものである。
④ 薬剤師が一包化の必要を認め,医師の了解を得た後に一包化を行った場合は,その旨及び一包化の理由を調剤録等に記載する。
⑤ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から,錠剤と散剤を別々に一包化した場合,臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが,処方箋の受付1回につき1回に限り算定する。
⑥ 同一薬局で同一処方箋に係る分割調剤(「区分番号 00」の調剤基本料の「注7」又は「注8」に係る分割調剤に限る。)をした上で,2回目以降の調剤について一包化を行った場合は,1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
⑦ 一包化加算を算定した範囲の薬剤については,自家製剤加算(「区分番号 01」の「注6」に規定する加算をいう。以下同じ。)及び計量混合調剤加算(「区分番号 01」の「注7」に規定する加算をいう。以下同じ。)は算定できない。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より 引用
 タコちゅけ
タコちゅけ
お馴染みの資料になってきてましゅね!
[/ふきだし]
そやね。さすがに見慣れてきたんちゃう?
『注〇における~』みたいなんが多くてわかりにくいね。けれど,根拠となる資料って大事やからね。知っておくべきやと思てる。
一包化加算の計算方法(算定点数について)はカンタン
算定要件が理解出来たら,一包化加算って何点の保険点数を計算したら良いの?って疑問が湧いてこぉへん??
実際問題,何点算定できるのか?がわかっていないと調剤録をみても意味不明ってことになっちゃうので,ここでしっかりと説明していきますわ☆
一包化加算の点数って何点ですか? 算定できる点数の計算方法が知りたいです!
42日分以下の場合 32点/7日分,43日分以上の場合 220点を算定して下さい
シンプルながら,これは重要やので覚えておきたい数字や。1週間ごとに32点が算定でき,上限は220点ってわけ。
一包化した日数と算定点数の関係
- 1~7日分までは32点
- 8~14日分で64点
- 15~21日分で96点
- 22~28日分で128点
- 29~35日分で160点
- 36~41日分で192点
- 42日分以上でで220点
一包化加算を算定した6つの具体例(練習問題も含む)と素朴なQ&A
算定要件の説明が終わったので,処方例を見ていきましょう。また,素朴な質問もあると思いますので,併せて紹介していきます。
Q&A ① 異なる2つ以上の診療科の処方箋を合わせて一包化。一包化加算は算定できる?
ある患者さんが病院で内科と整形外科を受診し,それぞれの科から発行された処方箋1枚ずつ,計2枚を持参して来局されました。内科では朝食後の降圧剤が1種類と制酸剤が1種類処方されています。整形外科では毎食後に服用する薬が2種類処方されていました。
「ごめんやけど,内科と整形外科をまとめて一包化してくれへん?」と言われたので,両方の科の医師に一包化指示をもらいました。このように,まとめて一包化した場合に算定要件を満たすとき加算は取れますか?
処方箋受付が1回となり,かつ,それぞれの医師から一包化指示をもらったのであれば,一包化加算を算定できます。
これはよくある話。外来服薬支援料って 何ですか? 算定のポイントは?でも似たようなケースを紹介しましたね。
異なる医療機関から発行された2枚の処方箋を受け付けて,同様にして患者さんからまとめて一包化して欲しい!と言われた場合は外来服薬支援料を算定するというものでした。良かったらリンクを貼りますので記事を読んでみてください☆
あわせて読みたい
外来服薬支援料って 何ですか? 算定のポイントは?
本日のテーマ 外来服薬支援料について解説算定要件について参考資料を明示したうえで,Pointをまとめます算定できるかQ&Aでイメージトレーニング このような流れで...
 けいしゅけ
けいしゅけ
こうやって1つずつ勉強していくことで,色々な処方箋受付・調剤するパターンに対応ができるようになれるわ☆
タコちゅけ,頑張ろなっ!
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
ハイでちゅ!!すっごく楽しいでしゅ!!
[/ふきだし]
Q&A ② 散剤が1剤3種類以上処方されている場合は一包化加算って取れるの?
1剤で3種類の内服用固形剤ならば一包化を算定できるのは理解できました。もしも,散剤が1剤で3種類処方されており,医師の同意を得た場合においては一包化加算を取れるという理解で良いですか?
その通りです。ちなみに日数が少ない場合(7日以下),計量混合加算(45点)として算定する方が一包化加算(32点/7日ごと)を算定するよりも点数が高くなります。その場合は計量混合加算を算定しても良いです。
ただし,同時算定は不可能ですので注意してください。
 けいしゅけ
けいしゅけ
ここは大事やから,超重要補足をしておくわ☆
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ
ハイでちゅ。
[/ふきだし]
一包化加算を算定した「剤」の部分では自家製剤加算や,計量混合調剤加算を同時算定できない。
これ,メッチャ大事やのでしっかりと理解して下さいな☆
一包化加算と共に,自家製剤加算も計量混合加算もとれるようにみえる処方ってあるねん。処方例を書いていくで☆
例)
RP.01 1 日3回 毎食後 21日分
RP.02 1 日1回 朝食後 21日分(自家製剤加算または計量混合加算を算定可能と仮定)
*RP.01と02で一包化加算が算定可能
RP.03 1 日3回 毎食前 21日分
RP.04 1 日1回 朝食前 21日分(自家製剤加算または計量混合加算を算定可能と仮定)
*RP.03と04で一包化加算が算定可能
- RP.01とRP.02で一包化加算を算定する場合 ➡ RP.04で自家製剤加算または計量混合加算を算定する。内服薬調剤料はRP.1~3で算定する。
- RP.03とRP.04の服用時点が異なるの場合 ➡RP.02で自家製剤加算または計量混合加算を算定する。内服薬調剤料はRP.1・3・4で算定する。
Q&A③ 一包化加算と計量混合加算 / 自家製剤加算が同時算定できる場合ってあるの?
一包化加算と計量混合加算 / 自家製剤加算が同時算定できる場合があるなら教えてください。
以下に処方例を示しますので,ご参照ください。
例)次のような処方の場合です。それではもう一度確認していきましょう。
RP.01 1 日3回 毎食後 21日分
RP.02 1 日1回 朝食後 21日分(自家製剤加算または計量混合加算を算定可能と仮定)
*RP.01と02で一包化加算が算定可能
RP.03 1 日3回 毎食前 21日分
RP.04 1 日1回 朝食前 21日分(自家製剤加算または計量混合加算を算定可能と仮定)
*RP.03と04で一包化加算が算定可能
- RP.01とRP.02で一包化加算を算定する場合 ➡ RP.04で自家製剤加算または計量混合加算を算定する。内服薬調剤料はRP.1~3で算定する。
- RP.03とRP.04の服用時点が異なるの場合 ➡RP.02で自家製剤加算または計量混合加算を算定する。内服薬調剤料はRP.1・3・4で算定する。
 タコちゅけ
タコちゅけ
よくわかりました!ありがとうございましゅ!!
[/ふきだし]
 けいしゅけ
けいしゅけ
どういたしまして☆お役に立てて何よりです🎵
[/ふきだし]
Q&A④ 一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は同時算定できるの?
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は同時算定できますか?
出来ません。平成22年の厚労省疑義解釈で明確にされているので以下に示します。
(問3) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては,一包化加算は算定できないとされているが,以下のような服用時点の重複のない2つの処方について,処方せんの指示により,嚥下困難者のために錠剤を粉砕し,服用時点ごとに一包化した場合,処方1で一包化加算,処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠,E錠,F錠 1日1回就寝前 × 14日分
(答) 算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は,いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし,当該技術全体を評価したものであり,処方せん受付1回につき1回の算定としている。
したがって,2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず,1枚の処方せんについて,一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
平成22年4月30日 疑義解釈資料の送付について(その3) より引用
これすごく重要やで,タコちゅけ。
これからますます高齢化社会になるんやから,嚥下困難者が増えるのは予見できるもの。覚えておいてな🎵
 タコちゅけ
タコちゅけ
わかりましたでしゅ!!
[/ふきだし]
Q&A⑤ 飲み誤り防止や心身の理由により服用が難しいという理由以外で一包化するのは,一包化加算の算定対象にならないってホンマでっか?
「こんなにたくさんの種類の薬が出てたら,いちいち薬を取り出すのが面倒やから一包化してくれへん?」患者さんからの要望があり,医師に了解を得て一包化しました。加算を取っても良いですよね?
算定できません。初歩的かつ根本的な一包化加算の要件を満たしていません。如何に理由を示します。
③ 一包化は,多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ,飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし,治療上の必要性が認められる場合に,医師の了解を得た上で行うものである。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
平成30年3月5日 保医発0305第1号 別添3(調剤点数表)PDF [329KB]より 引用
 タコちゅけ
タコちゅけ
あぶないあぶない!
危うく算定しちゃうところでした。そっかぁ,「飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし,治療上の必要性が認められる場合」これがポイントなんでしゅね!
[/ふきだし]
うん。
せやから,「”服薬管理を容易にするため”は治療上の必要性に当たらない」ってことになるねん。つまり一包化加算の算定要件は満たさへん。一包化加算を算定したらアカンねん。
ココが大事なポイントで,ややこしい点やな。
ただ実際問題としては,「面倒だ」とか「飲みやすくするために」って理由だけではなくって,「飲み間違える可能性が高いから」という理由があると思うねん。「飲み忘れることはありますか?」っていうような問いかけをすると良いかも知れへんよ☆
 タコちゅけ
タコちゅけ
そっかぁ,患者さんの『コトバ』の表現1つだけで判断しちゃいけないんでちゅね。勉強になりましゅ!
[/ふきだし]
特におっちゃんとかは言葉足らずな人がいらっしゃるからね。「飲み忘れる,なんて格好悪くて言えねぇし,めんどくさいから,ってことにしとくか!」みたいな人もいるかもしれへんわ。
このように,このQ&Aを読んで直ちに,面倒だから1包化して欲しい➡算定不可!と早合点しないように注意しましょう。
Q&A⑥ 一包化加算のレセプト摘要欄への記載について注意点は?
一包化加算のレセプト摘要欄への記載について注意点はありますか?
以下にお示しします。
イ 「加算料」欄について
(ア) 嚥下困難者用製剤加算,一包化加算,麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算,時間外加算,休日加算,深夜加算,時間外加算の特例,自家製剤加算,計量混合調剤加算,予製剤加算又は無菌製剤処理加算を算定した場合は,当該名称を記載して加算点数(無菌製剤処理加算においては加算点数に日数を乗じた点数)の合計点数(ただし,医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。
また,一包化加算の算定対象となる剤が複数ある場合は,同加算を算定する点数に対応する投薬日数が分かるように,原則として,当該日数が「調剤数量」欄に記載されている剤の欄に(当該日数の剤が複数ある場合は,いずれかの1欄にのみ),一包化加算に係る点数(ただし,医師の指示による分割調剤にあっては「0」)を記載すること。
ただし,同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され,受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については,同一調剤であっても,それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが,これに該当する場合で
あっても,これらの加算はどちらか1欄にのみ記載すること。
(イ) 一包化加算については,上記(ア)のほか,当該加算の算定対象となる剤が複数ある場合は,一包化を行った全ての剤の「加算料」欄に名称を記載すること。
(ウ) 調剤基本料に対応する加算点数,夜間・休日等加算及び在宅患者調剤加算に係る点数については本欄には記載しないこと。
(エ) 電子計算機の場合は,麻 等の□を省略して記載しても差し支えないこと。以下,麻 等の略号を使用する場合について同様であること。
(オ) 1行で記載できない場合は,同欄において行を改めて記載しても差し支えないこと。
保 医 発 0 3 2 6 第 5 号 平 成 3 0 年 3 月 2 6 日 「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
医・歯・調 – 88 より引用 (強調は筆者による)
一包化加算に関する過去の疑義解釈
本文でほぼカバーできているとは思いますが,厚労省が過去に発表した一包化加算に関する疑義解釈を引用してここに記載しておこうと思います。
別包の必要がある一包化,算定できる? 平成26年 診療報酬改定の疑義解釈資料 より
(問1)処方された薬剤を一包化する際に,吸湿性が強い等の理由で直接の被包(PTPシート)から取り出すことができない薬剤をPTPシートで交付するなど一包化とは別にした場合であっても,その薬剤を除いて一包化した部分が算定要件を満たしていれば一包化加算を算定できるか。[/box]
(答)算定して差し支えない。この場合,一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。
(問2)一包化加算の算定に当たっては,同一銘柄の同一剤形で規格のみが異なる薬剤が同時に調剤された場合(例えば0.5mg錠と1mg錠)は1種類として取り扱うことでよいか。[/box]
(答)貴見のとおり。
平成27年2月3日 疑義解釈資料の送付について(その12)より引用
一包化加算に係らない別剤の自家製剤加算や計量混合加算,算定できる? 平成22年 診療報酬改定の疑義解釈資料 より
((問2) 一包化加算を算定した場合においては,自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが,一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば,以下の処方において,処方1又は処方2で一包化加算,処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠,B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠,D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散,F散 1日1回就寝前 × 14日分[/box]
(答) 算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は,原則として1調剤行為に対して算定することとしている。
質問の例においては,処方1と処方2で一包化加算の算定要件を満たしており,処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが,処方3は,一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のいずれとも服用時点の重複がなく,一包化加算の算定対象とならないことから,処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。
(問3) 嚥下困難者用製剤加算を算定した場合においては,一包化加算は算定できないとされているが,以下のような服用時点の重複のない2つの処方について,処方せんの指示により,嚥下困難者のために錠剤を粉砕し,服用時点ごとに一包化した場合,処方1で一包化加算,処方2で嚥下困難者用製剤加算を算定することは可能か。
処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠,E錠,F錠 1日1回就寝前 × 14日分[/box]
(答) 算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は,いずれも原則として処方せん中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし,当該技術全体を評価したものであり,処方せん受付1回につき1回の算定としている。
したがって,2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず,1枚の処方せんについて,一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
平成22年4月30日 疑義解釈資料の送付について(その3)より引用
一包化加算と内服薬調剤料の算定について 平成20年 診療報酬改定の疑義解釈資料 より
(問2)一包化薬については,従来の要件(2剤以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合)に加えて,1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化薬として調剤した場合にも算定できることとされたが,以下の例においては,どのように調剤料を算定することになるのか。
なお,いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。
例1)
処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠 1日1回朝食前 × 14日分
処方3 E錠 1日1回就寝前 × 14日分
例2)
処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠,E散 1日2回朝夕食後 × 14日分
例3)
処方1 A錠,B錠,C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠,E散,F散 1日1回朝食前 × 14日分
処方3 G散 1日1回就寝前 × 14日分[/box]
(答) 例1においては,処方1が1剤で一包化薬の要件を満たしており,かつ,処方2と処方3は,処方1とは服用時点が重複していないことから,処方1について一包化薬調剤料を算定する。
また,一包化薬については内服薬に準じて剤数に含めることとされており,内服薬は3剤まで算定可能であることから,以下のとおり,処方1に係る一包化薬調剤料と別に,処方2及び処方3について内服薬調剤料を算定することができる。
処方1 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方2 内服薬調剤料 63点(14日分)
処方3 内服薬調剤料 63点(14日分)
例2においては,処方1のみで一包化薬の要件を満たすものの,処方2と服用時点が重複しており,処方1と処方2の全体で一包化薬の要件を満たすと考えるべきであることから,以下のとおり,全体として一包化薬を算定し,処方2を別に内服薬として算定することはできない。
処方1 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方2 算定なし
例3においては,処方1(1剤)と処方2(1剤)のいずれも一包化薬の要件を満たしており,かつ,処方1,処方2及び処方3の間で服用時点の重複はないことから, 処方1又は処方2のいずれか一方について一包化薬調剤料を算定する。
また,処方1と処方2はいずれも内服薬の1剤相当であり,内服薬は3剤まで算定可能であることから,以下のとおり,処方1を一包化薬として算定した場合は,処方2及び処方3を内服薬として算定することができる。
同様に,処方2を一包化薬として算定した場合は,処方1及び処方3を内服薬として算定することができる。
(処方1を一包化薬として算定した場合)
処方1 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方2 内服薬調剤料 63点(14日分)
処方3 内服薬調剤料 63点(14日分)
(処方2を一包化薬として算定した場合)
処方1 内服薬調剤料 63点(14日分)
処方2 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方3 内服薬調剤料 63点(14日分)
(問3)受け付けた処方せんに,一包化薬の算定要件である2剤以上の内服薬(以下「要件①」という )に係る処方と1剤で3種類以上の内服薬(以下「要件②」という )に係る処方が記載されており,かつ,これら2つの処方に服用時点の重複がない以下の例においては,どのように 調剤料を算定することになるのか。
なお,いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。
例1)処方1と処方2で要件①を満たし,処方3が要件②を満たす場合
処方1 A錠,B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C散,D散 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E錠,F錠,G散 1日1回就寝前 × 14日分
例2)処方1から3までで要件①を満たし,処方4が要件②を満たす場合
処方1 A錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 B散 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 C錠 1日1回朝食後 × 14日分
処方4 D錠,E錠,F散 1日1回就寝前 × 14日分[/box]
(答) 要件①に係る処方と要件②に係る処方のいずれについて一包化薬調剤料を算定してもよいが,要件①で一包化薬を算定した場合と要件②で一包化薬を算定した場合との間で,別途算定できる内服薬の剤数に差が生じないようにするため,要件②に係る処方について一包化薬調剤料を算定する場合にあっては,要件②に係る処方については,要件①に係る処方と同一の剤数とみなして算定する。
すなわち,例1においては,要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)は内服薬の2剤相当であることから,要件②に係る処方(処方3)も2剤相当として取り扱う。
よって,以下のとおり,要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)で一包化薬を算定した場合には,内服薬の3剤目として処方3について内服薬調剤料を算定することができ,また,要件②に係る処方(処方3)で一包化薬を算定した場合には,内服薬の3剤目として処方1又は処方2について内服薬調剤料を算定することができる。
(要件①に係る処方(処方1と処方2の組合せ)で一包化薬調剤料を算定する場合)
処方1 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方2 算定なし
処方3 内服薬調剤料 63点(14日分)
(要件②に係る処方(処方3)で一包化薬調剤料を算定する場合)
処方1(又は処方2) 内服薬調剤料 63点(14日分)
処方2(又は処方1) 算定なし
処方3 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
また,例2においては,要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)は内服薬の3剤相当であることから,要件②に係る処方(処方4)も3剤相当として取り扱う。
よって,以下のとおり,要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)で一包化薬を算定した場合には,処方4について別に内服薬調剤料を算定することはできず,また,要件②に係る処方( 処方4)で一包化薬を算定した場合には ,処方1から処方3までのいずれについても,別に内服薬調剤料を算定することはできない。
(要件①に係る処方(処方1から処方3までの組合せ)で一包化薬調剤料を算定する場合)
処方1 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
処方2 算定なし
処方3 算定なし
処方4 算定なし
(要件②に係る処方(処方4)で一包化薬調剤料を算定する場合)
処方1 算定なし
処方2 算定なし
処方3 算定なし
処方4 一包化薬調剤料 89点32点×2(14日分)
(問4)処方せんの指示により,1剤で3種類の散剤を計量し,かつ,混合して,服用時点ごとに一包化した場合には,内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定するのか,それとも,一包化薬調剤料を算定することになるのか。[/box]
(答) 処方せんの指示の具体的内容及び患者の状態(治療上,一包化が必要か否か)にもよるが,基本的には,1剤で3種類の散剤を計量し,かつ,混合して,服用時点ごとに一包化した場合には,内服薬調剤料と計量混合調剤加算の合計により算定する。
ただし,患者の状態が一包化薬の算定要件を満たしており,かつ,処方せんにおける一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には,一包化薬調剤料を算定することができる。
(問5)同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合(処方せんの受付回数が1回となる場合)において,個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが,2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には,一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。なお,いずれも処方医による一包化の指示があるものとする。[/box]
(答) 2枚の処方せんの処方内容を併せて一包化薬の算定要件(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)を満たしている場合には,一包化薬調剤料を算定して差し支えない。
(問6)異なる保険医療機関から交付された2枚の処方せんを同時に受け付けた場合において,個々の処方せんに記載された処方だけでは一包化薬の要件を満たさないが,2枚の処方せんの処方内容を併せれば要件を満たすような場合には,一包化薬調剤料を算定しても差し支えないか。[/box]
(答) 一包化薬調剤料は処方せんの受付1回につき1回のみ算定するものであり,質問の事例においては,別々の処方せん受付(受付回数が2回)となることから,一包化薬調剤料は算定できない。
平成20年度診療報酬改定に係る通知等について
疑義解釈資料の送付について(その2)別添3より引用(一包化加算の点数に関してはH30の点数に合わせて筆者が改変)
一包化加算の算定要件・計算方法まとめ
もう一度,処方例をみながらまとめます。以下の6点が大事なポイントや。
一包化加算6つのポイント
- 処方2の朝食後「1剤」で3種類以上の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- 処方1と処方4において,異なる用法=「2剤」で内服薬調剤料を算定できる処方の,昼食後2種類の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- 処方3と処方4において,異なる用法=「2剤」で内服薬調剤料を算定できる処方の,夕食後2種類の薬を一包にまとめた場合,一包化加算が算定できる。
- ①~③のどの条件でも算定要件を満たすので,処方1~4が処方されている処方箋の場合は,どれかの要件を理由に一包化を算定することができる。
- 内服薬固形剤であればいいので,散剤が混じっても,散剤だけ*であったとしても一包化加算は算定が可能である。
*散剤だけの場合は計量混合加算との点数で高い方を算定する。同時算定は不可能。
- ちなみに,上記の処方1~4の場合,一包化加算を算定可能であり,寝る前は1種類だけである。この場合は薬をシートから取り出さず(分包せず)に患者さんにお渡しした場合でも服用に差支えがない旨,患者さんに確認ができていれば一包化加算の算定に問題は生じない。
次に,算定できる点数の計算方法を説明したで。
一包化加算の点数
- 42日分以下の場合 32点/7日分
- 43日分以上の場合 220点
これらの一包化加算の算定要件や,6つのQ&Aから得た知識を使って普段の業務に臨んでください☆
きっと一包化加算をマスターできるはずやで!応援しています☆
一包化の点数は理解できた!けど,知りたいのは料金やねんけど?
こういう問い合わせもあろうかと思います。なので,別の記事を作りました。
一包化のかかる料金はいくら?|自費の場合と保険適用時の料金の違いは?
この記事に,一包化でかかる料金の一覧表を載せていますので,良かったら見てみてください☆
[kjk_temp id=”5491″]
[kjk_temp id=”5491″]

この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!










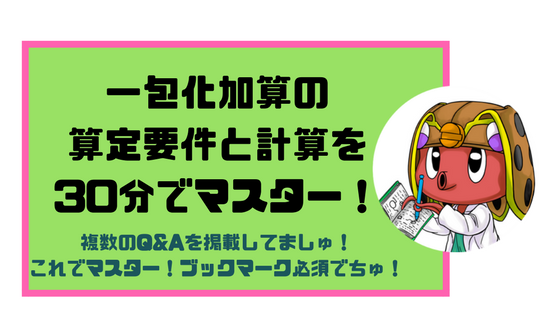









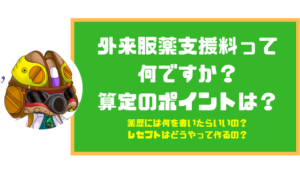


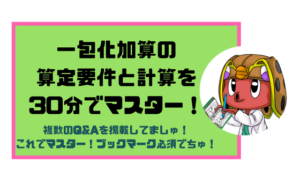
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (2件)
度々、分からない事があると拝見させて頂いています。
分かりやすくとても助かっています。
初歩的な事でお恥ずかしいのですが、質問するです。
一包化加算についてですが、
A錠 1錠
B錠 1錠
朝食後 ○日分
C錠 1錠
D錠 1錠
就寝前 ○日分
この処方は一包化加算算定できますか?
2剤と認識して良いのですか?
お手数おかけしますがら返答お待ちしております。
マンゴー様
コメントいただき有難うございます。
頂いた処方内容であれば、一包化加算は取ることができないんです。
理由として、
A錠 1錠
B錠 1錠
朝食後 ○日分 は、「朝食後」という”1剤”あたり2種類の一包化となっているので、
【1剤で3種類以上の薬を分包する】という要件を満たしません。
C錠 1錠
D錠 1錠
就寝前 ○日分 も「就寝前」という”1剤”あたり2種類の一包化となっているので、
【1剤で3種類以上の薬を分包する】という要件を満たしません。
よって、いずれも算定要件を満たさないので加算を取ることができないんです。
例として頂いた処方で、仮にAという薬が用法として「朝・夕食後」で出ていたとすると、
朝食後に薬をまとめるのは「朝・夕食後」という1剤であるAと「朝食後」という1剤であるBを分包することになります。
これならば、【2剤以上の薬を(ある服用時点で)分包する】ということになり、一包化加算が取れるという感じです。
ここがちょっとややこしいですが、説明としていけてますでしょうか??