調剤報酬点数表を作ったで!【2018.4~2020.3保存版】を公開してから情報収集をしています。
調剤基本料1届出薬局の場合,これまでの基準調剤加算の施設基準に加えて,当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制を整備され,一定の実績を有していることっていう条件が書き加えられています。
当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制を整備され,一定の実績を有している事
って具体的に何をしたらいいの??
当該保険薬局以外の医療従事者等に対し,医薬品に係る医療安全に資する情報の共有を行うにつき必要な体制を整備って何でしょうか?取り組みの実績って何が求められますか?
・前年1年間(1月1日~12月31日)に,疑義照会により処方変更がなされた結果,患者の健康被害や医師の意図した薬効が得られないことを防止するに至った事例を提供した実績を有し,薬局機能情報提供制度において「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としている(2019年4月以降適用)
・副作用報告に係る手順書を作成し,報告を実施する体制を有している(2018年10月以降適用)
 けいしゅけ
けいしゅけ明記されたのは2つやで☆
① 「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」を「有」としている(2019年4月以降適用)こと
② 副作用報告に係る手順書を作成し,報告を実施する体制を有している(2018年10月以降適用)こと
ほな,プレアボイドって何ですか?手順書ってどうやって作るんですか?ということを書いていこう。
プレアボイドって何ですか?



プレアボイド??
タコちゅけ同様,プレアボイドってなんだろう?という方もいらっしゃるかもしれません。
プレアボイドの定義・目的
「プレアボイド」は,Prevent and avoid the adverse drug reaction(薬による有害事象を防止・回避する)という言葉を基にした造語である。
プレアボイドは,日本病院薬剤師会(以下,日病薬)が提唱し収集している薬学的患者ケアの実践であり,実践結果に基づく成果報告の呼称です。
医療現場に勤務する薬剤師は,医薬品の供給管理,内服・外用・注射剤の調剤はもとより,病棟をはじめ院内全域で医薬品の適正使用に貢献することを求められています。
プレアボイドは,薬剤師職能のなかでも“Pharmaceutical Care”に着目したものです。
医療現場に勤務する薬剤師は,服薬指導,治療モニタリング,副作用モニタリング,薬歴管理,薬物血中濃度管理などの薬学的患者ケア(表1)を通じて,有効で安全な薬物療法の推進の一翼を担っています。
その結果として,副作用によるリスク回避,患者QOLの改善といった具体的な成果が得られています。
これを各ご施設で,職能団体として見える形にすることが報告制度の目的の1つです。
表1. 薬学的患者ケアのためのチェックリスト
- 適応外使用
- 未治療な病態
- ガイドラインからの解離
- 薬物動態のモニタリング
- 治療と反応の解離
- 不適切な治療期間
- 不適切な投与経路
- 薬物有害作用
- 薬物相互作用
- 薬物アレルギー
- 投与禁忌
- 重複する治療
- 過剰費用となる治療
- 必要な患者教育
- 必要なカウンセリング
- 治療意義の理解と参加
- 不適切な自己治療
- 過量使用
- 薬物乱用
プレアボイド報告の3つの様式
プレアボイドの報告には大きく分けて3つの様式があります。
- 副作用回避報告
- 未然回避報告
- 薬物治療効果の向上
[/list]
①副作用回避報告
既に患者さんに副作用が起こってしまっている可能性が高く,それを薬剤師が発見し悪化することを防いだという報告のことです。
患者さんの自覚症状の悪化だけではなく,他覚的に見える症状や検査値異常も含めて,薬剤師が病棟や外来でそれらを発見して医師に薬剤の中止や減量を提案する事例があてはまります。
②未然回避報告
現在行われている薬物療法について相互作用や過量投与,禁忌疾患への処方など,副作用が起こる可能性が高いものを薬剤師が発見し,副作用の発現を防いだという報告のことです。
それって疑義照会=プレアボイドになるということですか?
違います。日本病院薬剤師会(以下;日病薬)では処方箋に記載されている処方薬情報のみから発生する疑義照会は薬剤師の責務と判断しており,この場合における疑義照会はプレアボイドとしていません。
他方で,薬剤師が薬歴やカルテ,患者症状や会話を発端として行った疑義照会はプレアボイドとしています。



処方せん情報のみからの疑義照会はプレアボイドにならない。
処方せん情報に,薬歴やカルテ,患者さんの症状や会話から得られた情報が加わって行った疑義照会はプレアボイドになるっちゅうことやね。
③薬物治療効果の向上
副作用の悪化の防止や副作用の回避には該当しないもので,薬剤師の処方提案によって治療効果が向上したという報告のことです。
それはなぜプレアボイドにあたるのですか?
本来患者さんが受ける最適な治療を受けられていない「患者不利益」を回避したと判断し,プレアボイドの概念に含まれています。
副作用報告に係る手順書ってどんなものですか?どう作るのですか?
これに関しては,僕も「なにそれ?どうすんねん?」と思ったので,日本薬剤師会のHPを見てみました。
すると以下のような記載を発見しました。
日薬において,手順書作成のための資料として,「医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子」※を踏まえた薬局における副作用報告への取組みに関する資料を作成中。3~4 月頃を目途に公表予定。
日本薬剤師会HPより http://www.nichiyaku.or.jp/wp-content/uploads/2018/03/sochi0315.pdf (強調は筆者による)



なるほど。これから日本薬剤師会も対応していくのか。
つまり現状は,副作用報告に係る手順書のフォーマット(=ひな形)は存在しないわけだ。
日本薬剤師会が作ったひな形を使って,調剤薬局各社は副作用報告に係る手順書を作成していく流れになりそうやね。
医薬関係者の副作用報告ガイダンス骨子って何ですか?
平成30年度診療報酬改定では以下の3つが紹介されています。
【速やかに報告する副作用】
- 死亡,障害及びそれらにつながるおそれのある症例等について,重篤度分類基準を参考として,重篤なもの(グレード3)を15~30日を目途に当局に報告
【医療機関の対応について】
- 医療機関内での診療科間,診療科と薬剤部門間における情報共有,連携。連携方法のあらかじめの共有
- 副作用が疑われる症例に関する情報の医療機関内での集約・一元化。管理者を定め,情報の恒常的な把握
【薬局の対応について】
- 処方した医療機関への受診勧奨によるフィードバック。患者の副作用,検査値等の情報共有
- 情報共有の結果,薬局から副作用報告を行うこととした場合,提出に際し,処方した医療機関は連名として記入する
その他の医薬品に係る医療安全に資する情報の共有としてできること
① ヒアリハット事例報告
JCQHC(公益財団法人日本医療機能評価機構)に薬局からヒヤリ・ハット事例を報告する。報告されたヒヤリ・ハット事例は分析され,共有化されるシステムになっている。参加している薬局の一覧も確認できる。
JCQHC ; Japan Council for Quality Health Care
② 副作用報告
PMDAへ副作用事例を報告する。
プレアボイド&副作用報告は難しいことではないと思う
ここまでいろいろと書き連ねてきました。
調べながら書いて思うのが,意外と難しいことではないのではないか?ということでした。



プレアボイドにしても,副作用報告に係る手順書を作成して報告を実施する体制を整えるってなんかムズそうに思たけど,
疑義照会などいろいろな手段があるものの,患者さんの為に僕たちがいつもやってることやん。それを「報告するだけ」やん。



患者さんの為に僕たちがやっていることを報告することによって,薬剤師の活躍の実績が見えるようにする仕組みと考えたらいいのかも。なんて思ったでしゅ!
[/ふきだし]









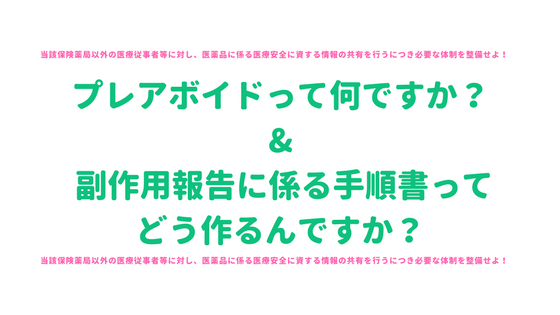


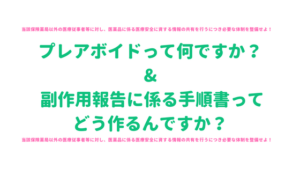
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (1件)
難しい言葉の話で困ってましたが明快な解説で本当にアリガトウございました これからもよろしくお願いします