【医療統計学の用語をマスターや!】医療論文や薬のパンフレットを読めるようになる為の記事をまとめたで!
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
これまでいくつかの論文読解に対するヒントとなるような記事を書いてきました。
すこし記事の数もまとまってきたのでまとめページを作ってみましたで🎵
良かったら各ページの記事を参考にしてみてください☆
医療系論文や薬のパンフレット,インタビューフォームに書かれた統計用語が理解できるか!?
薬剤師として仕事をしていく中で,この問いに対して,
「統計用語?p値とか有意差,NNTとかRRRとかARR,ハザード比・オッズ比・リスク比,peco・・・その他もろもろの事かね?フツーに分かるで!!」
そう言い切れる方は少ないと思う。
いや,正直言うて,僕の周りではほとんどいないわ。悲しいことに。
しかしTwitterなんかやってると,スゴイね,このあたりを当たり前にわかっていて論文を発表している薬剤師の先生もフツーにいらっしゃる。
そやから,医療統計学に関する知識を色々と記事にしていこう!!!そう思ったのがキッカケになりこれまで複数の記事を書いてきました。
実際問題として,こういった統計用語と言うのはわかりにくいものやわ。とっつきにくいものでもある。それをいかにカンタンに,わかりやすく書くか?それをメッチャ気にしながら記事にしてきたつもりです。
実は国家試験の勉強のときには一通りやってるんやで?にもかかわらず,実際に現場に入って数年働くとほっとんど忘れてるねん。
何を隠そう,僕が忘れている薬剤師の一人でした(笑)
けどね,これら統計用語が読めないと添付文書やインタビューフォーム,勉強会を開いたときや新薬のパンフレットなんかをMRさんが持ってきてくれた時に内容を正しくキャッチできない人になってしまうねん。
それって,薬剤師としてイケてへんわ!自分に対してムカついてきたのも記事を書くキッカケになったのでした。
医者よりも薬に関してはわかります!それくらい勉強しなきゃアカンと思うねん薬剤師は。
だって薬のプロなんだから。それが仕事で,それで生計を立てて生きていくんだもの!
そういった考えから作ってきた記事たちを紹介するのがこのページと言うわけです。
1日1ページずつでいいから読んでみて,論文でその用語についてわかるか確認してください!
さぁ,はじめていきましょう。
まず,手始めに読むのをおススメしたい記事を紹介します。
「有意差」「p<0.05」薬の臨床試験の結果で見る統計学用語の意味は?
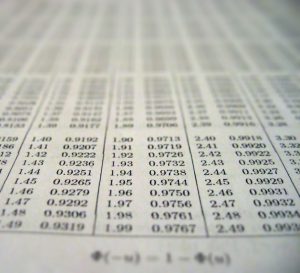
この記事を書いた理由
ある薬がほかの薬やプラセボなどよりも,「より効果が高い」とか,「より安全性が高い」(もしくはその逆でもいい)といった事を証明するには統計学的に,きちんと『差』が付いているという事を証明する必要があるのは理解できますよね?
そらそうやんな?
「なんとなく,Aという薬よりBという薬の方が頭痛に効く気がする。」ので販売を開始します!なんていうて薬が販売になってたらアカンやろ?
てか,アカンよ!
「従来のAという薬を飲んだ人100人と,新薬のBという薬を飲んだ人100人を集めた時に,偶然ではなく間違いなくBの薬の方が効くことが統計学的に証明された」
こんな風に,「なんとなく」が排除されなければいけないねん。
それを示す指標こそ,p値や有意差といった言葉やのよ。これがわからないなら,薬剤師ではなく,ただの物知りな人になってまう。
そんな物知り素人になり下がらないためにも,ぜひ読んでいただきたい!そう思って書きました。
これが読めたら次におススメなのが,
臨床試験の結果に出てくるハザード比や95%信頼区間の意味って何?

この記事を書いた理由
これも「有意差」「p<0.05」薬の臨床試験の結果で見る統計学用語の意味は?という記事と同じ理由で書いたものなんです。実はこの2つの記事はセット読みするのが最も効率がいい。なぜなら,95%信頼区間と言うのは・・・という理由があるからなんです!
気になる?
本文・・・読んでください(笑)
読んだらわかるねんけど,これら2つの記事の内容が理解できてこそ,確実に有意差がある!と読み取れるようになるんです。
たった2つの記事だけですが,ほとんどのお薬のパンフレットには出てくる用語なので,理解できると知識が格段に頭に入ってくるようになります!
いやぁ,勉強って,本当にすばらしいですねぇっ!!!!!
そう叫んでほしいものです。
さて,それでは次のオススメ記事に参ります。
オッズ比が論文や薬のパンフレットの臨床試験結果に使われる理由

この記事を書いた理由
ハザード比と共にしょっちゅう出てくるオッズ比という言葉を攻略したくなったから。
これが個人的な理由で,皆さんに情報提供したい人間としては,順番的にこれが理解しやすいと思うからですわ。
ハザード比と何が違うの?とか考えながら読んでください。するとセットでオススメしたい記事も出てきます。
治療効果指標:相対危険度減少率(RRR)・絶対危険度減少率(ARR)・必要治療数(NNT)とは

もはや統計学の用語の連発になってきますが,先ほどのオッズ比が論文や薬のパンフレットの臨床試験結果に使われる理由という記事の続きとして描いた記事なんです。
これらがわかってしまえば,ぶっちゃけほぼ用語は網羅できてます。
あとは,論文をガンガン読んでいきましょうよ。きっと今までは「あんまよくわかんないからいいや」ってスルーしていた数値や用語が,
これメッチャ大事やんけ!!!!
って思えるようになっちゃいますよ☆
ここまできたら,あとは論文の読み方というか,まとめ方というか。あらすじの立て方や要点を捉えるための言葉,PECOを覚えましょう。
論文のPECOとは?何の略で,どう使うのか?

この記事を書いた理由
PECOを立てられるようになると,臨床で出会う疑問を形式化し,整理して考えることができます。
もちろん,論文の内容をPECO立てすることで理解もしやすくなります。
・・・と本には書いていますが,PECOってなんですか?と思ったので調べたことを記事にしました。
真のアウトカムと代用のアウトカムの違いって何ですか?
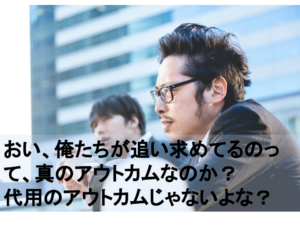
この記事を書いた理由
せっかく読んだ論文の結論が代用のアウトカムでは意味がない。真のアウトカムでなくっちゃ!
・・・いや,ちょっと何言ってるかわかんないです。そんな感じやった僕でしたが,調べて記事にしたので読んでみてください。
ITT( Intention to treat )解析って何ですか?
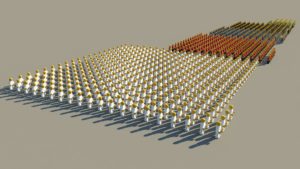
この記事を書いた理由
論文がなんとなく読めるかも!と思ったんですが,「ITT解析をした」ってやたらと書かれてるんですよね。
Intention to treatですよ!
・・・いや,ちょっと何言ってるかわかんないです。そんな感じやったので,調べて記事にしました。
ちょっと試しに,読み終わった後に,
PECOを使って論文を読み解く~PPIの継続服用で認知症発症リスク1.4倍~ この記事を読んでみてよ!

いやぁ,勉強って,本当にすばらしいですねぇっ!!!!!
こう言ってしまうでしょう。いや,言うて!!
さぁ,このカテゴリーの記事を読み進めたアナタは確実にレベルアップしてるはずや!!
どうですか?
全部読んでみましたか?
読んでみたら,けっこう食わず嫌いだった自分に気が付くんとちゃう?
もうこれからは違いますよね?
ガンガン論文もパンフレットも読んでいけますよ!
ちなみに,この本に大事なことは全部書いてます↓
是非とも論文を読んでみて欲しい
読んでみましたか?
なんやかんやで,めっちゃ読める気がしませんか?
これ,僕も自分で勉強した後に書いた記事なので,出てくる用語は全部わかってしまいました。
まぁ~気持ちのいいことよ!
アナタにもこの楽しさを感じてほしいです!!
[kjk_temp id=”5491″]
- AHEADMAPのWebサイト作成でけいしゅけが意識した事と,入会方法・入会特典の説明やっ!
- 肥満と病気について調べてたら,死亡率の低さで小太りさん最強説が!最も死亡率が低いBMIの数値とは?
- うがい薬で有名なイソジンよりも水道水の方が風邪予防に効果があるという論文があるねん!
- SGLT2阻害薬エンパグリフロジン(ジャディアンス)の論文【EMPA-REG OUTCOME】を復習や!
- 【CANVAS Program】でカナグリフロジン(カナグル)のエビデンスを見たが,SGLT2阻害薬は微妙だと思う
- 【DEVOTE試験】トレシーバ®(インスリン デグルデク)はインスリン グラルギンよりも心血管イベントリスクを下げますか?









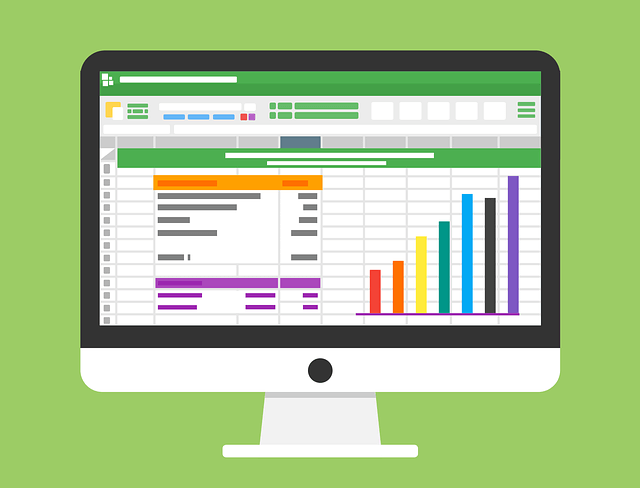


記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (3件)
[…] 【医療統計学の用語をマスターや!】医療論文や薬のパンフレットを読めるようになる為の記事をまとめたで! […]
[…] 【医療統計学の用語をマスターや!】医療論文や薬のパンフレットを読めるようになる為の記事をまとめたで! […]
[…] 【医療統計学の用語をマスターや!】医療論文や薬のパンフレットを読めるようになる為の記事をまとめたで! […]