 けいしゅけ
けいしゅけまいどっ! けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆



新米薬剤師のタコちゅけでちゅ☆
それでは,さっそく進んでいきましょう☆どうぞよろしくお願いいたします。もし,疑問点やご指摘,記事にしてほしい!といったご要望があればコメント欄へ遠慮なく書いてくださいね☆
腎臓の働き
①いらん老廃物を体の外に出す!
もはや基本的すぎるけど,血液をろ過して老廃物(尿素窒素,クレアチニン,尿酸とか)や塩分,余分な水分をオシッコとして体から追い出す。
あとは身体にとって必要な栄養は再吸収して体に戻しているんよ。
ちなみに薬の成分も不要なものとして出ていく経路になっている(水溶性の高い薬や脂溶性が高くともグルクロン酸抱合作用などで水溶性が増した後の場合)。
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
老廃物や毒素が外に出ないから尿毒症になる。水分が出せないから体がむくむ。
尿中に出るはずの薬の成分が出なくなる⇒作用が増強される。副作用が出やすくなったり増強する!
②血圧を調整する
腎臓はARB阻害薬でお馴染みのレニンというホルモンを分泌することができるねん。このレニンが血中のタンパク質と反応してアンジオテンシンⅡになって血管収縮を引き起こすことで血圧は上がる訳や。ここは薬理学やね。完全に。
血圧が下がるとスイッチオン。血圧を上げてくれる。恒常性を保ってくれているわけやね。
あとは,塩分の排泄調整も腎臓がするのでこれによっても血圧が調整される。
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
もちろん,この機構が壊れるので血圧はめっちゃくちゃ上がるようになってしまう。
塩分が溜まることで水分貯留が起こって血圧上昇。
レニン-アンジオテンシン系の恒常性の破たんによる血圧上昇などが起こる。
③糖新生をする
実はこれ,めちゃ大事です。
腎臓の糖新生とその特異性 – J-Stageという論文があるんよ。
それによると,肝臓がほぼ全て糖新生を行って血糖値を上げるコントロールをしていると思いきや,実は腎臓が20%~30%くらいは腎臓が糖新生を行っているという結果を示しているねん!
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
つまり,腎臓は血糖値が下がった時には血糖値を上げるように働いてくれているわけやから,その機能が落ちれば血糖値を上げる能力が落ちるようになる。
だから,腎不全患者さんや透析患者さんはインシュリン注射や血糖低下薬を飲ませると効果が出過ぎて低血糖を起こしやすくなるのよ。これは腎機能が落ちた患者さんに低血糖リスクの説明をしっかりとするべきかどうかの線引きに使える知識やから覚えておくといいよ。
④血液を弱アルカリ性に保つ
ヒトの血液のpHは大体7.4に保たれている。これは腎臓が重炭酸を作ることで酸性物質が体に入ってきたときに中和していることによるねん。
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
そやから,腎臓がへたると,血液が酸性に傾きやすくなる。アシドーシスやね。
そやから透析患者さんに重曹錠が出るわけさ。
人工的に腎臓の役目を果たさせているって事やね。
⑤骨を丈夫にする⇒ビタミンD3の活性化
小見出しの通りでございます。もはやひねりがありません。
ビタミンD3を活性化させることで骨を強く保っておます。
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
骨が弱りおす。
⑥造血作用
エリスロポエチンを分泌して骨髄に造血しやがれ!と指令を出すことができる。
これも腎臓の働きや。
腎臓の機能が落ちるとどうなる??
もちろん,貧血傾向になる。
ちなみに透析患者さんにはシナールがよく処方されるんやけど,この理由はね,ビタミンCが鉄分を組織に貯蔵されている状態から引きはがす作用があって,これによって貧血を改善する作用が知られているからなんやで?
まとめ
以上で腎臓についての説明はおしまい。これで腎機能が低下した患者さんの処方の傾向がわかるようになるよ。
これらでわかることは以下の通りやんね?
降圧薬が出やすくなる。
腎排泄じゃないタイプがメインね。
ビタミンD製剤が出やすくなる
骨が弱るから。
利尿剤が出る
オシッコが出ないから。
尿酸値を下げる薬が出やすくなる
フェブリク万歳
ビタミンC製剤(シナール)が出やすくなる
貧血傾向やから。
血糖降下薬は減量傾向
低血糖リスク増大による。特にインシュリン製剤はインシュリンの代謝自体が腎臓で行われるのでそれができなくなるんやから単位数の減量か処方中止になるわ。
Q.962 腎不全期になるとインスリンの分解が遅くなり,インスリンの必要量が低下するといいますがどのような原理なのか詳しく知りたいです。インスリンの分解はどのようにして行われているのでしょうか?(26歳,女性)
http://www.dm-net.co.jp/qa1000_2/2006/05/q96226.htmlより
A.
膵臓から分泌されたインスリンは,まず肝臓に取り込まれそこで分解を受けるものと,血液中に循環するものに分かれます。血液中に循環するインスリンは,ブドウ糖を筋肉や脂肪の細胞に取り込みます。そして最終的には腎臓の糸球体で分解され,尿中に排泄されていきます。腎不全は糸球体の機能が極めて低くなった状態ですから,インスリンの分解も滞ってくる結果,血液を循環しているインスリンの濃度が低くなりにくくなります。
また,注射などの方法で体外からインスリンを補給している場合は,肝臓で取り込まれる経路を経ないで大半が直接,血液中に循環します。そのため腎臓に到達するインスリンが相対的に多くなりますから,分解されるインスリン量が少ないことの影響が大きくなり,注射の必要量が減ってきます。
⇒肝代謝型のDPP-4阻害薬が処方されやすくなる印象がある。
どう?ここらへんで終えるけれど,かなり腎臓をちょっと勉強するだけで処方箋から情報を拾いやすくなるのがわかるでしょ?
同時に,処方箋に載っている薬が腎排泄か肝代謝型か?がわかってないとお話にならないことも。
いやぁ,面白いね!
書いていて,けいしゅけ,また勉強したくなってきたのでここで終了!
添付文書あつめよっと。
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!










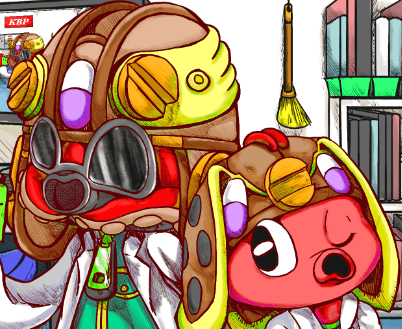


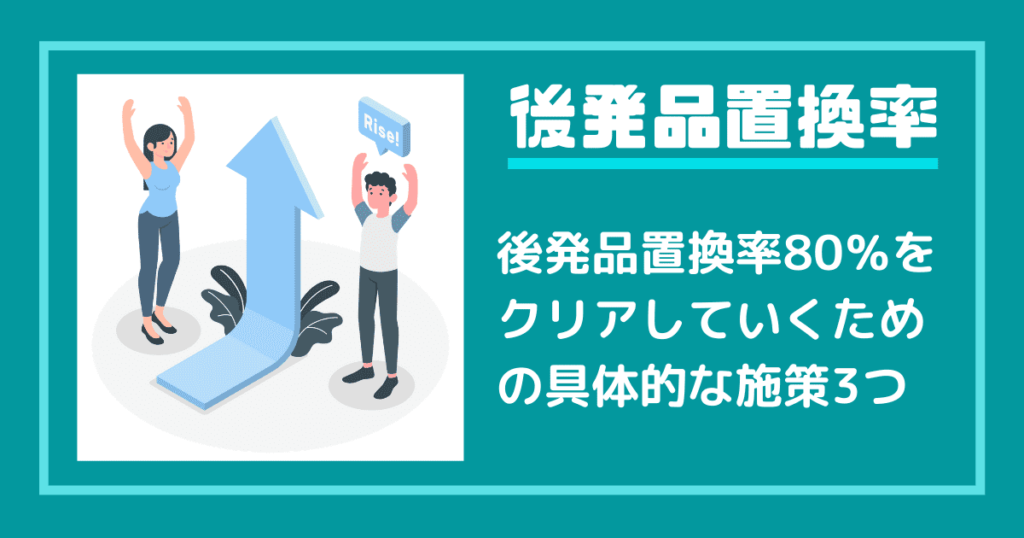
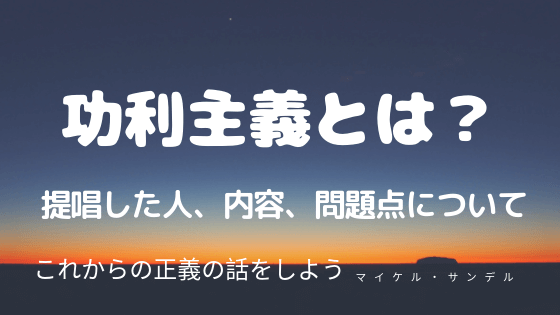
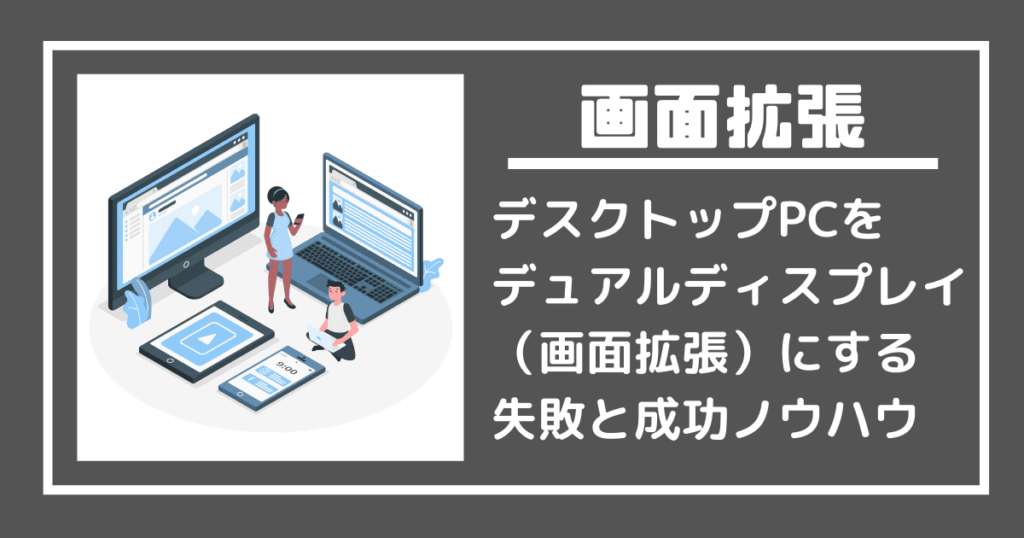


記事の感想など,ひとこと頂けますか?