DAPT療法 ( dual antiplatelet therapy ) って良く聞くけど,いったい何のこと?
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
新人薬剤師が現場で主力に成長するための4つの施策で書いたことをそのまま現場で教えているけいしゅけやねんけど,新人薬剤師ってどれくらい学校で勉強してきたのかな?気になって聞いてみたら
「いや,知らないっす。」
・・・ふむ。(しょうがねぇ,他のスタッフからまずは指導をしてもらう方向で行こうか。)
そう考えて,「ほんじゃ先輩薬剤師に質問や。DAPT療法を誰か教えてやって・・・」
空気を察したのか蜘蛛の子を散らすように他の薬剤師がその場からいなくなった。
「え?みんな知らへんの?」
目を丸くして聞いてみると,
- 「説明するほどわかってへん」
- 「バイアスピリンとプラビックスを一緒に服用するってこと位しかわかりません」
- 「・・・すいません」
そんな返事が返ってきた。
「これはちょっとしっかり目に教えなあかん!」そう感じたので新人さん含めて知ってる範囲で説明をしたので内容を記録として記事にするわ。
ほな,いくで!!
DAPT療法( dual antiplatelet therapy )とPCI( percutaneous coronary intervention )
まず,DAPT療法って何のこと?と,何の薬をどう使う事なのか?それを知らなきゃ話になりませんよね。ここを書いていきます。
定義をはっきりさせよう!
DAPT療法 = 抗血小板薬2剤併用療法 。なにそれ?
経皮的冠動脈形成術( percutaneous coronary intervention : PCI )で留置したステント部分に血栓が生じることによって再び冠動脈が狭窄・閉塞することによる心筋梗塞などの虚血性心疾患を起こさないようにするために,2種類の抗血小板薬を使うことをDAPT療法という。
2種類の抗血小板薬は具体的には
アスピリン(バイアスピリン)+チエノピリジン系抗血小板薬(現在3種類ある。①エフィエント②プラビックス③パナルジンやで!)
となっている。 [/box]
まずは定義的なことをハッキリさせてみた。
ちなみにこのDAPT療法,2剤併用によってステント血栓症のリスクを60~70%下げることから推奨されるようになったんやで!
60~70%もリスクさげるってすごない??
これがよく処方箋で見る,「バイアスピリン+プラビックス」処方の正体。これがDAPT療法やったってわけよ🎵
読んでみると,「そういうことね。」って感じやろ?
PCI( percutaneous coronary intervention )= 経皮的冠動脈形成術 。なにそれ?
経皮的冠動脈形成術( percutaneous coronary intervention : PCI )について補足説明をしなきゃね。これがわかってなかったらDAPT療法も結果的にわかったことにはならんから。
心臓に酸素や栄養を送る冠動脈が動脈硬化やったり血栓ができたりすることで狭くなったり(狭窄するっていうねん),完全にふさがれてしまう(閉塞するっていうで)状態になってしまう。もちろん,命の危機や。
そんなとき,どうやって治療するかと言うと,
- 外科的な処置として冠動脈のバイパス手術をする
- カテーテルっていう管を足の付け根などから入れて,ステントっていうメッシュ状の金属を狭窄・閉塞した動脈部分に留置したりする方法
があんねん。
この,カテーテルを使って狭窄・閉塞した動脈を広げる手術を経皮的冠動脈形成術( percutaneous coronary intervention : PCI )っていうねんで。
 けいしゅけ
けいしゅけ
DAPT療法が必要な理由は? -ステント血栓症は予後不良-
ここまでで,DAPT療法とは?と,PCIとは?について説明してきました。
ステント血栓症について触れておくことで,DAPT療法がいかに重要であるかを触れておきたい。
ステント血栓症って何やの?
これはね,詰まった血管を広げる目的で血管の中に置いてきたステントっていうメッシュ状の金属部分に血栓が生じてしまって冠動脈が再び詰まってしまう状態を引き起こしてしまう現象を指すねん。
ステント血栓症は言葉でいうと,「ふーん。また広げる手術が必要になっちゃうわけ?」位に思えてしまうんやけど,ステント血栓症は起こってしまうと急性心筋梗塞を発症してしまったり,時には死んでしまうという重大な結末をたどってしまうことが多い厄介な病態やねん。
気になる!ステント血栓症はステントを入れてどのくらいで起こるものなのか?
意外に思われる方もいるかもしれないけれど,
ステント血栓症の発生時期で最も多いのがステント留置後1週間以内!!24時間以内に起こるものもある!
ステント血栓症の発生時期分類
- 急性ステント血栓症(acute stent thrombosis) : ステント留置手術後24時間以内に発生するもの
- 亜急性ステント血栓症(subacute stent thrombosis) : ステント留置手術後24時間以降30日以内に発生するもの
- 遅発性ステント血栓症(late stent thrombosis) : ステント留置手術後31日以降1年以内に発生するもの
- 超遅発性ステント血栓症(very late stent thrombosis) : ステント留置手術後1年を超えて発生するもの
しかし厄介なことに1年以上経ってからステント血栓症を発症することもあるねん。(超遅発性ステント血栓症と呼ばれる)
これは理由があって,もともとステントはベアメタルステント(BMS)というものが使われていた。BMSには弱点があって,ステント部分の再狭窄が起こりやすかった。これを克服するために開発されたのが,薬剤溶出型ステント(Drug-Eluting Stent : DES)というもの。これによってBMSに比べると飛躍的に再狭窄抑制作用を示してん。
ただし!新たな問題が起こる。DES留置から1年経過したにもかかわらず抗血小板薬中止直後に心筋梗塞などの虚血性心血管イベントの発生が報告されたのだ。これが超遅発性ステント血栓症( Very late stent thrombosis : VLST)ってわけ。
この状況を受けて2007年にはアメリカでガイドラインを改訂し,DES留置後は最低12カ月間DAPT療法を継続することを推奨するようになってん。っていうても,この「12カ月間」って期間には科学的根拠はなかったんやけどね。
さらにステントの改良は続く。第二世代DESが誕生するねん。これによってVLST発生率は飛躍的に低くなった。第一世代DESでは一定期間経過後(およそ1年くらい)に時間経過とともにステント血栓症リスクが増加していくという問題もあったけれど,それも第二世代DESは克服しているねん。
ちなみに現在は第三世代DESまで開発されている。DESについて細かく書き続けても意味がないので説明は割愛するで。
DAPT療法ってどのくらいの期間お薬を飲み続けるの?
実際にDAPT療法を受けるとなると知りたい情報やと思うので記載していこうと思う。
薬剤師としても,治療期間ってどのくらい何やろ?って気になるところやんね?
結論から言うと,論文などを読み漁る限り決まった期間は存在しない。
2014年の米国心臓協会(AHA)年次学術集会で DAPT Study という大規模ランダム化比較試験が発表されたんやけど,結果はDAPT療法を12カ月行うよりも30カ月継続した方がステント血栓症や主要脳心血管有害イベント(MACCE:死亡,心筋梗塞,脳卒中)のリスクを下げたというものやってん。
しかし!
世界中の研究者がこの結果を受けて行ったメタアナリティクスでは, DAPT Study の結果と反して有効性に差はないけど出血リスクは上昇する結果になってん。
ステントの機能向上もDAPT療法を続ける期間を決められない理由になってる
先に書いた通り,最近のステントは薬剤放出型ステント( Drug-Eluting Stent : DES )が主流になっている。
ステント血栓症を起こさないようにステントから薬が放出されてるのでステント血栓症のリスクは非常に低くなってるってヤツですな。
もしも,ステントの機能が変わってなければDAPT療法を行う期間も決定できたと思うねんけど,ステントの機能が向上しているゆえに,DAPTをどの位継続するべきか?については,ややこしなってんねん。
なぜか?
普通なら機能が向上したんやからDAPT療法の期間を短くしたら済むはずやん。って話やけど,じゃあ,どのくらいの期間ですか?
ってなると答えが出ぇへんのよ。個人差もある。結局ガイドライン改訂待ち,というのが多くの情報媒体の出している結論。
うーん,答え出せず。無念。
そやけど,そもそも留置するステントの性能がメッチャクチャ高くなって,DAPT自体が不要になることの方が大事やんな。
DAPT療法の期間が確定するより前に,ステントの進化が進むことに個人的には期待してしまう。
まとめ
DAPT療法( dual antiplatelet therapy )とは抗血小板薬2剤併用療法のことで,
アスピリン + チエノピリジン系抗血小板薬
を使う療法である。
使いどころは,経皮的冠動脈形成術( percutaneous coronary intervention : PCI )の後で,目的としてはステント血栓ができないようにすることである。
DAPT療法をどのくらい続けるべきなのか?はDAPT Study という大規模ランダム化比較試験が発表されたものの,世界中の研究者が行ったメタアナリティクスによると答えは異なる。長期間のDAPT療法は出血リスクを増やすというのが研究者たちの結論だったためである。
さらに,PCIで使われるステントも進化を遂げており,ステントの機能向上によってステント血栓リスクが下がっているため,DAPT療法はより短期間でいいのではないか?というのが大方の見方となっているものの,明確な期間は見いだせずにいるのだった。
今回の記事をまとめるとこうなりますわ。
ひとまず,DAPT療法ってなんやねん?にこたえるために書いた記事でしたが,参考になりましたでしょうか?
[kjk_temp id=”5491″]









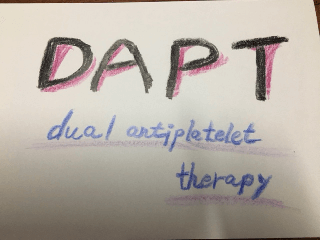
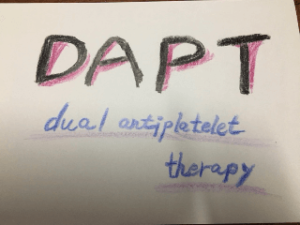
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (2件)
非常によくわかりました。
ジークフリード 様
コメントありがとうございますっ!!
これからも少しずつですがお役に立てるように記事を書いて参ります。何卒よろしくお願い致します。