 けいしゅけ
けいしゅけまいどっ! けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆



新米薬剤師のタコちゅけでちゅ☆
それでは,さっそく進んでいきましょう☆どうぞよろしくお願いいたします。もし,疑問点やご指摘,記事にしてほしい!といったご要望があればコメント欄へ遠慮なく書いてくださいね☆
外来服薬支援料って何ですか?
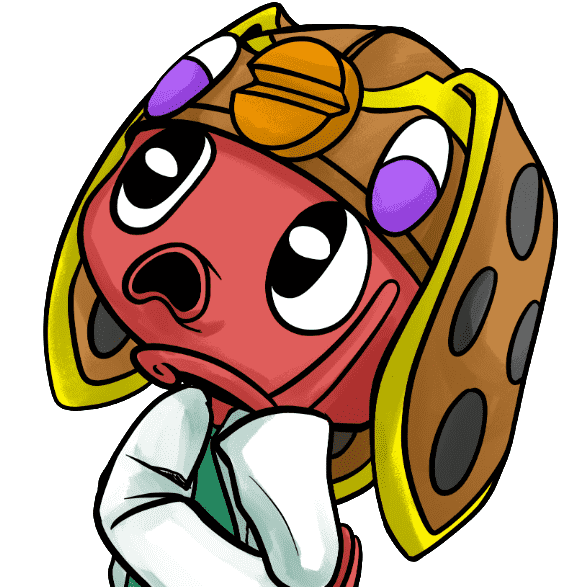
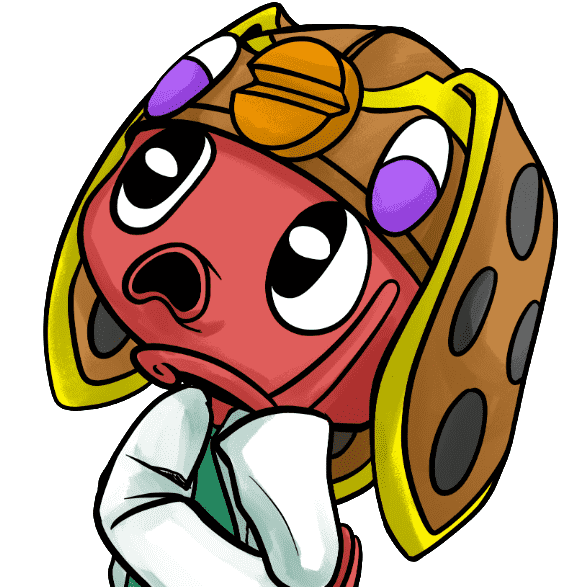
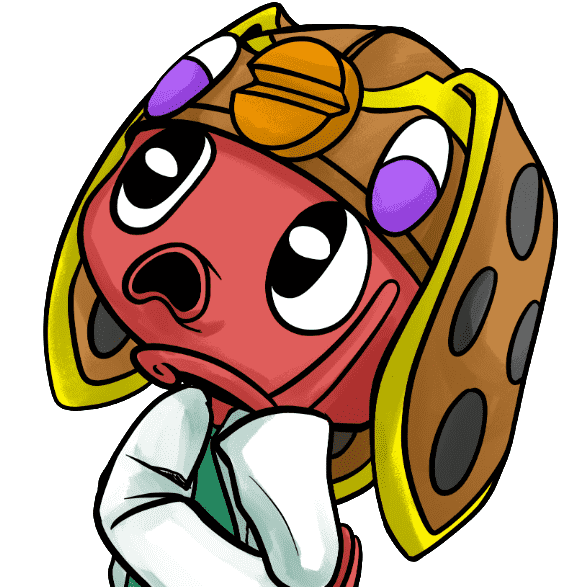
できれば,公の資料を見たいでちゅ



せやね。記事内容を現場に持ち込めるよう根拠を提示していくわ。
算定要件のポイントまとめ



それでは,外来服薬支援料について厚生労働省資料を提示したうえで,ポイントをかみ砕いていきましょう☆
まず厚労省資料を示し,本記事の根拠資料とします
外来服薬支援料の全体像を書いている資料は?
区分 14 の2 外来服薬支援料
(1) 外来服薬支援料は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。
(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整理するよう努める。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じる。なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。
(4) 外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。
(5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
(6) 外来服薬支援料を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴の記録に記載する。
(7) 外来服薬支援料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について,令和2年3月5日,保険発0305第1号
注1~3とは?
14の2 外来服薬支援料 185点
診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示) 令和2年 厚生労働省告示第57号 別表第3(調剤点数表)より
注1 自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。
2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
3 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
強調は筆者による



資料ありがとうございまちゅ。なるほど,かなりしっかりと書き込まれているんでちゅね。



そやねん。これが先ほど示したQ&Aの内容に対する根拠資料やわ。
ちなみに,調剤基本料1が取れない薬局の場合は薬剤師一人当たり年間12回以上算定が必要になっています。詳細は下記の記事で確認できます。
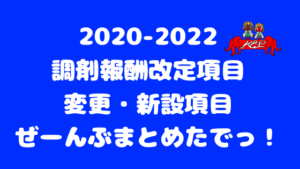
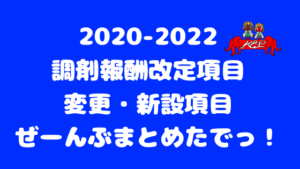
算定要件のポイントをかみ砕いて説明します
外来服薬支援料の算定は誰が対象になりますか?
自分で薬を管理して飲むことが難しい患者さん
外来服薬支援料算定のために必要な要件は?
- 患者さん・患者さん家族・医療機関の求め
- 薬剤師が服薬管理の必要性を判断し,整理・支援する薬を処方した医師に必要性の報告と支援の了承を得る事(電話でOK)
- 保険薬局へ服用中のお薬などを持参する動機付けのためにお薬などを入れる袋(いわゆるブラウンバッグ)を提供すること ⇒ 服薬管理を行う取り組みをしていることを患者さんなどに対して周知しておく
- 算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨 または 情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由 を 薬歴に記録する
- 自他どちらの保険薬局においても,在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない
外来服薬支援料って,どんな支援をするの?
- その患者さんが飲んでいる薬の数や種類を整理する。状況を把握する(必要性があれば疑義照会したり,他薬局に確認をとる)。
( 例:併用薬のチェック,重複している薬がないかチェック,相互作用のチェック,残薬の数を確認する,必要のない薬は飲まないように回収する…etc ) - 一包化をして,おくすり服用カレンダーにセットできるようにするなど,薬を飲みやすく・飲み忘れしにくいよう,患者さんによる薬の管理をカンタン化する
算定をした場合あとでするべきことは何ですか? 薬歴記載&レセプト作成について
- 薬歴への外来服薬支援の内容など4つのポイントを記載する
- 外来服薬支援料単独のレセプトを作成する
この2つが必要になります。
薬歴に記す4つのポイントって何ですか?
- 外来服薬支援をした理由
- 支援した内容(例:A病院とBクリニックの薬を〇日分1包化した。服薬カレンダーを設置した。etc…)
- 処方医に外来服薬支援の了承を得たこと
- 外来服薬支援で整理・一包化などをしたお薬の名称一覧
レセプト作成の仕方を教えてください
- 外来服薬支援料単独のレセプトを作成する
- レセプト上部の処方医や保健医療機関情報の記載はしない(処方箋を受け付けてないため)
- ①外来服薬支援をした日付 ②外来服薬支援で対象になった薬を処方した医師の氏名・保険医療機関の名称 ③具体的な理由(支援内容など)
を摘要欄に記載する - 処方箋の受付回数は「0件」と記載する



患者さんが来局した時以外でも,患者の求めに応じて保険薬剤師が患者さんの家に訪問して飲んでいる薬の整理などを行った場合でも算定できるで。
ちなみに,訪問に要した交通費(実費)は,患者さんに請求することが認められてるで。
服薬管理をカンタンにするような整理をせぇへんと単純に服薬指導をしただけやと算定はできへん点については注意が必要や(当たり前の話やろうけども)。
外来服薬支援料を算定できるのか!? 具体例を5つのQ&Aで説明します



算定要件は理解できたでちゅ!医師に電話での了承を得ましゅね。書面でのやり取りだとハードル高いなぁって思ってたので安心しました。
けど先生,改めてどんな場合に算定できるか具体例を知りたいでちゅ。同じ病院の異なる科からの薬を持ち込まれて一包化した場合はどうなんでしょう?などなどっ💦



そうやね!冒頭でも少し示してしまったけれど,改めて具体例を示していこか☆
Q&A形式で事例を挙げていくでっ!
患者さんからの求めがあり,それに応じていることがポイント
ちなみに,A病院からの処方箋を持ってくると同時に,①別の薬局でもらった薬 ②院内調剤で出された薬 などを持参してきた場合,患者さんからの求めがあって一包化した場合はどうだと思いますか?
もちろん,患者の求めがあって応じているので,算定可能です。
また,外来服薬支援料の要件を読み込むと”薬剤の一包化による服薬支援は,多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ,飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし,治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。”という文言があります。
本件の場合は,共に一包化指示の入った処方箋の受付・調剤となり,それぞれの病院の処方箋に基づいて別々の一包化を作る必要があるところを,併せて一包化することによる服薬支援と解釈します。
処方せん受付と外来服薬支援料の算定が同時である場合にミスしやすいから注意やで
この場合,一包化加算は取ってはいけません。(外来服薬支援は,そもそも処方せんによらず,調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため)



これはH24年調剤報酬改定の疑義解釈のQ&Aの内容やねん。
Qの文章の解釈が大事で,「患者さんまたはその家族からの要望」がなくって「単純に保険薬局側が処方日数が異なる一包化処方箋が複数あるので飲みやすいようにまとめますね,ってサービスをしているだけ」の場合は外来服薬支援料が取れないって意味です。



「患者さんまたはその家族からの要望」があれば,算定できるんでちゅか?



算定できます。ただし,ちゃんと服薬状況の把握をしてからやで☆ほかにもサプリメントやらさらに別の病院からもらっている薬なんかがあるなら,そこまでまとめなきゃ支援したことにならへんからね☆



きちんとニーズに応えきる,が大事でちゅね☆



その通り!サービスの押し売りはアカン。一方で,求めがあれば全力で応える。そこに料金が発生したとしても後ろめたいことなんてないし,逆に無料サービスをしてはいけないね。
なぜ外来服薬支援料が算定できないのでしょうか?
患者さんの求めに応じているのに,なんで?ってなりませんか。
答えはちょっと理屈っぽいです。
外来服薬支援料は,「自分で薬を管理して飲むことが難しい①外来患者さんもしくはその家族の求め,②または医療機関の求めに応じて,その患者さんが飲んでいる薬の数や種類を整理するとともに,一包化や服薬カレンダーの活用などによって薬が飲みやすい・飲み忘れしにくいように管理を支援することを評価する仕組み」です。
一方で本件の場合は,既に一包化して薬が飲みやすい・飲み忘れしにくいように管理を支援されているわけなので,そこから1種類抜いて一包化し直すのは算定要件を満たすとは考えられないのです。
外来服薬支援料についてのまとめ
外来服薬支援料を算定する流れは次のようなものでした。ざっとおさらいしましょう。
- 保険薬局へ服用中のお薬などを持参する動機付けのためにお薬などを入れる袋(いわゆるブラウンバッグ)を提供すること⇒ 服薬管理を行う取り組みをしていることを患者さんなどに対して周知しておく
- 患者さん・患者さん家族・医療機関の求めがある
- 薬剤師が服薬管理の必要性を判断し,整理・支援する薬を処方した医師に必要性の報告と支援の了承を得る事(電話でOK) ※残薬持ち込みの場合は,医療機関に外来服薬支援に関する情報を提供する
- 一包化や服薬カレンダーを利用するなどして患者さんにとって薬が飲みやすいように支援を実施する
- 外来服薬支援を実施した後で薬歴に次の4項目を記載する
①外来服薬支援をした理由
②支援した内容(例:A病院とBクリニックの薬を〇日分1包化した。服薬カレンダーを設置した。etc…)
③処方医に外来服薬支援の了承を得たこと
④外来服薬支援で整理・1包化などをしたお薬の名称一覧 - レセプトを作成する。記載事項やポイントは4つ。
①外来服薬支援料単独のレセプトを作成する
②レセプト上部の処方医や保健医療機関情報の記載はしない(処方箋を受け付けてないため)
③-1. 外来服薬支援をした日付 ③-2. 外来服薬支援で対象になった薬を処方した医師の氏名・保険医療機関の名称 ③-3. 具体的な理由(支援内容など)を摘要欄に記載する
④処方箋の受付回数は「0件」と記載する
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!
-


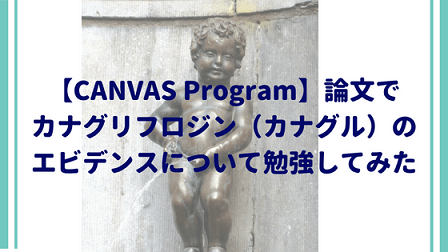
【CANVAS Program】でカナグリフロジン(カナグル)のエビデンスを見たが,SGLT2阻害薬は微妙だと思う
-


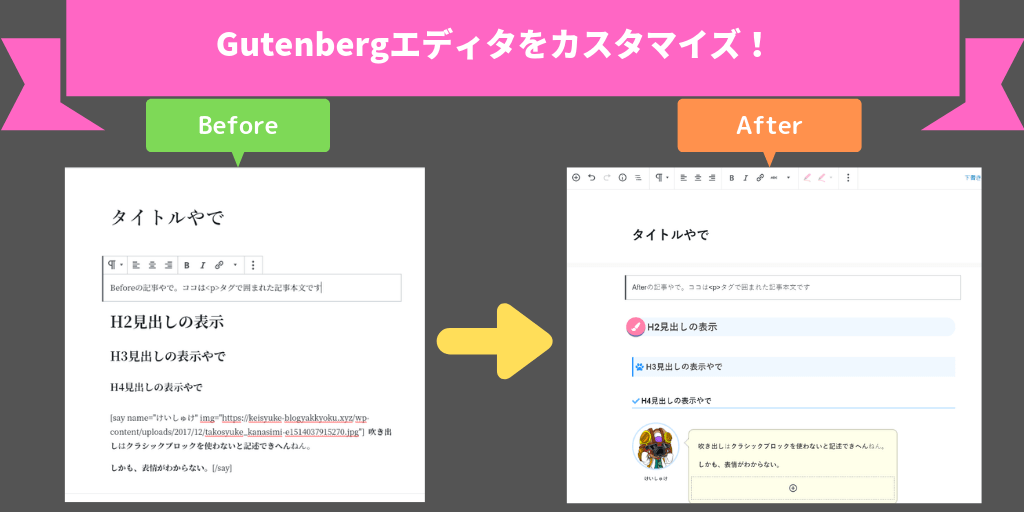
【WordPress】SANGOでGutenbergエディタに施した6つ+αのカスタマイズ全手順を無料公開します!
-



無料ブログは絶対におすすめしない!理由は4つ
-


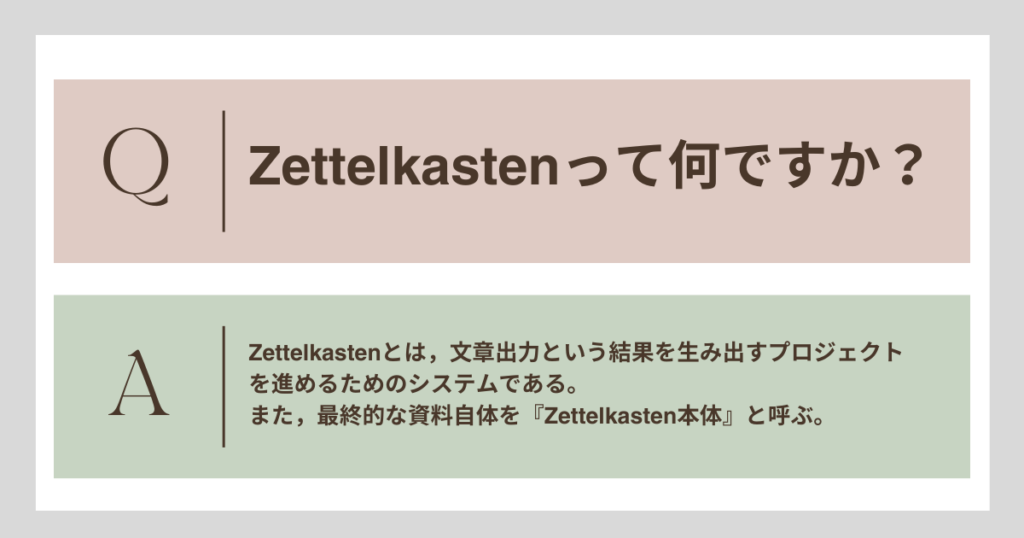
ツエッテルカステン(zettelkasten)って何ですか?
-


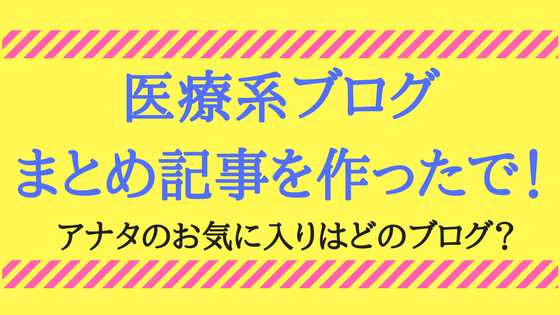
けいしゅけオススメ 医療ブログ30選 ~医師・薬剤師・看護師~
-


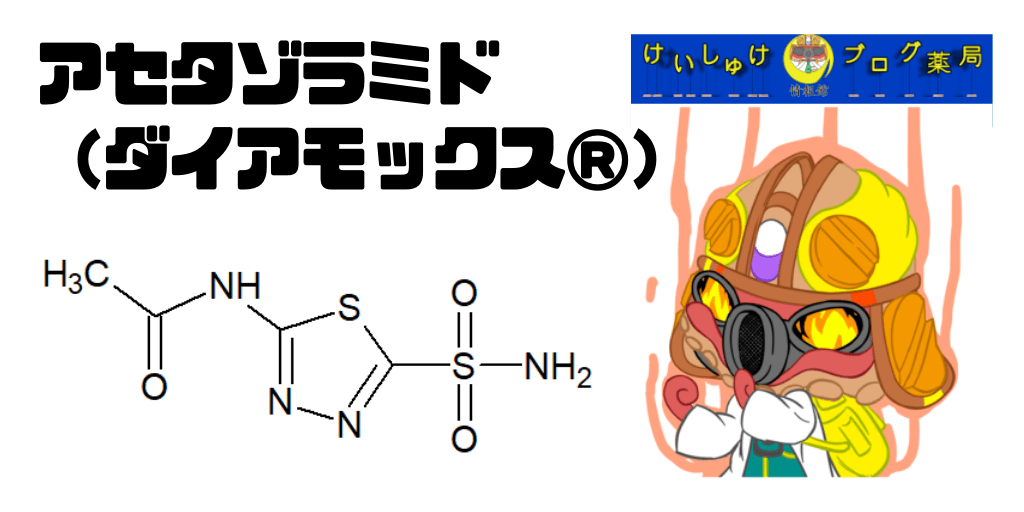
アセタゾラミド(ダイアモックス®)について独り勉強会









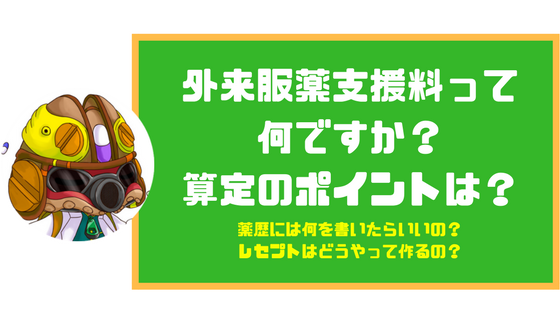
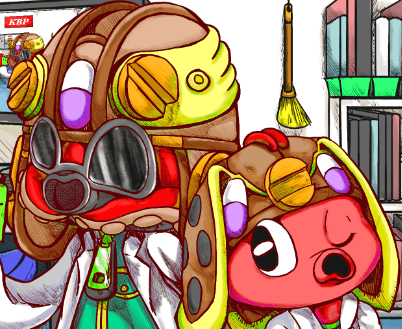
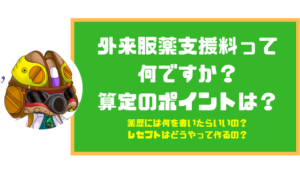
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (14件)
とても分かりやすく説明いただき、ありがとうございます。
外来服薬支援料について。
具体例1つ目の「A病院の内科の処方箋とB整形外科クリニックの処方箋を併せて1包化して欲しい」と求めがあって応じた場合はどうして外来服薬支援料を算定できるのか疑問に思いましたので、教えて下さい。
どちらか一方が持参薬として持ってきた場合は算定できるかと思うのですが、両方処方箋持参の場合は「服薬中の薬剤」に該当しないのでは、と思いました。
宜しくお願い致します。
N.K様
コメントありがとうございます!
仰る通りで、実は具体例1は僕も同じ考えで「無理ちゃうん?」と考えていました。
理由としては、疑義解釈資料の送付について(その8)(平成24年8月9日)で、以下の場合は算定不可と示されていたからです。
[box class="box2"](問1)
同一又は異なる保険医療機関の複数診療科から処方日数の異なる処方せんを保険薬局が受け付けた場合、薬剤等を整理し、日々の服薬管理が容易になるように支援すれば、その都度、外来服薬支援料を算定できるのか。
(答)算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。[/box]
しかし、H28の調剤報酬Q&A(じほう社)には似たケースで「算定可能」の記述があり、「マジでかぁっ!」となった為、本文に載せた次第です。
読み比べての違いは以下のとおりです。
①2つの処方箋に共に1包化指示がある
②別々に1包化するのでは服薬困難で、患者さんから「ややこしいから1つにまとめて1包化して欲しい」という求めがある。
③その求めに応じて、本来2つの1包化調剤が出来上がるものを1つにまとめる服薬支援をした
これらが重なることで、はじめて算定可能な例なのだと思われます。
・・・うーん。けっこう微妙やん?とスッキリ!とはいかない感じですね。
分かりやすい解説ありがとうございます。
一点質問なんですが、算定条件の注1及び注2合わせて月1回と記述がありますが、これは両方をクリアしなければならないのでしょうか?
片方ということでしたら、注1にそって算定する場合は、ブラウンバック運動の周知を行なっていなくても算定可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。
斎藤様
コメントありがとうございます。
これについては、注1)をクリアして算定するか、注2)をクリアして算定するかという意味で理解するといいと思われます。
どちらの条件をクリアして算定するとしても、月 1 回までしか算定できないということです。
ですので、注1に沿って算定する場合はブラウンバック運動の周知を行っていなくも算定可能と考えます。
レセプトについてですが、同日に2箇所の病院から処方箋を持ってきて、二つの処方箋を一包化した場合に、外来支援料を算定する時、レセプトは外来支援料をいれて、三枚になりますが、2箇所の処方箋入力に関しては一包化以外の、調剤基本料、調剤料、薬学管理料を算定していいのか?
えい様
ご質問ありがとうございます。
ご貴見の通りで差し支えないと考えます。
けいしゅけ様、初めまして。
丁寧でわかりやすいご解説、誠にありがとうございます。大変勉強になります。
外来服薬支援料に関して、2点質問させていただけますでしょうか。
①注1にて算定する場合の、服薬支援に関する処方医の了解について
A病院とBクリニックとC病院の処方薬を合わせて服薬支援する場合です。
この場合、3つの医療機関全ての処方医からの了解が必要という認識で相違ございませんでしょうか。
②生活保護の患者さんに外来服薬支援料を算定した場合の調剤券について
調剤券を市役所へ請求する際、処方元医療機関名等の記載が必要かと思います。
外来服薬支援料は医療機関名がないため、
外来服薬支援料を算定し調剤券を市役所へ請求する場合、医療機関名等の記載はどのようにすれば良いのでしょうか…。
分かりづらい文面で申し訳ございません。
また、不勉強でお恥ずかしい限りです。
お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いでございます。
めんま様
コメントありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
➀について:はい,各処方医に了承を得て外来服薬支援をするものと考えます。
➁について:出典)保医発0326第5号「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について
とあることから,記載なしで問題ないと考えます。(とはいえ,市役所に問い合わせて確認するのが確実かなと…。)
けいしゅけ様
ご返信ありがとうございます。
お忙しいところお手数をお掛けしてしまい申し訳ございません。
詳しくご返答くださり感謝です!
今後ともけいしゅけ様のブログやツイッターを拝見させていただき、学ばせていただきたいと思います。
本当にありがとうございました。
3ヶ月にわたりブラウンバッグ運動を強化したところ100件近くの要望が患者よりありました。いきなり活動を始めたせいか国保のみ全て返戻となりました。根拠を示し算定要件に問題なしと判断され最初の月は通りましたが次の月に返戻もしくは一部は問答無用で減点となりました。このような事は普通にあることなのでしょうか。 原点理由を聞いても的確な指摘がなく、ただ気に入らないと受け取れるような内容でした。
全く同じことをやっているのに、返戻になるものならないものの違いは保険によって違うのでしょうか。また問答無用で減点というのは諦めるしかないのでしょうか。
S様
コメント頂きありがとうございます。
今回の件については,実際に自分が経験しているわけではないので回答に責任は持てないことをご了承ください。
私見になりますが,急激な算定回数増加に対して支払基金側が疑問を持ったことが原因なのだろうと思われます。
とはいえ,確実に行動したものに関しての減点は,プロとして仕事したものの否定になりますので受け入れがたいですよね。
レセプト適用コメントに「いつブラウンバッグをお渡しし,どの病院の薬を,どのように整理してお渡ししたか」明記しては如何でしょうか。
返戻に対しての不服申し立てをしても良いと考えます。少なくとも納得のいく返戻理由を示して頂くのが良いでしょうね。
そうでなければ,診療報酬に定められた算定要件(診療報酬の存在意義)が損なわれてしまいます。
いつも勉強させていただいてます!
例えば院外処方箋をもってきて
一包化加算にみたない調剤でも
お昼の飲み忘れが多いなどの理由で
患者さんから一包化にして欲しいという要望があったら
医師に電話で了承得たら
外来服薬支援料取れるのでしょうか?
その場合は
処方箋のレセプトには一包化加算いれずに作成して
単独で外来服薬のレセプト作成するってことですよね?
外来服薬の単独のレセプトは
外来服薬支援料
のみでしょうか?
Ⓜ様
コメント頂きありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
頂いた質問に関しては,単独の医療機関からの院外処方箋に関するものと受け取りました。
この場合ですと,以下に算定要件を引用しますが,算定不可と考えます。
ただし,本件が仮に”(単独の医療機関から出た)調剤済みの薬”を”患者が持参した”として,飲みやすい形に改めて分包したりカレンダーセットして飲みやすくした場合は算定可能と思われます。
もしくは,持参薬+今回の質問にある院外処方箋を合わせて分包したのならば可能です。
算定要件がややこしいですが,この回答で大丈夫でしょうか?言葉足らずであれば補足いたしますのでご連絡くださいませ。
ありがとうございます!
よく分かりました。
もう一つ質問があります。
院内投薬された薬剤を持参した患者さんに対して加算した場合
自院での一包化するか、院外処方で薬局への一包化を支持すべきものとして
2回目以降算定不可
という疑義解釈を見ました。
現在もこの考えでしょうか?
調べてると色んな年代の疑義解釈が出てきて混乱しています。
例えば院内投薬された薬剤+別の薬局で調剤済みの薬剤を持参された場合は
2回目以降も算定可能ということでしょうか?