まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
この記事では,調剤報酬に関する情報の中でも「処方せん受付や受付回数,算定点数の定義とQ&A」を書いていきます。
 けいしゅけ
けいしゅけあまりにも基本的なこと過ぎるが故に,盲点になりやすい部分や。
タコちゅけ,一緒にまとめていこうか☆



バッチリ理解したいと思いまちゅ!皆さん,どうぞよろしくお願いいたしまちゅ🎵
処方箋受付回数と,処方箋枚数の違い



まずはジャブ。「処方箋受付回数と処方箋受付枚数の違い」
これはちょいと考えたらわかるかと思うんやけど,タコちゅけわかる~?



処方箋受付回数と処方箋受付枚数の違いでしゅか?
瞬間的には「同じでちゅ!」と感じたけど・・・そっか!
1人の患者さんが2枚以上の処方箋を持って来局した場合を考えたら説明できまちゅ!
この場合,処方箋受付回数は1回で,処方箋受付枚数は2枚でしゅ!!



大正解!



やったぁ🎵
処方箋受付回数と処方箋受付枚数を区別して考える必要性とは?
先に挙げた通り,処方箋受付回数と処方箋受付枚数は同じにならないケースがあることは理解できたと思うねんけど,だから何やねん?って思いません?
その,だから何やねん?を追いかけてみましょう。
処方箋受付枚数は何のためにカウントする?
医薬品医療機器等法のページを探索してみます。
医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年1月26日政令第11号)によると,処方箋の総取扱数は
- 眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋の数に2/3を掛けた数
- その他の診療科の処方箋の数
の合計になることが分かります。
(取扱処方箋数の届出)
第2条
薬局開設者は,厚生労働省令で定めるところにより,毎年3月31日までに,前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科,耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ3分の2を乗じた数とその他の診療科の処方せんの数との合計数をいう。以下この条において同じ。)を薬局の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
ただし,総取扱処方箋数が著しく少ない場合又はこれに準ずる場合として厚生労働省令で定める場合にあつては,この限りでない。
医薬品医療機器等法ページより引用(強調は筆者による)
さらに医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年2月1日厚生省令第1号)を参照してみると,薬局の開設の申請時には,1日平均取扱処方箋数(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第(2)号に規定する1日平均取扱処方箋数をいう。以下同じ。)を記載した書類を提出する事となってます。
ややこしいけど,もうちょいで結論に達するので我慢して読んでください!
で,この昭和39年厚生省令第3号)第1条第1項第(2)号に規定する内容こそが,
薬剤師は処方箋応需枚数40枚につき1人置かなければならない。
になるわけです。
もちろん,この処方箋応需枚数40枚=眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋の数に2/3を掛けた数+その他の診療科の処方箋の数であることは賢明な読者の皆様ならお察しいただけてると思てます🎵
昭和三十九年厚生省令第三号
薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令
薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第六条第一項第一号の二(第二十六条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)及び第八十二条の規定に基づき,薬局及び一般販売業の薬剤師の員数を定める省令を次のように定める。
(薬局の業務を行う体制)
第一条 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「法」という。)第五条第二号の規定に基づく厚生労働省令で定める薬局において調剤及び調剤された薬剤又は医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は,次に掲げる基準とする。
(中略)
二 当該薬局において,調剤に従事する薬剤師の員数が当該薬局における一日平均取扱処方箋数(前年における総取扱処方箋数(前年において取り扱つた眼科,耳鼻咽喉科及び歯科の処方箋の数にそれぞれ三分の二を乗じた数とその他の診療科の処方箋の数との合計数をいう。)を前年において業務を行つた日数で除して得た数とする。ただし,前年において業務を行つた期間がないか,又は三箇月未満である場合においては,推定によるものとする。)を四十で除して得た数(その数が一に満たないときは一とし,その数に一に満たない端数が生じたときは,その端数は一とする。)以上であること。



1つ目の結論が出たわ。
処方箋受付枚数をカウントする理由は,薬剤師の人員数の計算に使うためって事やね。
しかし,この要件って微妙やんね?眼科で60枚(60×2/3=40枚)と,1包化も多くて処方日数が56日以上といった総合病院前の内科処方40枚が,どちらも法的には薬剤師1名でOK!となってるんやもんなぁ・・・。
いや,眼科の処方を軽視しているわけではないよ?けどね,調剤にかかる時間数を考えたら,少なくともイコールにはならんやろといって良いんじゃないのかなぁ?タコちゅけはどう思う?



そうでちゅね。
皮膚科で混合が多い処方箋や,小児科の散剤や水剤の処方はやっぱり気を遣いまちゅ。
かといって,ほんじゃ線引きをどうすべきか?に対する明確な答えもないでしゅ・・・。
この話題は別の記事で先生,考えていきましょうよ。にテキストを入力
処方箋受付回数は何のためにカウントする?
受付回数をカウントする理由は,おそらく多くの読者の方が分かっているかもしれません。



調剤基本料の算定要件やものね。
2019年10月版の調剤報酬点数表ダウンロード対応&各項目の解説の記事から引用しましょう。
- 調剤基本料1・・・41点
・調剤基本料2,調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当しない保険薬局であること - 調剤基本料2・・・25点
以下のいずれかに該当する保険薬局。
ただし調剤基本料3のイ,調剤基本料3のロ又は調剤基本料の注2の(1)に該当する保険薬局を除く
・処方箋の受付回数が月2,000回を超える(かつ,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える場合)
・処方箋の受付回数が月4,000枚を越え,かつ特定の医療機関からの処方箋の集中率が70%を超えること
☆特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数が月 4,000回を超えること(当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在する場合にあっては,当該保険医療機関からの処方箋を全て合算した回数とする。☜医療モールが対象になった)
☆特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループに属する他の保険薬局において,保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は,当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。☜門前に系列薬局を複数出店することで集中率を下げようとしてもムダっていう意味)が月4,000回を超えること - 調剤基本料3
イ)20点
・同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える(集中率が85%を超える)保険薬局
・同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。)による処方箋受付回数4万回を超え40万回以下の場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%以下(集中率が85%以下)であっても,医療機関と不動産の賃貸借契約がある保険薬局
ロ)15点
・同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超える(集中率が85%を超える保険薬局)
・同一グループの保険薬局による処方箋受付回数40万回を超える場合で,特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%以下(集中率が85%以下)であっても,医療機関と不動産の賃貸借契約がある保険薬局 - 特別調剤基本料・・・10点(敷地内薬局)
注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては,注1本文の規定にかかわらず,特別調剤基本料として,処方箋の受付1回につき 10 点を算定する。
・病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局であって,当該病院に係る処方箋による調剤の割合が95%を超えること。
・調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない保険薬局



処方箋受付回数については,調剤基本料に関係するという事でちゅね。
あれ?なんか同時に下線が引かれている部分,”集中率”がキーワードにもなっているようでちゅ・・・。
- 処方箋受付枚数をカウントする理由は,薬剤師の人員数の計算に使うため
- 処方箋受付回数をカウントする理由は,調剤基本料の算定要件に使うため
もちろんこれだけではありませんが,ひとまず保険の知識ゼロから始めるならば,これを意識するところから始めると良いかもしれません。



さてさて,回収できていないクエスチョンがあるね。
タコちゅけ,聞きたいことあるで!って顔してるやん☆



もちろんでちゅ!
集中率って何でちゅか??
計算方法も知りたいでちゅ!



よっしゃ!
ほんだら集中率についてと,計算方法を解説していこか!!



お願いしましゅ!!!
集中率って何ですか?どうやって計算するの?
厚生労働省資料による説明をまず読んでみよう。
(3) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合は,特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から,歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は,それらを合計した回数とする。)を,当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり,同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上,緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋は,特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(平成30年3月5日)の194-195ページより引用 (強調は筆者による)
単純明快でした。まとめましょう。



読んでみるとと簡単でちゅね。



そやね。厚労省資料を読むだけやと,堅苦しくてとっつきにくい印象があるかも知れへん。
けど,ひも解いてみればこんなもんやわ。
平成30年疑義解釈(その①)でも集中率については言及があったで☆
まとめ
基本的な質問ほど,回答って明確にしにくいものだと記事を書いていて実感しました。なかなか根拠となる資料が見つからないんですよね。それでは最後にこの記事のまとめを書いて終わりにしましょう。
- 処方箋受付枚数と処方箋受付回数は考え方が違う。
- 処方箋受付枚数は,眼科・耳鼻咽喉科・歯科の処方箋の数に2/3を掛けた数+その他の診療科の処方箋の数でカウントしたもの
- 処方箋受付回数は,1度に複数科の処方箋を持ってきても1回とし,カウントしたもの(別の病院や,同一病院でも歯科は別)
- 処方箋受付枚数をカウントする理由は,薬剤師の人員数の計算に使うため
- 処方箋受付回数をカウントする理由は,調剤基本料の算定要件に使うため
- 処方箋の特定医療機関からの集中率を計算する理由は,調剤基本料の算定要件に密接に関係するから
こういった感じでしょう。これくらいわかっていればひとまずOK!と言えると思います!!
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!









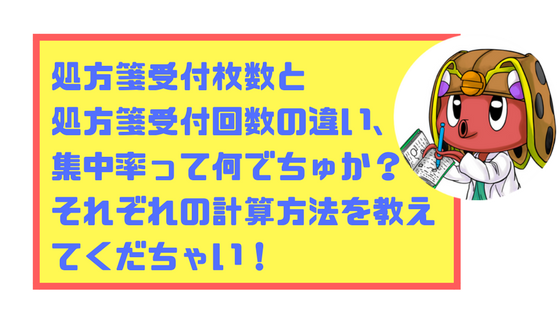
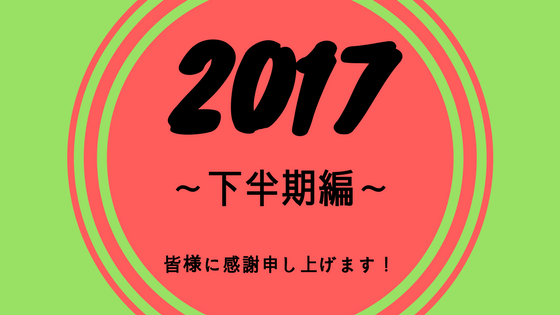
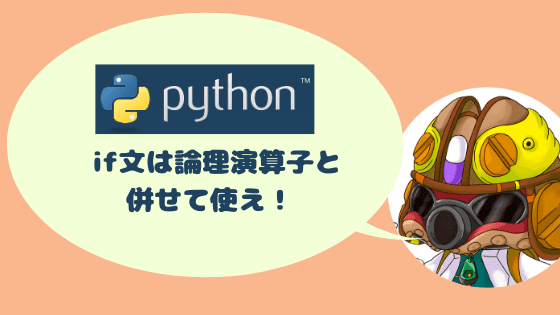



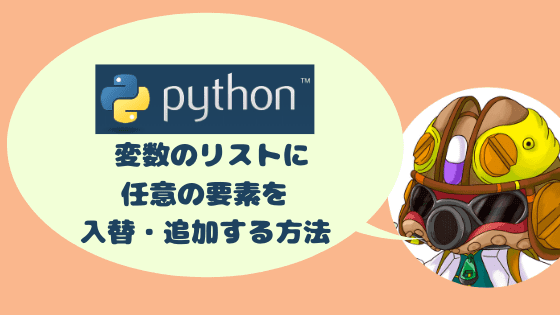
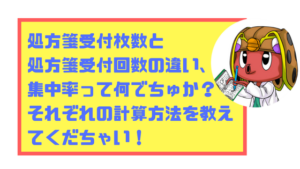
記事の感想など,ひとこと頂けますか?