タケプロンなどに代表されるPPI(プロトンポンプ阻害薬)を継続的に服用することで,非服用者に比べて認知症発症リスクが1.4倍になる!っていう論文を示したのはドイツ神経変性疾患センターのWilly Gomm博士ら。2016年2月15日の「JAMA Neurology オンライン版」に報告されたもの。
今回の記事は,先日の論文のPECOとは?何の略で,どう使うのか?という記事と,臨床試験の結果に出てくるハザード比や95%信頼区間の意味って何?という記事が実際にこんな風に応用できるで!というのをお見せしたいために書いたものや。論文の内容も面白いしね。


論文の概要
PPIが認知機能の低下に関係していることを示唆する研究がいくつか報告されている。そこで著者らは,PPIの使用と認知症の関係を明らかにするために大規模な高齢者集団による前向きコホート研究を実施した。対象は,ドイツ最大の法定保険会社であるAllgemeine Ortskrankenkassen(AOK)が取り扱った2004~11年の診療記録。入院患者と外来患者の診断名と処方の記録を調べ,PPI(オメプラゾール,パンテプラゾール,ランソプラゾール,エソメプラゾール,ラベプラゾール)を処方されている患者を抽出した。
PPIの処方記録が四半期に1回以上あれば,その四半期は「使用あり」と判定した。18カ月間(6四半期)の診療記録を調べ,全ての四半期で「使用あり」だった患者をPPI定期的使用者とし,全ての四半期で処方記録がなかった患者をPPI非使用者と判断した。認知症の評価は18カ月ごとに行った。データ追跡は認知症の初回診断,死亡,あるいは18カ月のインターバル終了まで行い,その時点で認知症と診断されなかった人は,引き続き次の18カ月間も観察対象とした。追跡は2011年末まで行った。
主要評価項目は,認知症の新規診断に設定,時間依存性Cox回帰モデルを適用し,年齢,性別,併存疾患,他剤の併用などの交絡因子候補で調整して,PPIの使用と認知症の関係を分析した。
2004年のベースライン時点では認知症ではなく,追跡期間中に初めて認知症と診断された75歳以上の患者7万3679人が解析の対象になった。このうち,診断されたインターバルにPPIを定期的に使用していた2950人(平均年齢83.8歳,77.9%が女性)と,使用していなかった7万729人(83.0歳,73.6%)を比較した。PPI定期使用者に多かった薬の種類は,オメプラゾール1340人,パントプラゾール659人,エソメプラゾール308人だった。
PPI定期的使用者の認知症発症リスクは,PPI非使用者に比べ有意に高かった。交絡因子で調整して求めたハザード比は1.44(95%信頼区間1.36-1.52)になった。性別別にハザード比を求めると,男性では1.52(1.33-1.74),女性は1.42(1.33-1.51)だった。PPIの種類別に行ったサブグループ解析では,オメプラゾールのハザード比が1.51(1.40-4.64),パントプラゾールが1.58(1.40-1.79),エソメプラゾールが2.12(1.82-2.47)となった。
患者を年齢で層別化したところ,PPI定期使用者の認知症リスクは,年齢が上昇するにつれて徐々に低下する傾向が見られた。75~79歳群のハザード比は1.69(1.49-1.92),80~84歳は1.49(1.35-1.66),85歳以上では1.32(1.22-1.43)だった。
引用元:日経メディカル http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/jama/201603/545943.html
はい。概要をキーボードで打つのがめんどくさいので引用で失礼しました。
なかなか,材料としてはおもろい記事でしょ?これがきっちり読み込めるかどうか。これまでの記事のチカラを借りて読み解いていくで!
論文の概要を PECO でまとめる
| P | 認知症を発症していない75歳以上の高齢者に |
| E | 継続して胃酸を抑える薬の中でもPPIという分類のものを服用した場合 |
| C | PPIを服用しない患者に比べて |
| O | 認知症の発症率は上昇するか? |
こうなりますわな。
ちなみにこの臨床試験の手法は 前向きコホート研究
コホート研究と症例対象研究の違いについては後日記事にしようと思っているので,記事が出来上がったらこの項目にも貼り付けます。
今回は結論のみ。
前向きコホート研究はエビデンスレベルとしては臨床試験の中では2番目に優れたものです。(1番はメタアナリティクスという手法)
ただし,この研究については,エビデンスレベルが下がる要因がある。それは以下の引用の通り
この分析結果から,研究グループでは,日常的なPPIの服用を避けることで,認知症リスクを低下させることができる可能性があると結論づけている。
論文ではこのPPI服用と認知症の関係性について,すでに報告されているマウスにおける研究で,PPIが脳血管関門を通じた脳のアミロイドベータ沈着を増加させることが明らかになっていることから,このことがリスクを有意に高めた原因ではないかと考察されている。
ただし,今回の研究は直接的にPPIと認知症の関係を生物学的に証明するものではないとし,因果関係を確認するには,より精度の高い研究方法であるランダム化比較実験が必要であるともされた。
認知症ねっと https://info.ninchisho.net/archives/7746
ランダム化比較試験,というものについても後日記事にしてみる必要が出ました。これも後日のお楽しみという事で今回はいったん割愛!
論文の結論の PECO です。
| P | 認知症を発症していない75歳以上の高齢者に |
| E | 継続して胃酸を抑える薬の中でもPPIという分類のものを服用した場合 |
| C | PPIを服用しない患者に比べて |
| O | 認知症の発症率は1.44倍上昇した。ハザード比 は1.44( 95%信頼区間 は1.36-1.52)(信頼区間が0をまたいでいないので,有意差ありと判定できる) |
かなりシンプルに結論がわかりますね。
ハザード比 と 95%信頼区間 もしっかり記載されてるでしょ?
ハザード比 は1.44( 95%信頼区間 は1.36-1.52)
ほらね,今までの記事を読んでいるとメッチャクチャ意味がわかるでしょ?
まとめ
そんなわけで,今回は,以前に書いた3つの統計に関する記事を応用して実際に論文がこんな風に読めるようになるよ!っていうことを紹介しました。どうでしょうか?おもろいやろ??っちゅうても,まだコホート研究と症例対象研究の違いについてや,ランダム化比較試験についてそれぞれどういうものか?を記事にしていないので,これを後日のお楽しみにしようと思います!
この記事をきっかけにEBMや論文を読んで勉強する楽しさを知ってもらえたらなぁと思います!
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/
 けいしゅけ
けいしゅけこの記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!










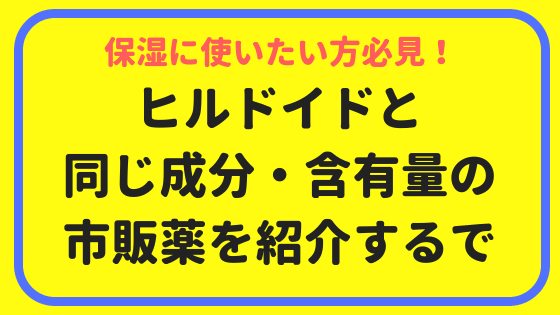



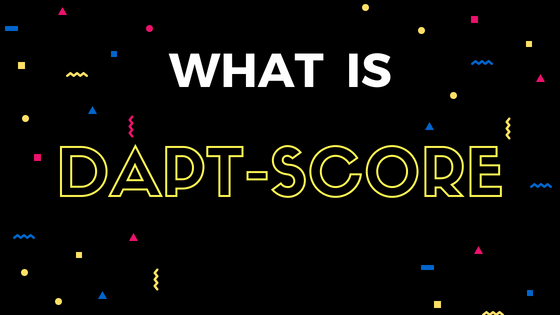
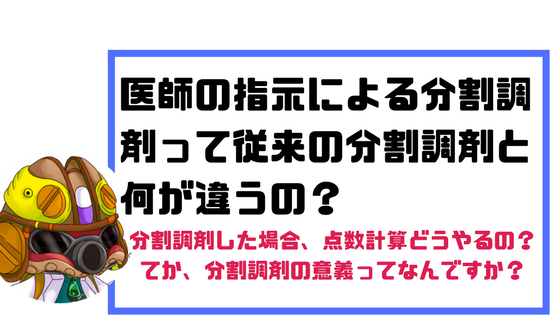

記事の感想など,ひとこと頂けますか?