服用薬剤調整支援料って何ですか?算定要件に関する4つのポイント
当ページのリンクには広告が含まれています。
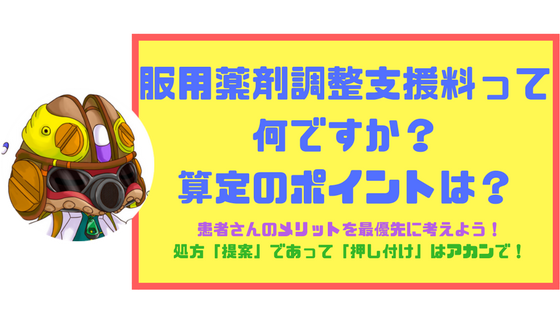
※当ブログはアフィリエイト広告を利用しており,記事にアフィリエイトリンクを含むことがございます
まいど!けいしゅけ(@keisyukeblog)です☆
調剤報酬点数表【2018年調剤報酬改定資料】を作ったで!の記事のとおり,今回の診療報酬改定の調剤の部分(調剤報酬改定)で地域支援体制加算が新設されました。そして厄介なことに調剤基本料1をとれない薬局は,薬剤師1人あたり1年間に8つの加算をすべて算定しやんとあきません(*調剤報酬点数表【2018年調剤報酬改定資料】参照)。
ちなみに服用薬剤調整支援料を薬剤師1人あたり年間で何回算定すれば,調剤基本料1以外の薬局が地域支援体制加算を取れる条件のひとつをクリアできるんでちゅか?
必要な服用薬剤調整支援料の算定回数は1回 / 年間や。
たった1回だけでいいんでちゅか??
[/ふきだし]
その1回のハードルが実はすんごい高いのだ。
これから服用薬剤調整支援料の算定要件と4つのポイントをまとめていくけれど,難関やぞこれは。
言い換えれば,薬剤師としての腕の見せ所っちゅう感じやね。
・・・先生,いつもなら先生から言われちゃうので今回は言いまちゅ!
そのカベ,この手でよじ登って見せまちゅ!!!燃えてきました!!
算定方法や,算定するにあたっての4つのポイントをまとめていきましょう!!
よっしゃ,アツいやんけタコちゅけ!!そういうの好っきゃで!!
ほんだら,気合い入れてまとめていくわっ!!
目次
服用薬剤調整支援料って何ですか?
(新設)服用薬剤調整支援料・・・125点
服用薬剤調整支援料とは何ですか?
患者の意向を踏まえ,患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で,処方医に減薬の提案を行い,その結果,処方される内服薬が減少した場合を評価するものです。
[算定要件]
6種類以上の内服薬が処方されていたものについて,保険薬剤師が文書を用いて提案し,当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に,月1回に限り所定点数を算定する。
この場合の「2種類」というのは,具体的にはなんでちゅか?
内服薬の種類数の計算はね,錠剤,カプセル剤,散剤,顆粒剤及び液剤と色々な剤形があるわけやけども,1銘柄ごとに1種類として計算するで。
具体例を挙げて説明するわ。
[般] ロキソプロフェンナトリウム錠60mgという「1銘柄」を減薬した場合に「1種類」の減薬になりますわな。
[般] ロキソプロフェンナトリウム細粒10%という「1銘柄」を減薬した場合にも,「1種類」の減薬とカウントできるわけや。
ちなみに,[般] ロキソプロフェンナトリウム錠60mgに加えてもう「1銘柄」,[般] レバミピド錠100mgを減薬した場合には,合わせて「2種類」の減薬になるんよ。
「毎食後」の薬だとか,「1剤」を減薬するのとは違うから注意やで☆
ありがとうございまちゅ!
先生,内服薬の「1剤」って,服用時点=どのタイミングで飲むか,で整理するんでちゅよね??
具体的に言えば「朝食後」とか,「朝・夕食後」,「毎食後」,「寝る前」といった具合に。
せや☆わかりやすい説明するやんタコちゅけ。
ちなみに同じ服用時点の薬で処方されている日数が違ったとする。Aという薬が14日分,Bという薬が28日分でどちらも「朝食後」で処方されている場合を考えよう。
この場合は「1剤」になるか「2剤に」なるか。どっちやと思う??
この場合は「1剤」でちゅ!
服用時点が同一である者は投与日数にかかわらず「1剤」として算定しましゅ。
服用薬剤調整支援料の算定要件に関する4つのポイント
それでは服用薬剤調整支援料を算定するに当たってのポイントをまとめていきます。
1.2種類の内服薬を減薬した状態が4週間以上継続する必要がある!
減薬した状態が続かなきゃダメってことやねんけど,まぁ~当たり前やんな。
減薬をしました。けど,その次の週には「やっぱり薬が減って心配になったから処方してもらってん」
なぁんてことになった場合を考えるとわかりやすい。これじゃ「減薬した」とは言えないわなぁ。「いったん止めた」ってだけやん。
患者さんの減薬の意向を踏まえて減薬しなきゃうまくいかないでちゅよ,ってことでしゅね!
2.服用薬剤調整支援料の調整前の内服薬の種類数から除外される条件は大きく分けて2つや!
では,実際に患者さんの減薬の意向を踏まえて,お薬の種類を減らそうと思ったときに2つだけ気を付けたい基本的と言えば基本的な条件があるねん☆
2-1. 飲み始めてから4週間以内の内服薬や頓服薬は減薬した種類のカウント対象外!
4週間以上継続して飲んでいる薬が,服用薬剤調整支援料の算定要件にある(6種類以上の)「内服薬」として認められるってことやね。
つまり6種類以上の薬を4週間以上飲んでいる患者さんの薬を2種類減らさないと服用薬剤調整支援料は算定できひんねや。
頓服薬はそもそも,継続して飲む意味合いがないから対象外でちゅ!
2-2. 現在飲んでいる薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤
および内服薬以外のお薬への変更は減少した種類のカウント対象外
この条件はしっかり分かってなきゃダメやで!
例えば,Aという血圧を下げる薬と,Bという利尿剤を患者さんが飲んでいたとしよう。Bという利尿剤と同一薬効分類とあるから利尿剤Cという成分があったとして,
降圧剤Aと利尿剤Cを1つにまとめた配合剤Dに変更した場合に,2種類から1種類に飲んでいる薬の「種類」を減らしたとはならないんや。
常識的に考えりゃわかるわな。
確かに2個のむところを1個にしとる。けど,成分の種類は2種類で変わっとらへん。
これを「種類」の減少として認めてしまったらやたらめったら「配合剤にしませんか?」運動が起こってまうもんなぁ。
本質的に「減って」ないでちゅからね。
ちなみに,内服薬以外への変更ってどういう意味でちゅか?
これな,わかりやすいのは「貼り薬」への変更や。
認知症の薬や高血圧の薬,女性ホルモン剤,痛み止めに至るまでいろんな種類の薬で「貼り薬」が存在するねん。
これに変えることで「内服薬=飲み薬」が減ったやろ?みたいな屁理屈は通用しまへんで!って事やね。
薬効分類って何ですか?
薬効分類というのは,利尿剤・血圧降下剤 ・気管支拡張剤などなどを指します。
薬効分類表というものが厚生労働省が出していますので,リンクボタンを貼ります☆
薬効分類表
3.処方医へ減薬を提案する場合,薬剤師は減薬に係る患者さんの意向や減薬提案をするまでに考えた薬学的内容を薬剤管理服用歴に記載しておく。また,保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は薬剤服用歴の記録に添付するなどのして記録・保持する。
保険薬剤師は患者さんのお薬の飲む種類を減らしたいという意向を確認して,処方医に対して文書(必要に応じて対面相談)にて減薬を提案するわけですが,保険医療機関からその提案に対してどうなったか結果の情報共有を厚生労働省はイメージしているようです。
⇒減薬を提案する書面には保険医療機関からの返事(提案の結果)を記す欄があると良いかもしれないですね。
書面でのやり取りをしたのだから,提案までのいきさつや薬学的に自分がどう考えて行動したかを記録することも,医療機関からの返事を保存するのも当然やね。
4.服用薬剤調整支援料を算定した患者さんに1年以内にもう一度服用薬剤調整支援料を算定する場合はさらに2種類の減薬が条件や!
かなり実現する可能性は低いと思われるものの,きちんと条件を設定してきますね,厚生労働省は。
6種類以上の薬を4週間以上飲んでいる患者さんの減薬の意思を確認したうえで,医師に文書で減薬提案をして,結果を薬歴に残したあとでさらにもう2種類の薬を減薬提案して減ったらもう一回算定していいで!
って条件。
もともと飲んでいた薬の種類がかなり多い場合はありえる話やね。
ただし,減らすことを目的にしたらアカン。
大事なのは薬を減らすことじゃないもん。減らすことによって患者さんにとって真のアウトカムが得られるかどうかを十分に吟味して行わないときっと失敗するわ。
[/ふきだし]
 タコちゅけ
タコちゅけ














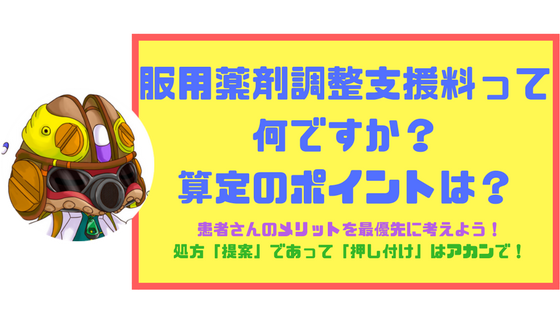






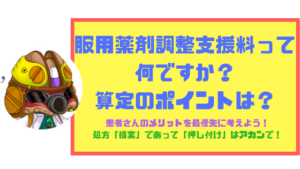
記事の感想など,ひとこと頂けますか?