ライゾデグ配合注は使用前に振って混ぜなくて良いんやって!
え!?なんで???
調剤室にこんな会話が響き渡る。
ライゾデグ配合注フレックスタッチってなんですか?
ライゾデグ配合注フレックスタッチは2015年12月1日に販売開始になった
インスリン デグルデク(トレシーバ):インスリン アスパルト(ノボラピッド)=7:3
で配合された溶解インスリンアナログ製剤や。
ライゾデグ配合注フレックスタッチは,対抗品の持続型インスリン注射のランタス(インスリン グラルギン)に対して,HbA1cを下げる効果の面で非劣勢が検証され,優越性が実証されると同時に,低血糖及び夜間低血糖リスクを高めないことが確認されている。
- ライゾデグ配合注フレックスタッチは何で使用前に振ったり転がしたりして混ぜなくていいの?
- 今までのインスリンの混合型製剤と言えば,必ず使用前に掌で10回ほどコロコロと転がしたり,プンッ!プンッ!と振る必要があったやん?あれってなんでそうする必要があったの?
この理由に本記事では迫っていこうと思う!!!
ライゾデグ配合注フレックスタッチはなぜ使用前に振って混ぜなくてもいいのか?
この答えが知りたくてこの記事をお読みであろうから,単刀直入に答えを言おう。
結晶化された中間型インスリンを含まへんからや!
ふむ。いきなり答えを言うたものの,これだけ読んでも。
あ,そう。で?
って思うやんね?
いやいや,中間型インスリン?結晶化?は?ひ?ふ?へ?ほ?
ってなりますわ。
そんなわけで,過去に販売されていた手のひらでコロコロ&プンッ!ププンッ!と振って混ぜなければならなかったインスリン注射剤がなぜにそうして混ぜなければいけなかったのか?を知らないと解決できないようや。
 けいしゅけ
けいしゅけなかなかオモロイやんけ!
”インスリン注射は振って混ぜてから使う!”って常識をどうやって破ったのか?追求していこうや!!
インスリン注射の一覧を分類化して表にまとめれば混ぜなければならない理由が見つかる?
従来の混ぜなければならない製剤を一覧にまとめてみよう。
まとめてみると非常によくわかるねん。
赤字にしているところに注目や。
混ぜないといけないインスリン注射には全て中間型インスリンが入ってる
どうやらこれが答えのようや。
中間型インスリンかぁ。何それ?
調べてみると・・・
1922 年にイーライリリー社が世界で初めてインスリンの製剤化に成功し,1923 年にインスリ ン製剤「アイレチンⓇ」が発売された。
同年にノルディスク社から「インスリンレオⓇ」,ヘキ スト(現サノフィ・アベンティス)社から「インスリンヘキストⓇ」が発売された。
すい臓抽出物から精製されたインスリンは,正規インスリンまたはレギュラーインスリンと 呼ばれ,その後 Regular の頭文字をとってRと称されるようになった。
1924 年,ベクトン・ディッキンソン社は世界初のインスリン専用注射器を製造し,1925 年に ノボ社からシリンジタイプの「インスリンノボⓇ」が発売された。
1926 年に Abel がインスリンの結晶化に成功し,1929 年に Scott がインスリン結晶化の亜鉛 の必要性を発見した。
この頃からインスリンの作用時間を考慮した製剤の開発が進められ,1938 年にはノボ社がプ ロタミン亜鉛インスリン(PZI)を発売,1946 年にノルディスク社から,自社インスリン研究所 長のハーゲドンらが開発した,
インスリンに硫酸プロタミンを付加したイソフェンインスリン の結晶性プロタミンインスリン(NPH)が発売された。
この製剤は,Neutral Protamine Hagedorn の頭文字をとってNPHと命名され,その後NPHやNと称されるようになった。
インスリン製剤の基礎知識 より引用
インスリン製剤の基礎知識 より引用
ふむふむ,そういうことなのか。



そう,中間型のインスリンって即効型や超即効型のインスリンを結晶化して作用時間を延ばしたものやねん。
なにやらサケの精子から抽出したプロタミンっていうタンパク質だったり,亜鉛を即効型・超即効型のインスリンにくっ付けることで結晶化するんだとか。
当然のことながら,結晶化しているんやから溶解していない。だからインスリンをみると白濁しているわけや。やから性状は「白色の懸濁液」ってなるわけ。
ほんでもって溶解していないんやから,放っておけば当然沈殿するわなぁ。・・・振ったりして混ぜないとアカンやん!!お~,答えにたどり着いたわ!!!
そう,中間型のインスリンは結晶化しているインスリンであり,これが超即効型のインスリンの溶液の中に溶け込んでいるものこそ,
混合型や中間型と呼ばれるインスリン製剤やねんね。結果として,使用する前には沈殿してしまっている中間型の結晶化されたインスリンを即効型(超即効型)のインスリンの溶液と均一に懸濁させる必要が出てくるからこそ混ぜる必要があったわけ。
ライゾデグ配合注フレックスタッチはなぜ混ぜないのか?さぁ答えが出たよね!!
先ほど書いた通り,
結晶化された中間型インスリンを含まへんからや!
ライゾデグ配合注フレックスタッチ=インスリン デグルデク(トレシーバ):インスリン アスパルト(ノボラピッド)=7:3
そして,
- インスリン デグルデク(トレシーバ) : 持効型インスリンで,溶解液である
- インスリン アスパルト(ノボラピッド) : 超即効型インスリンで,溶解液である
2つの溶解液を足しても,ライゾデグは透明な溶解液であり,沈殿物は存在しない。
よって懸濁させる動作である振ることによる混和動作は不要なのだッ!!!
最後に:ライゾデグ配合注が混ぜる必要がないことで得られる最大のメリット
これが最も大事なことやねんけど,多くのお年寄りの患者さんは実はちゃんと懸濁作業をできていない可能性がある!
実際に,僕が経験した例では,ノボラピッド30ミックス注を処方されていた患者さんがライゾデグ配合注フレックスタッチに変更になった後,なんとHbA1cが1.2も下がったのだッ!!!
具体的には,HbA1cの数値が7.4➡6.2になった。
即効型:持効型=3:7で同じにもかかわらずこれだけの薬効が現れたという事が示す事実は?
これは明らかに
ちゃんとノボラピッド30ミックス注を混和して使えてなかったからじゃないの?
てことやんね?



やはりお年寄りは目も手先も衰えている場合が多いので,最初から溶解液であるライゾデグ配合注フレックスタッチは非常にありがたい存在と言えるのではないやろうか?僕はそう思う。
けいしゅけのオススメ書籍 3選です☆



これらの書籍は僕が影響を受けまくったものです。どれか一つでもいいので迷わず1冊手に取ってみて下さい。薬を比較の視点で考える,薬学を構造式・理論・エビデンスから見る,人として生きていくのに大切なことって何か・・・。それぞれの本があなたに伝えてくるメッセージを受け取ってみて下さい☆
けいしゅけイチオシ勉強サイト
今回の記事はここまでや☆
最後まで読んでくださってホンマおおきにっ!!お時間を使って読んでくださったことに心から感謝申し上げます!
\最新記事をメールでお知らせするで/



この記事の感想をコメントしていただけるとメッチャうれしいです!!
ご意見&ご質問も遠慮なく書いてください☆皆さんとの対話を楽しみにしています☆
下のボタンを押すとコメント記入欄へジャンプできますよ~!!



ウチのけいしゅけはSNSもやってまちゅ!良ければフォローしてやってくださいでしゅ💛
Twitterでけいしゅけをフォロー
けいしゅけFacebookにいいね!









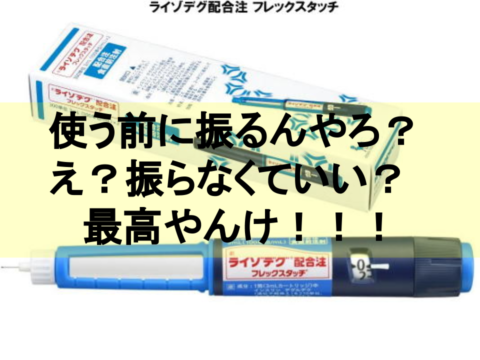




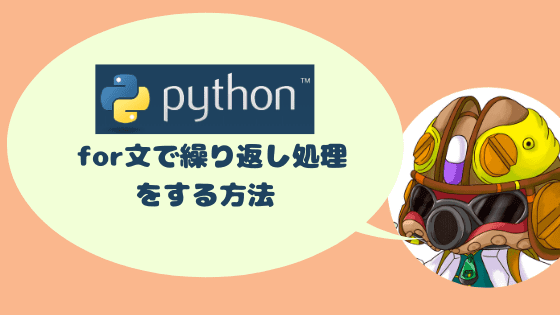
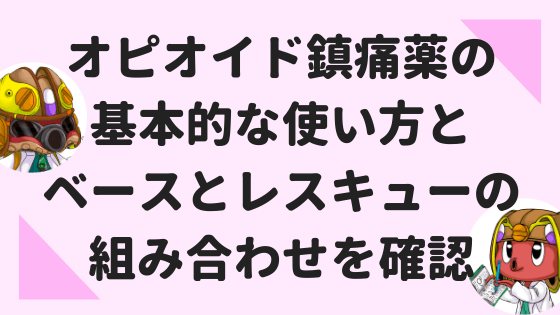
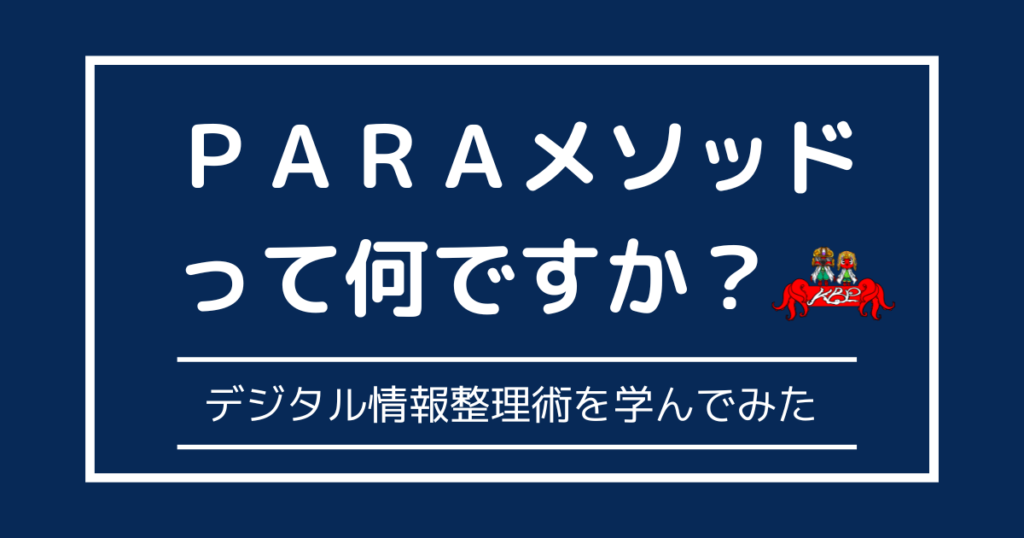



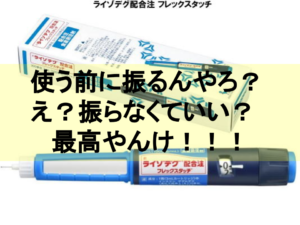
記事の感想など,ひとこと頂けますか?