【CANVAS Program】でカナグリフロジン(カナグル)のエビデンスを見たが,SGLT2阻害薬は微妙だと思う
これは先日の投稿,SGLT2阻害薬エンパグリフロジン(ジャディアンス)の論文【EMPA-REG OUTCOME】を復習や!

とセットで勉強した後に感じた感想である。
SGLT2阻害薬。これ,使う必要は今のところないんとちゃうかな?エビデンス的にはそう言わざるを得ない。
この結論を出した過程を理解していただきたい。ひとまず内容を確認していこう。
CANVAS試験( Canvas Program )ってそもそも何ですか?
CANVAS Programは2つの試験の結果を統合して発表されたもの
既存の糖尿病治療に対して非劣性であることを証明するために,カナグリフロジンの心血管イベントへの影響を検証するために実施された第Ⅱ相ランダム化比較試験(RCT)がCANVAS(Am Heart J 2013;166:217-223)や。
さらに,心血管イベントおよび腎臓関連イベントへの影響を検証するために実施された第Ⅲ相ランダム化比較試験(RCT)がCANVAS-R(Diabetes Obes Metab 2017;19:387-393)ってわけ。
これらの結果を発表したものが今回の記事で取り上げるCANVAS Programの結果や。
参照URL:http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1611925#t=article
[/box]
カナグリフロジン(カナグル)の実力や如何に!?CANVAS Programのチェックポイント
- ランダム化されているか? ➡ されてる(ランダム化比較試験-非劣勢試験)
- 論文のPECOは何か?
- P: 2型糖尿病患者で以下の条件を持つ人が
- 30歳以上・症候性アテローム硬化性心血管疾患がある・HbA1cが7.0~10.5%
- 50歳以上・心血管疾患リスク因子のうち2つ以上を有する
ちなみに,30ヶ国・10142例・平均年齢63.3歳・男性64.2%/女性35.8%・平均糖尿病罹患期間13.5年である。また,65.6%は心臓病の既往歴があった。
- E: カナグリフロジン(カナグル®) 300mg/日 または 100mg/日 を投与すると( 5795例 )
- C: プラセボ群に比べて ( 4347例 )
- O: MACE(心血管疾患死亡・非致死的脳卒中・非致死的心筋梗塞の複合アウトカム)を減少できるのか?
- P: 2型糖尿病患者で以下の条件を持つ人が
- 1次アウトカムは明確か?➡ 明確である
- 真のアウトカムか?➡ 真のアウトカムである
- 盲検化されているか?➡ 被験者のみ単盲検化されている
- 解析方法は? ➡ ITT解析
- 追跡期間は? ➡ 188.2週間
CANVASでは
- プラセボ群
- カナグリフロジン100mg群
- カナグリフロジン300mg群
の3群に1:1:1でランダム化割り付けが行われていて,
CANVAS-Rでは
- プラセボ群
- カナグリフロジン100mg群(ただし,300mgへの用量調節が許容されていた)
の2群に1:1で,それぞれランダムに割り付けられた。
CANVAS Programの結果:1次アウトカムで心不全による入院と心血管死または心不全による入院を有意差をもって下げたという結果を出した。複合アウトカムも有意差をもって下げた。
1次アウトカム
MACE(心血管疾患死亡・非致死的脳卒中・非致死的心筋梗塞の複合アウトカム)は優位差をもってカナグリフロジン群で減少
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=26.9/1000人患者・年 : 31.5/1000人患者・年
➡ハザード比 0.86 (95%信頼区間:0.75-0.97) p<0.001 NNT=217人/年
2次アウトカム
心血管死のイベント抑制効果に有意差なし
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=11.6/1000人患者・年 : 12.8/1000人患者・年
➡ハザード比 0.87 (95%信頼区間:0.72-1.06) p=0.9387
非致死的心筋梗塞のイベント抑制効果に有意差なし
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=9.7/1000人患者・年 : 11.6/1000人患者・年
➡ハザード比 0.85 (95%信頼区間:0.69-1.05) p=0.9777
非致死的脳卒中のイベント抑制効果に有意差なし
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=7.1/1000人患者・年 : 8.4/1000人患者・年
➡ハザード比 0.90 (95%信頼区間:0.71-1.15) p=0.4978
総死亡のイベント抑制効果に有意差なし
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=17.3/1000人患者・年 : 19.5/1000人患者・年
➡ハザード比 0.87 (95%信頼区間:0.74-1.01) p=0.5675
心血管死亡または心不全による入院のイベントはカナグリフロジン群が有意差をもって抑制した
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=16.3/1000人患者・年 : 20.8/1000人患者・年
➡ハザード比 0.78 (95%信頼区間:0.67-0.91) p=0.4584 NNT=222人/年
安全性アウトカムに問題の下肢切断リスク上昇/骨折リスク上昇の記載あり!(論文page.6)
下肢切断イベントリスクはカナグリフロジン群で有意差をもって上昇した
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=6.3/1000人患者・年 : 3.4/1000人患者・年
➡ハザード比 1.97 (95%信頼区間:1.41-2.75) p<0.001 NNH=345人/年
全骨折イベントリスクはカナグリフロジン群で有意差をもって上昇した
カナグリフロジン投与群:プラセボ群
=15.4/1000人患者・年 : 11.9/1000人患者・年
➡ハザード比 1.26 (95%信頼区間:1.04-1.52) p=0.02 NNH=286人/年
CANVAS Programの結果を見て,カナグリフロジン(カナグル®)への考察
正直言って,SGLT2阻害薬エンパグリフロジン(ジャディアンス)の論文【EMPA-REG OUTCOME】を復習や!
と2次アウトカムを見る限り,有意差をもってリスクを下げる項目って被るねん。心血管死または心不全による入院ってやつね。
ってことは,やっぱり利尿作用による効果なんじゃないの~ん?という印象があるんよね。
あと,
1次アウトカム,これ信用できるん??
EMPA-REG OUTCOMEでは1次アウトカムって用量別に見てみると有意差がなくなったからね。
あの試験でも用量を統合した結果におけるMACE抑制のアウトカムの95%CIって~0.99とかでギリギリセーフ!って感じのもんやったやろ?
CANVASも用量を明らかにしてやってみたら?
これやってみたらな~んか都合悪い結果が出てくる気がしてならへんわ。
メ〇ィカル〇リビューンってサイトやと,「これでSGLT2阻害薬の心腎保護効果は確定」とか言っちゃってるけど,
そりゃどうかな?
って印象がハンパない。
保護作用が作用機序的にも間違いなくありまっせ!っていうほどのエビデンス,この2つの試験から読み取れますか?
僕はレベルが低いんで,あんまそんな風には思えへんかったなぁ。
あと,1000人の患者・年あたりおよそ3人の下肢切断リスク上昇ではあるけれど(数字で表せば小さいけどって意味),
下肢切断っていうアウトカムってもんのスゴイ最低なアウトカムとちゃうのん??
ほんまにこのリスクがあるとわかってて積極的に使えますか?っちゅう話ですわ。
それに,この論文の用量を統合したりしている不確かな部分を見る限り,個人的にはあんまり信用できない。
SGLT2阻害薬を信用するのは,まだ今じゃないな。そう思ったのでした。
 けいしゅけ
けいしゅけ今回の記事はいかがでしたか? アナタのお役に立てていれば幸いです! もし良ければコメント欄から記事を読んだ感想や,ご意見,ご質問など寄せて下さい☆待ってます!!









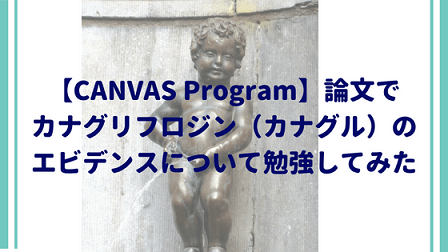
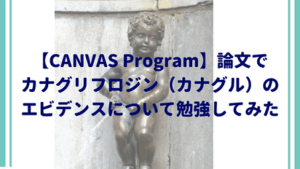
記事の感想など,ひとこと頂けますか?
コメント一覧 (4件)
勉強になりました。ありがとうございます。
湯浅秀道 様
コメントありがとうございます!そう言っていただけると本当にうれしいです
分かりやすい内容にて勉強になりました。
一つ質問があるのですが、SGLT2にて利尿作用があり、その作用機序について何か知っていることがあれば教えていただきたく存じます。
雄太様
コメントありがとうございます!!
SGLT2阻害薬の利尿作用については、現在以下のようなメカニズムが考えられています 1)
僕はこの辺りの文章を見て、作用機序はこんな感じなんやね。と考えています。
あとはこのコメントをきっかけに論文を探してみて、どういう作用機序か海外でわかったことはないか?を調べようかなぁと思いました
日々勉強です☆
1)日本高血圧学会(JSH2016)より SGLT2阻害薬の降圧はループ利尿作用による -http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/special/dmns/report/201610/548489.html